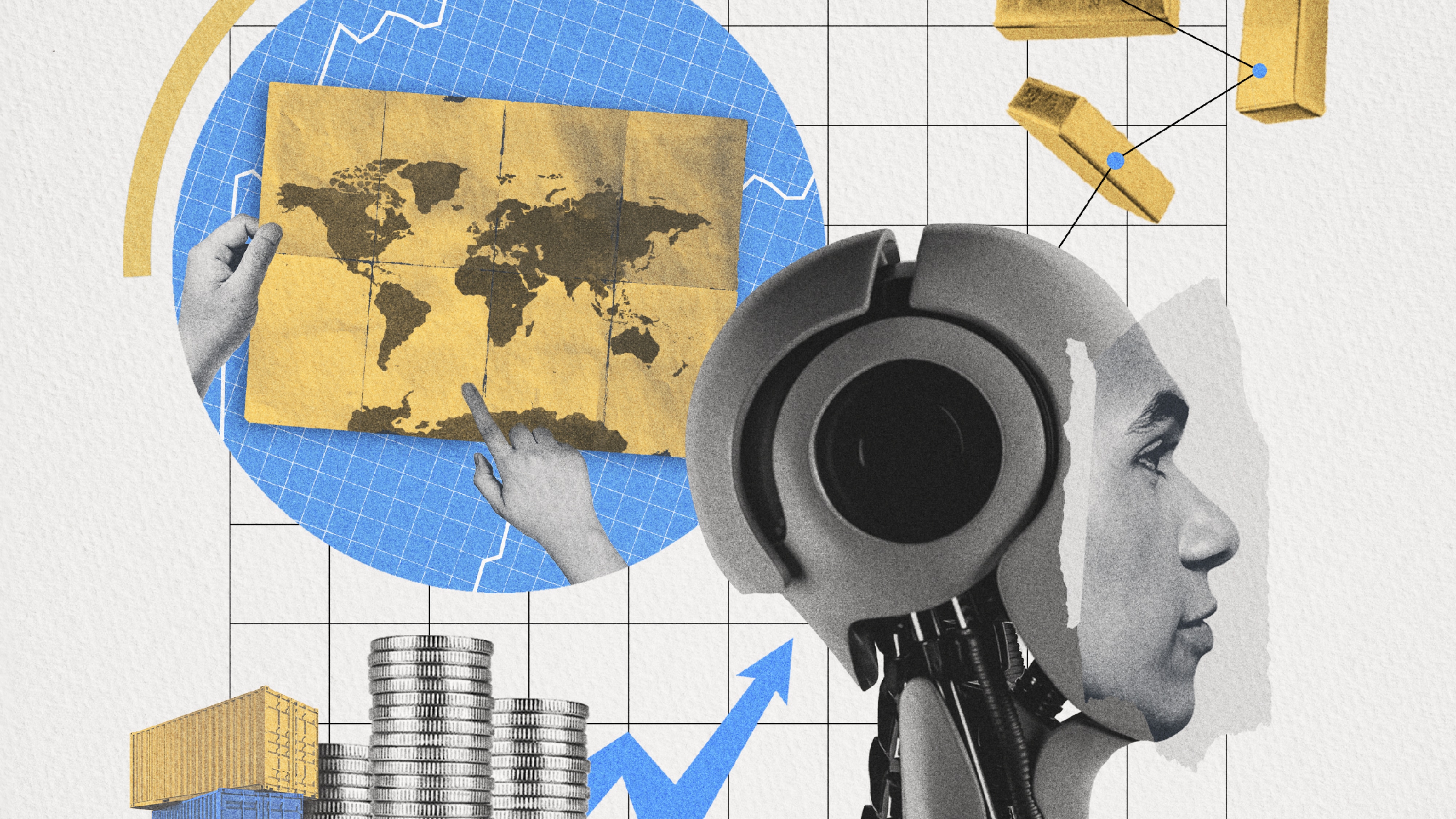日本の「就職氷河期世代」支援に見る、レジリエントな社会の構築

企業は「就職氷河期世代」を採用し、スキルを向上させることの重要性に注目し始めています。 Image: REUTERS/Stringer (JAPAN BUSINESS EMPLOYMENT)
- 日本では、40代・50代の労働者のうち、約1,700万〜2,000万人が非正規雇用や低賃金の仕事に就いています。
- こうした状況を改善するため、2020年以降、日本政府はこの世代を対象にした雇用支援プログラムを本格的に進めており、すでに多くの人が正社員として働き始めています。
- 企業側も、職場の世代間ギャップを埋めるために、この世代を積極的に雇い、スキルを伸ばしていくことの重要性に注目し始めています。
安定した雇用は、社会のレジリエンスを支える土台です。一方、経済が停滞すると、働く世代に長期的な影響を与える可能性があります。経済的に厳しい状況の中、社会全体のレジリエンスを維持するためには、雇用の安定を保つことが重要です。
日本では、1990年代にバブル経済が崩壊し、企業による採用が大幅に縮小しました。1990年代から2000年代初頭に就職活動を始めた人々は「就職氷河期世代」と呼ばれ、40代と50代を中心に1,700万~2,000万人が該当するとされています。この世代の多くは、今なお正規雇用の機会に恵まれず非正規雇用として働いており、労働条件や賃金などの待遇面において不利な状況に置かれています。
非正規社員には一般的に雇用期間が定められており、時給ベースの給与(2023年)も正社員の約7割の水準にとどまります。こうした状況は、安定した日常生活を送ることや将来計画を立てることを困難にします。また、就職氷河期世代は賃金上昇率も他の世代より低いと報告されています。厚生労働省の調査によると、初任給の引き上げなどにより若い世代では賃金の上昇率が10.0%(20~24歳)に達する一方、40代以上は7.0%(40~44歳)、6.9%(45~49歳)、2.9%(50~54歳)にとどまっています。
就職氷河期世代は現在、若手とシニア層のちょうど中間に位置する年代として職場における世代間の橋渡し役を担い、コミュニケーションの円滑化を図ることができます。
”このような状況に置かれているため、就職氷河期世代は貯蓄額が少なく、持ち家率も低い傾向にあります。さらに、年金受給者になる頃には、国民年金の支給額が今より3割減るとの試算もあり、最大2,000万人が引退後の生活に不安を抱えているとされています。
就職氷河期世代が将来、ある程度経済的に自立して暮らすことができなければ、その影響はその他の世代にも波及します。そのため、この世代の雇用促進は、国全体のレジリエンスを維持するためにも喫緊の課題です。日本政府および企業は、同世代を支援するため、就職支援サービスやキャリア形成支援などの取り組みを加速させています。
政府による就職氷河期世代の支援策
日本政府は2020年度から5年間、就職氷河期世代における「不本意非正規」の人や仕事に就けず悩んでいる人などを対象に、集中的に就労支援をしてきました。これにより、正規雇用の労働者は31万人増え「不本意非正規」の人は11万人減少したと内閣府は報告しています。
2025年4月には、今後の「就職就職氷河期」世代への支援強化に向けた関係閣僚会議を開催。2025年6月に発表された「新たな就職氷河期世代等支援プログラムの基本的な枠組み(案)」では、公務員として積極的に採用することに加え、「資格やスキル標準と結びつく指定講座の拡大を検討」、「AIを含むデジタルスキルに関する認定講座を拡大」、「リスキリングと合わせて他の一定の事業を実施する自治体に対する支援を強化し、無償のリスキリング機会を拡充することを検討」など、同世代のキャリア形成に関する具体的な方針も盛り込まれています。
厚生労働省は今年度、就職氷河期世代に向けた就労支援の一環として、厚生労働省が運営する無料の公的な就職支援機関、ハローワークに設置する専門窓口を通じた支援対象の年齢を59歳から35歳に拡張しました。さらに、事業主による氷河期世代の積極的採用や人材育成のための助成金を設置し、キャリア形成促進に向けたセミナーの開催などを実施。また、これと同様の支援が多くの自治体でも行われています。
就職氷河期世代を雇用するメリット
就職氷河期世代は現在、若手とシニア層のちょうど中間に位置する年代として職場における世代間の橋渡し役を担い、コミュニケーションの円滑化を図ることができます。また、効果的なマッチングやスキルアップ支援により、人材不足の解消につながることも期待され、企業にとってのへのメリットも少なくありません。
日本での取り組みは、世代間の経済的不安を防ぎ、レジリエントかつ包摂的な社会を築く上で貴重な示唆を与えます。
”人材確保に苦戦していた株式会社大光は、千葉県主催の企業向けセミナーに参加し、県によるマッチング制度を通じて雇用へと至りました。同社では、職場で必要となるフォークリフトなどの機械の操縦免許取得のほか、免許取得後のスキルアップなどの支援を実施。雇用した人材の定着にも注力しています。環境インフラの管理・運営を行う、アイテック株式会社もまた、就職氷河期世代の雇用を通じて人材不足を改善し、また昇給制度の見直しにより働きがいのある職場づくりを進めています。
不安定な情勢の中、安定した雇用はレジリエンスにつながる
世界経済フォーラムの「グローバルリスク報告書2025」では、調査に回答した企業の5%が、「経済低迷」を現在の主要リスクとして挙げています。世界的に経済の不安定さが常態化する中、どの国でも、今後同様の課題に直面する可能性があります。
日本での取り組みは、世代間の経済的不安を防ぎ、レジリエントかつ包摂的な社会を築く上で貴重な示唆を与えます。高齢化や経済格差の進行が共通課題となる中、日本の経験は長期的な社会的安定に向けた貴重なケーススタディとなるでしょう。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。