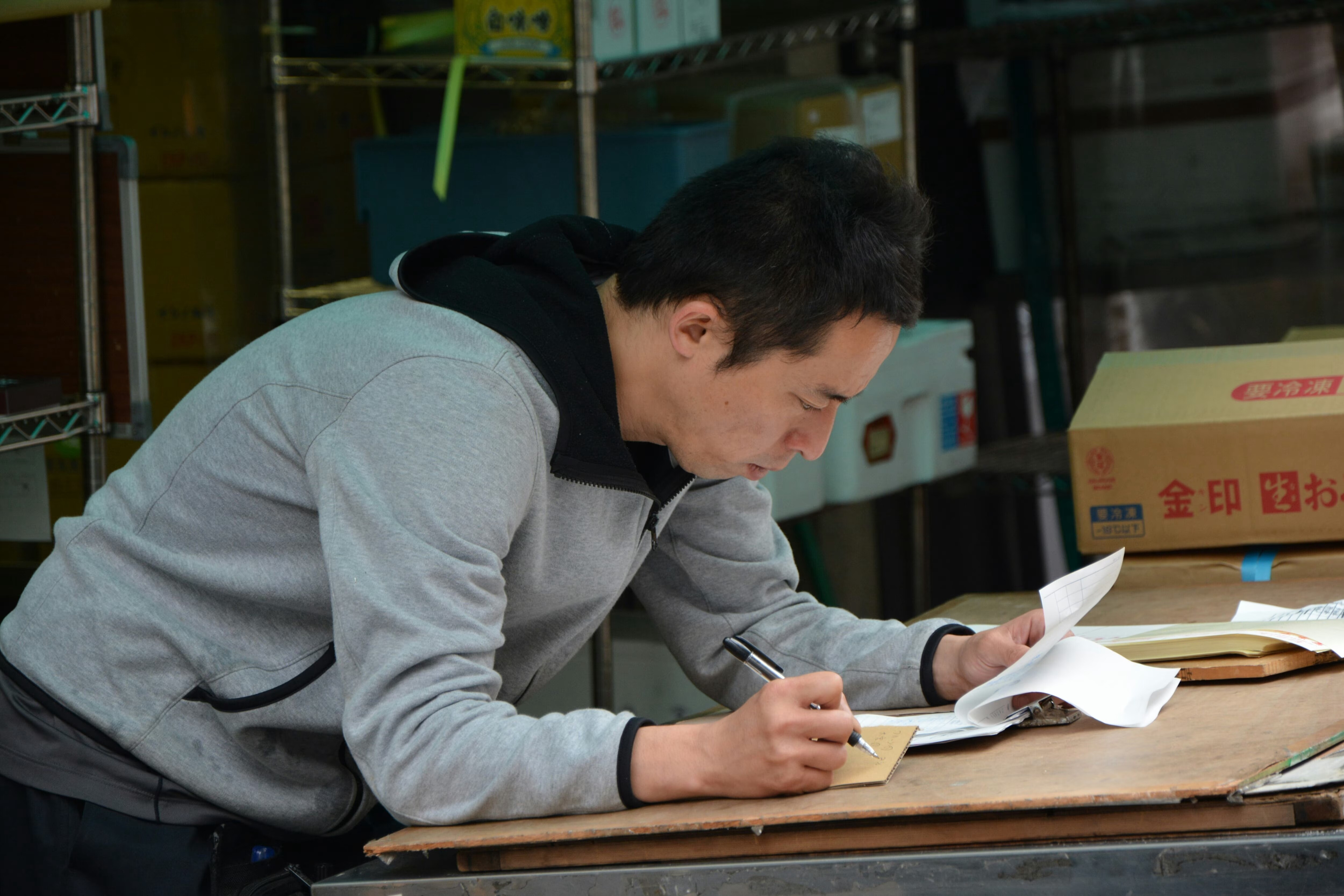デジタル時代に必要な力を育む、日本の金融教育

京都、日本。日本では、官民の取り組みにより、子どもが金融教育を受けるための支援が進められています。 Image: Unsplash/StephanieHau
- 世界的にキャッシュレス決済への移行が加速しており、多くの国で近年、デジタル取引が増加しています。
- キャッシュレス決済が普及する中、日本では子どもの金融教育を強化する取り組みが進められています。
- デジタル化が進む現代において、健全な消費習慣を育み、生涯にわたる資産管理スキルを身につけることを目的とした様々な施策が展開されています。
世界的に決済のキャッシュレス化が加速しています。韓国や中国、スウェーデンでは、キャッシュレス決済の比率が8割を超えており、現金をほとんど見かけない社会が現実になりつつあります。日本でも同様の変化が進んでおり、2019年以降キャッシュレス決済の比率は1.5倍に増加し、2024年には42.8%に達しました。取引規模は141兆円に上り、経済産業省が掲げていた「2025年までに4割」という目標を1年前倒しで実現しました。現在、最終的に目指している80%の比率に向け、決済インフラの整備や利用環境の向上が進められています。
こうした変化は、大人だけでなく子どもたちにも広がっています。2025年3月には、英国発のデジタルバンキングアプリ「レボリュート」が6~17歳を対象とした金融サービスを日本で開始しました。子どもはデビットカードを使い、親はアプリを通じて利用状況をリアルタイムで把握することができます。同年5月には、ソニー銀行が12歳以上の子ども向けに「ファミリーデビットカード」を発行。親の口座から直接引き落としができるようになりました。
このようなサービスの普及を背景に、「お小遣いをキャッシュレスで受け渡すこと」に賛成する保護者は6割近くに達しています。日本の1,000人以上の学生を対象とした最近の調査では、約75%が、お小遣いを含む家族間の送金をアプリで受け取った経験があると答えました。スマートフォン利用が当たり前となる中、キャッシュレスでの金銭のやり取りは、若い世代でも着実に定着しつつあります。
一方、キャッシュレス化が進むにつれ、金融トラブルに巻き込まれる子どもの低年齢化も指摘されています。金銭感覚や判断力がまだ十分に育っていない子どもや学生が、スマートフォンやSNSを通じて詐欺や過剰消費といったリスクに直面するケースが増加。現金を直接扱う機会が減ることで、「お金の重み」を実感する機会が失われ、数字上の残高だけで消費行動を判断してしまう危うさも懸念されています。こうしたことから、日本では、子どもを対象とした官民による金融教育が進められています。
政府による制度的な取り組み
文部科学省は2022年4月から金融教育を学校教育に組み込み、小学校から高校まで一貫したカリキュラムを導入しました。発達段階に応じ、「お金の役割」や「必要と欲しいの違い」といった生活に密着したテーマから、中高生になると、キャッシュレス決済や金融商品、将来の生活設計にまで学びのテーマが広がります。さらに、2024年8月には、金融経済教育推進機構(J-FLEC)が本格稼働。「官民一体となって戦略的に金融経済教育を実施する」ことを目的とする同機構は、教材提供、認定講師の派遣、教師研修の支援等を通じ、教育現場での取り組みがより実践的かつ持続的になることを支援しています。
経済産業省も子ども向けに「キャッシュレスって知ってるかな?」という教育用ガイドを公開。イラストや身近な事例を交、キャッシュレスの仕組みやリスク、適切な利用方法をわかりやすく解説しています。
企業による教育プログラムの広がり
金融教育の取り組みは企業にも広がっています。キッズ・マネー・ステーションは、幼児から大学生までを対象に、親子で学べる講座を全国で展開。実体験を生かし、講師陣が子どもでも理解しやすい形で金融リテラシーを育む活動を続けています。
NTTドコモは、家族とともに子どもの成長を育むことを目的とした「comotto」を通じ、子どもたちが「学ぶ・稼ぐ・ためる・使う」という一連のプロセスを体験できるコンテンツを提供。クイズやイベントを通じて金融行動を疑似体験させる取り組みは、楽しさと学びを両立させる新しい教育モデルとなっています。さらに、野村ホールディングスと連携した金融教育イベントでは、参加者に「お給料」としてキャッシュレス決済のポイントを配布。そのポイントを使ってお菓子を購入することで、お金を稼ぎ、使い、貯める一連の流れを実際に体験できる仕組みを導入しています。
またセブン銀行は、教育事業を手掛ける株式会社ARROWSと協力し、小学校向けの教材や動画を開発。修学旅行という子どもたちにとって身近なイベントを題材にし、計画的なお金の使い方やキャッシュレスの仕組みを学べるように工夫しています。これらの取り組みはいずれも、キャッシュレス化する社会に対応し、子どもたちがお金を主体的に考える力を育むことを目指しています。
キャッシュレス時代に、お金の価値を学ぶことの意義
スマートフォンのアプリひとつで買い物が完結する時代において、子どもたちがお金の価値を正しく理解することは極めて重要です。金融教育は、単にトラブルを防ぐためだけでなく、将来にわたり健全なお金の使い方や資産形成の習慣を身につける基盤となります。こうした取り組みは、個々人にとっての安心や安定だけでなく、レジリエンスのある経済を築くためにも、今後社会全体にとって不可欠な要素となっていくでしょう。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。