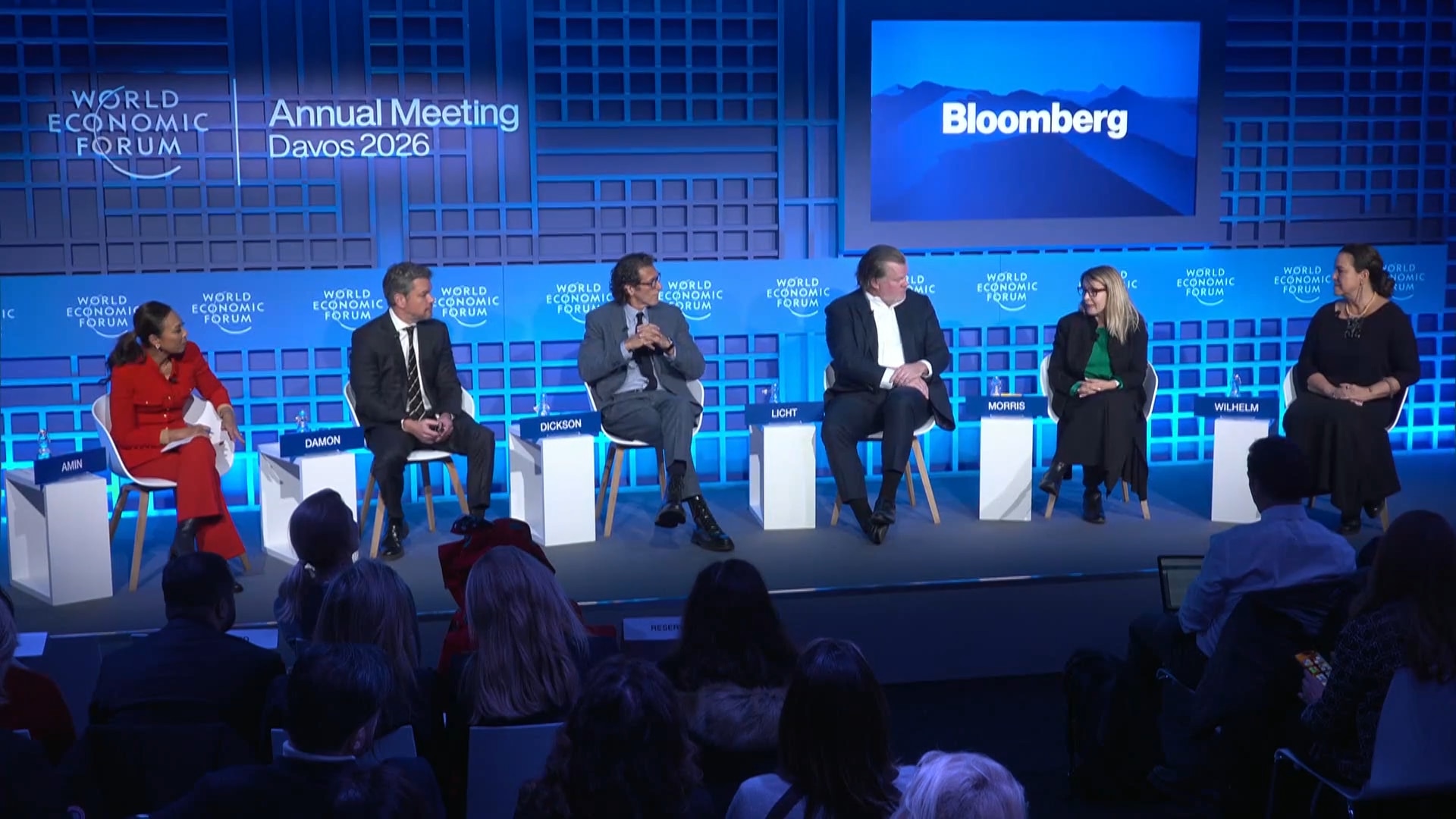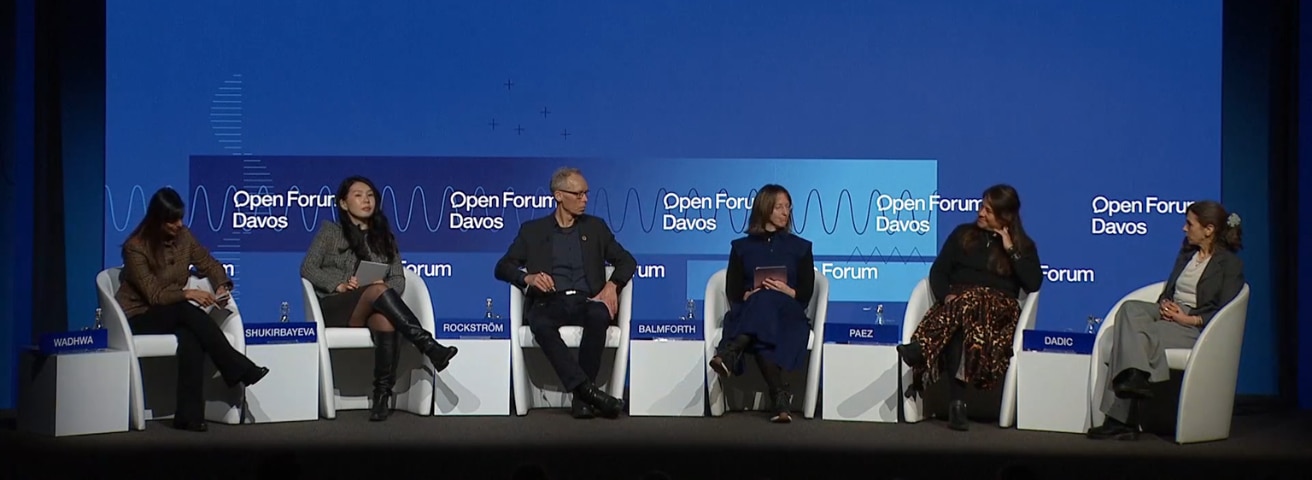持続可能かつレジリエンスのある社会の実現に向けた、水インフラの再構築

日本における水の安全保障は、脆弱な水インフラなどの課題を抱えています。 Image: Unsplash+/Karen Chew
- 日本の水の安全保障は、高齢化の進行、収入の減少、地域間格差、そして脆弱な水インフラなどの課題を抱えています。
- 政府は、データ、イノベーション、官民連携を通じて監視体制の強化を進めています。
- 東京のような大都市では、脱炭素化、再生可能エネルギー、そして生態系の保全に焦点を当てた野心的な環境計画が実行されています。
水は、すべての人の命と暮らしに不可欠であり、その安定供給を支える水インフラは、社会のレジリエンスと持続可能性の根幹を支えています。
国連によると、人類が利用できる淡水は地球上の水のわずか0.5%に過ぎず、今なお22億人が安全な水へのアクセスを持たずに暮らしています。日本は比較的水資源に恵まれており、国連食糧農業機関(FAO)によると、年間約4,300億立方メートルの水資源量を保有しています。しかし、水が豊富であることと、水へのアクセスが安定していることは同義ではありません。水を持続可能に管理・供給するためには、インフラの整備と維持、制度設計、人材確保、そしてテクノロジーの活用が不可欠です。
現在、日本の水道事業を取り巻く環境は、急速な少子高齢化や都市部への人口集中により、厳しい局面に直面しています。1970年代に大幅に整備されたインフラの多くが老朽化し、維持・更新が喫緊の課題となる一方、水道料金収入の減少や技術者の不足、地域間の格差も顕在化しています。こうし背景のもと、政府、自治体、企業は、水インフラの構築とレジリエンス強化に向けた取り組みを進めています。
可視化による改善の推進
国土交通省は2024年12月に「水道カルテ」を公表し、全国約1,300の水道事業者の経営状況と施設の耐震化率を可視化しました。このデータにより、水道料金で給水コストを賄えていない事業者や、浄水場や配水池の耐震化率が全国平均を下回る施設を抱える地域の課題が明らかになりました。
2022年度の時点で、料金回収率が100%を下回り、かつ耐震化率も平均以下である事業者は全体の約46.5%。特に小規模な自治体では、老朽化対応や災害対策の遅れが目立ちます。国はこうした恐恐に対応するため、全国の事業者に対するアンケート調査や実態把握を進め、2026年度を目途に新たなガイドラインを策定する予定です。加えて、広域連携や官民連携の推進、耐震化や省エネ型設備の導入支援も進められています。
都市部での持続可能な水道運営
東京や大阪などの都市圏では、数千万単位の人口を支えるためのインフラおよび水源の管理が求められています。東京都水道局は2025年3月に、新たな「環境5か年計画(2025–2029)」を策定しました。この計画は、「脱炭素社会の実現」「循環型社会の構築」「水と緑の保全」「多様な主体との連携」という4つの基本方針に基づき、45の具体的な施策を展開しています。
中でも注目されるのが、2030年までに温室効果ガス排出量を2000年比で50%削減し、再生可能エネルギーの利用割合を60%以上に引き上げるという野心的な目標です。また、水源林の保全や都市緑化、地域住民との協働による環境教育にも注力しています。こうした都市部の先進的取り組みは、人口が集中する地域の水道を健全に維持するための対策に加え、社会インフラの脱炭素化とレジリエンス強化を同時に実現する道筋を示しています。
人口が集中する都市部と過疎化の進む地方の双方において、地域特性を生かした水インフラの再設計とレジリエンスの強化が、今まさに求められています。
”テクノロジーの活用による効率化
過疎高齢化が進む地方では、水道料金収入の減少などにより、水道の維持管理を効率化することが喫緊の課題です。こうした地域では、最新のテクノロジーが、持続可能な水インフラの確保に向けた鍵となります。
国土交通省は、上下水道分野でのデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するため、「上下水道 DX技術カタログ」を通じて、施設の劣化予測、点検・調査、データ管理などに活用できる119の先端技術を紹介。自治体や事業者による活用が期待されています。
さらに、官民連携による取り組みも進んでいます。その一例が、株式会社ウォーターリンクスと和歌山県串本町、鳥取県湯梨浜町、鳥取県北栄町、熊本県南関町、宮崎県宮崎市など複数の自治体の連携による、水道スマートメーターの実証実験です。
この実験では、水道メーターに搭載された無線子機により、正確でスムーズな一括無線検針を行うことができる「AMR(自動検針)方式」を活用。検針作業の効率化や人手不足の緩和だけでなく、宅内漏水の早期発見や高齢者の見守りサービスの実現を目指します。こうした取り組みは、業務効率化にとどまらず、地域全体の生活の質向上の原動力となり得ます。
未来を見据えた連携と行動
社会構造の変化や気候リスクが高まる中、水インフラには、単なる設備の更新や補修だけでなく、テクノロジーを活用した効率化が求められています。国や自治体、企業、市民が互いに連携し、地域の実情に応じた持続可能なモデルを構築していくことが不可欠です。
世界経済フォーラムのレポート「Water Futures: Mobilizing Multi-Stakeholder Action for Resilience(水の未来::レジリエンスに向けたマルチステークホルダーの行動の促進)」でも指摘されているように、水の未来は、多様なステークホルダーが共に行動することによって守られます。人口が集中する都市部と過疎化の進む地方の双方において、地域特性を生かした水インフラの再設計とレジリエンスの強化が、今まさに求められています。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。