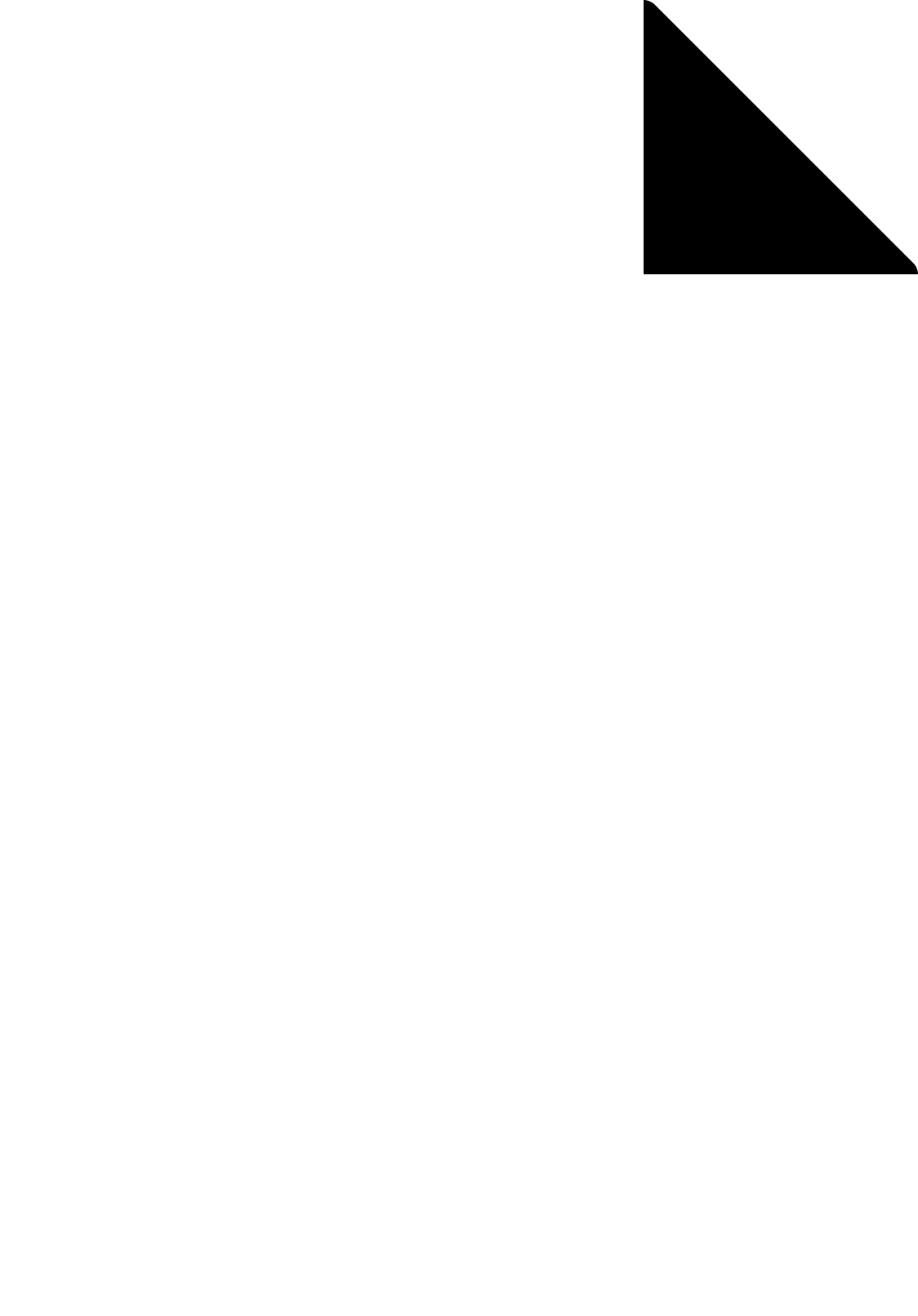誰も幸せになれない「ハイブリッド勤務」の落とし穴

「ハイブリッド勤務」は、柔軟性のある妥協策として提示されることが多い。しかし現実には、どちらの世界にとっても最悪の結果をもたらす可能性が高い。 Image: 2021年 ロイター/Henry Nicholls
「ハイブリッド勤務」は、柔軟性のある妥協策として提示されることが多い。オフィスでの勤務とリモートワークそれぞれの長所を最大限活かせる、という触れ込みだ。しかし現実には、どちらの世界にとっても最悪の結果をもたらす可能性が高い。
こうしたハイブリッド勤務を最も声高に提唱してきたのは、都市中心部のオフィス物件に多額の投資を行っている商業不動産のオーナー、そして彼らと取引のある銀行や不動産業者である。
彼らにとって、その利点は明らかだ。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック(世界的大流行)が終わった後、ハイブリッド勤務になれば、都市中心部のオフィス利用の低下を最小限に食い止められるだろう。
だが、公共交通機関の事業者や多くのサービス企業も含め、それ以外の企業や従業員にとっては、ハイブリッド勤務はコストがかかり非効率であるという結果になりそうだ。
企業にとって都市中心部のオフィススペースにかかる費用は依然として高いままだろうし、従業員の側でも、自宅を拠点に働くには、これまでより広い住居空間が必要でコストもかかる。しかし、その多くは限られた時間しか利用されない。
交通費や通勤時間は依然として大きく、その負担は企業が担うか(人件費の上昇と生産性の低下)、従業員が担うか(可処分所得の減少と拘束時間の延長)、いずれかである。
公共交通機関の事業者は、利用回数の減少、設備稼働率の低下、運賃収入の減少に直面し、固定費が支出に占める比率が比較的高いことを思えば、厳しい財務状況に直面するだろう。
オフィス労働者に依存していた都市中心部のサービス企業が売り上げの一部を失う一方で、郊外及び都市以外のサービス企業の売り上げ増加は限定的であり、双方ともスペース稼働率は不十分になる。
結果として、ハイブリッド勤務によって、大半のオフィス、小売店舗、住宅、交通システムの稼働率は下がり、完全なオフィス勤務、あるいは完全なリモートワークというモデルに比べ、ほとんどの企業・労働者は不利な状況に陥るだろう。
ほぼ同じ理由により、ハイブリッド勤務というシステムは、あるレベルの経済産出量に対して消費するエネルギーが増大し、エネルギー効率という点でも劣る可能性が高い。
企業から見れば
大企業の大半は、COVID-19の制圧が実現した際には、週労働時間の半分ないしそれ以上、オフィスでの勤務に復帰するよう社員に命じる構えでいる。
その主な根拠は、オフィス中心の勤務でなければ、効果的な協力や創造性、チームワークを確保できず、組織全体でのアイデアや知識、文化の伝達も望めないからである。
オフィス勤務を提唱する見解では、集約的なオフィスで勤務する時間が減れば組織としての一体感が失われ、経営陣による効果的な監督・統制が困難になる、とされている。
だが、リモートワークの比率が比較的少ないとしても、直接の対面による協力やネットワーク形成によるメリットとされるものは大幅に限定されてしまう。
従業員がオフィスに出社する日数を平均週3日としよう。これはまだ比較的多い想定だが、それでも任意の2人の従業員が直接対面する時間は、(週5日出社に比べ)わずか36%に減少してしまう。
従業員が週2日オフィスに出社する場合、任意の2人の従業員が直接対面する平均時間は、わずか16%になる。出社日は週全体を通じてランダムに分布しているという想定である。
そこで多くの企業は、毎週のオフィス出社日数を比較的多め、一般的には3日以上にする必要性を口にしているのである。
同一のチームや関連の深い職務に携わる従業員の間の接触時間を増やすため、多くの企業はローテーションシステムを推進し、特定の曜日にオフィスに出社することを従業員に求めている。
しかし同じチームに属する労働者同士の接触時間を増やすには、異なるチームに属する、また関連の薄い業務に携わる従業員の間の接触時間をさらに減らすしかない。
またハイブリッド勤務モデルでは、オフィスの利用率を最大化し、必要スペースを最小限に抑え、オフィスに要するコストをできるだけ節約するように、週を通してオフィス出社スケジュールを設定する必要がある。
従業員全員が月曜日はオフィス出社、金曜日はリモート勤務にしようとすれば、企業は全員分のデスクを用意せざるを得ず、オフィスに要するコストはまったく節約できない。
そこで大半の企業は、かなり厳格なスケジュール設定を求めるハイブリッド勤務システムに力を注いでおり、そうなれば従業員の側ではあまり柔軟性を享受できないことになる。
従業員から見れば
企業がオフィスの利用率を最大化し、従業員間の協力を促進し、その一方で不動産コストをなるべく押さえようとするならば、従業員から見た選択肢は大幅に少なくなる。
リモートワークの比率が比較的低いとしても、自宅で作業するスペースを確保するためにはもっと部屋数が必要になり、それだけでも住居費がかさむことになる。
そのうえ、週3日、あるいはそれ以上オフィス出社を求められるとなれば、せっかく用意した在宅勤務用のスペースも部分的にしか利用されないことになる。
週の半分、あるいはそれ以上オフィス出社を続けるとなれば、通勤に要する時間・費用もそれほど減りはしない。
実際には、日々の通勤コストはむしろ高くなる可能性が高い。交通機関では、利用回数減少に対応するため、距離や(定期券の場合の)1日当たりの運賃を引き上げて固定費を回収せざるをえないからだ。
だが頻繁にオフィスに出社するとなれば、住宅費用の節約や広い住宅に住み替える費用をねん出するために都市中心部から郊外・都市以外の地域に転居するという選択肢も限定されてしまう。
結局のところ従業員は、恐らくは高くなる運賃を払いつつ頻繁に通勤せざるを得ず、しかもリモートワークのためにこれまでより広い家に住む必要があり、それでもオフィスとは縁が切れないためにもっと遠方に転居することも難しい、ということになる。
公共交通機関から見れば
公共交通システムは、高い固定費を回収しつつ運賃を低く抑え、その一方で非常に良好なエネルギー効率を維持するために、乗客数の多さと設備稼働率の高さを頼りにしている。
朝夕の通勤ラッシュ時の大量輸送システムに見られる極端な混雑は、長年にわたり「バグではなく仕様」だった。
ハイブリッド勤務になれば、利用回数と運賃収入は減少するが、システムを運用・維持する間接費の削減は、可能だとしてもさほど大幅ではない。
公共交通機関の事業者にとって、収入の減少を補う方法があるとすれば、運賃値上げ、政府補助金の増額要請、あるいはネットワークの縮小だけである。
他の企業と同様、公共交通機関の事業者も、できるだけ効率よく輸送能力を稼働させようとする。つまり、通勤客が週全体を通じて均等に分布しているのが理想ということになる。
従業員全員が月曜日はオフィス出社、金曜日はリモート勤務にしようとすれば、公共交通システムは週の初めは相変わらず超満員で、ウィークエンドはガラガラ、全体として運賃収入は減少ということになるだろう。
したがって事業者は、恐らくは変動運賃を導入することにより、企業・従業員がオフィス出社をできるだけ週全体で均一化するように誘導する必要があるだろう。
サービス企業から見れば
都市中心部に立地し、通勤客に依存していた小売店、レストランその他のサービス企業は、リモートワークへの移行によって手痛い打撃を受けるだろうが、ハイブリッド勤務モデルもあまり大きなメリットにはなりそうにない。
ハイブリッド勤務モデルでも、都市中心部の店舗を利用する顧客数はやはり減少する可能性が高いが、多くの場合、家賃、固定資産税、光熱費、そしてある程度は人件費も固定されたままか、少なくとも簡単には削れない。
同時に、郊外や都市以外の地域のサービス企業にとっても、多くのコストが固定的である一方で、オフィス出社を続ける必要があるせいで売り上げ増大の可能性は限定的ということになるだろう。
都市中心部、郊外や都市以外の地域のサービス企業は、結局のところ、潜在的な顧客ベースを分割共有することになる一方で、双方のグループとも店舗の稼働率は低く、収益性は悪化してしまう。
エネルギー利用
ハイブリッド勤務によって、労働者は、これまでは勤務先企業が負担してきた光熱費・電気料金の一部を肩代わりせざるを得ないが、それに応じた賃金・給料の調整が行われる可能性は低い。
ハイブリッド勤務によって、使用するオフィス、住宅用スペースの総量は増加する可能性が高く、全体としてのエネルギー消費を押し上げる。
さらに、満員状態で利用されている集約的なオフィスや交通システムでは、エネルギー効率が非常に高くなるのが普通だが、住宅用物件ではエネルギー効率がはるかに低くなる場合が多い。
交通システムのエネルギー消費が減少するとしても、そのペースは乗客数・利用回数の減少に比べてはるかにゆっくりしたものになるだろう。
また、ほとんどのサービス企業にとっては、エネルギー消費及びそのコストはほぼ固定費に近く、都市中心部でも郊外でも店舗の稼働率が低くなればエネルギー利用効率・コストの双方が押し上げられる。
結局のところ、企業や従業員から公共交通機関の事業者、サービス企業に至るまで、ほぼすべての当事者が、ハイブリッド勤務によって、完全なオフィス勤務や完全なリモートワークのいずれに比べても不利な状況に陥ることになりそうだ。
*この記事は、Reutersのコラムを転載したものです。
このトピックに関する最新情報をお見逃しなく
無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
最新の情報をお届けします:
労働力と雇用
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。