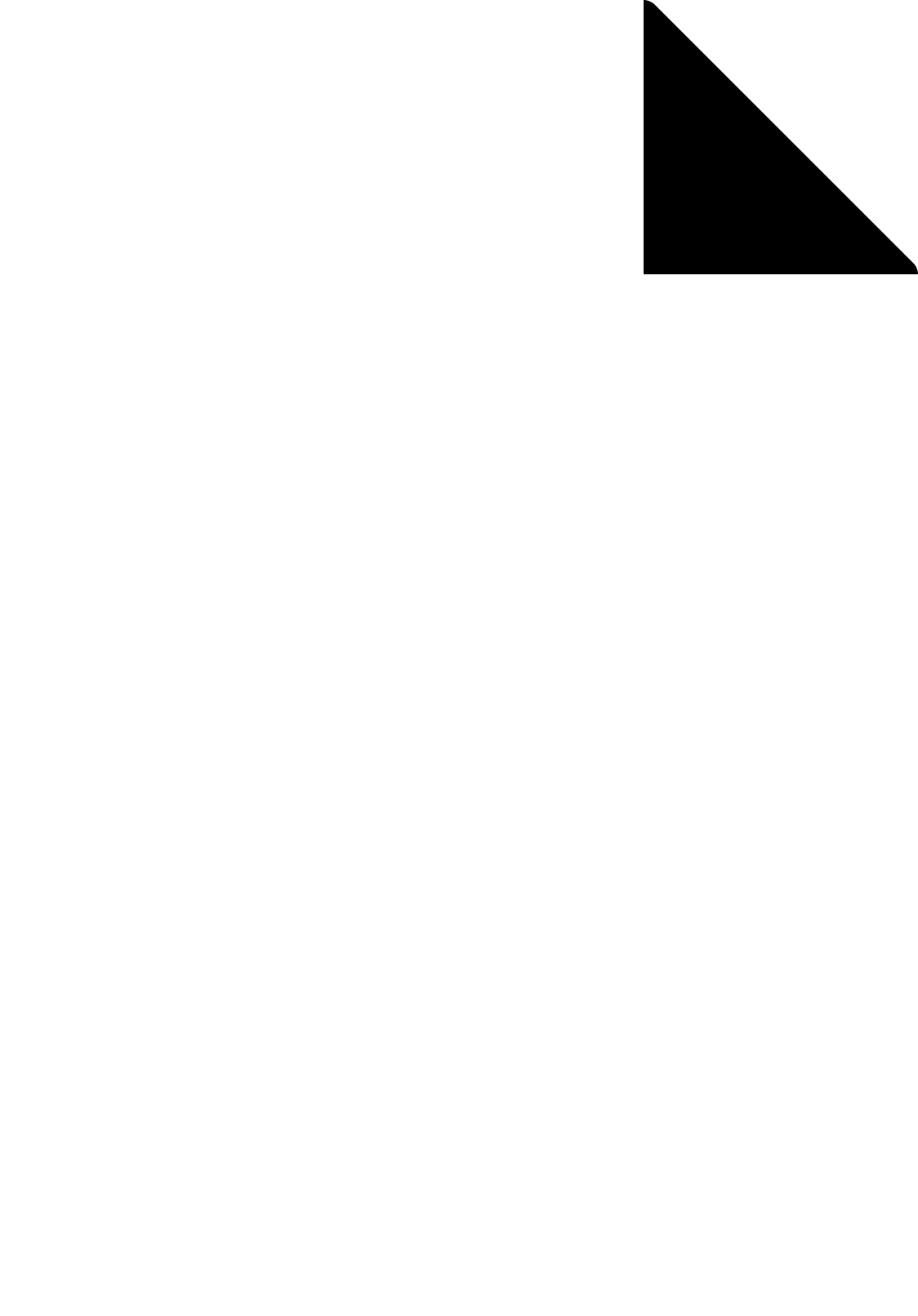コロナで通勤はなくなるのか、「職住革命」阻む要素も

先進諸国では今後、新型コロナウイルスの感染拡大が、人々の働く場所と住む場所、そして両者をつなぐ交通システムの長期的な構造変化を加速させる公算が大きい。 Image: 2021年 ロイター/Kim Kyung-Hoon
先進諸国では今後、新型コロナウイルスの感染拡大が、人々の働く場所と住む場所、そして両者をつなぐ交通システムの長期的な構造変化を加速させる公算が大きい。
しかし不動産市場と交通システムには、都市中心部から近郊や地方都市へと職場が幅広く変化していく流れにブレーキを掛ける非常に大きな「硬直性」が存在する。これが構造変化の速度を遅らせるだろう。
土地使用の現在の分布は19世紀の鉄道網の発達と10世紀のモータリゼーションの産物だ。人々が自宅から職場までより長い距離を移動できるようになったからだ。
多くの企業重役や専門職従事者であれば、ビジネスの出会いや社交がしやすく、文化施設へのアクセスもしやすい優位性から大都会の中心に住む余裕もあろう。だがほとんどの労働者は、住宅費が安い近郊や衛星都市で暮らさざるを得ない。
その結果、労働者は自宅と職場の往復を強いられる毎日になる。特に大都市や主要都市に通勤する場合はお金、時間、エネルギーの面で、相当な代償を払わなければならなくなる。肉体的、精神的な負担もかなり大きい。
一方で、この30年間で通信技術が進歩を続けた。つまり電子メールやインスタントメッセージ、低料金のビデオ会議システムなどが相次いで登場し、リモートワークの実現可能性は高まった。職場同僚との連携やサプライヤー、顧客とのつながりが不可欠なサービス業でさえ、その例外ではなかった。
特権から日常へ
英国家統計局が2019年に実施し昨年3月に公表した調査は、同国労働人口に占める在宅勤務者の割合は、比較するベースが低いとはいえ、着実に増加していたことを示した。
新型コロナの登場以前ですら、労働人口の5%は主に自宅で働いていた。調査の直前1週間に最低1日在宅勤務をした人は12%いた。
在宅勤務の普及はフルタイムでもパートタイムでも、伝統的には通勤者が暮らす地域であるロンドンとサウス・イーストで最も進んでいた。年齢が上であるとか職場での上位者、さらには給与水準が最も高い人が、より在宅勤務に携わっていた。
通勤時間を減らす、あるいは全く通勤しない環境を求める傾向は強く、できるなら自宅で働きたいと思っている勤労者も多いことがうかがえる。
ただ当時は、リモートワークは地位の高い人や、引退も近いベテランに与えられた特権との固定観念のために、普及が阻まれていた。事態を一変させたのが新型コロナ感染の大流行だ。多くのホワイトカラー労働者にとって在宅勤務は技術的に可能であることも証明された。社会の許容度のハードルも下がった。これなら導入に弾みがつきそうなものだ。
通勤地獄
英運輸省の昨年公表の統計資料によると、19年にロンドンの労働者が毎日通勤にかけた時間は平均1時間32分で、他の地域の平均1時間弱よりずっと長かった。1年間で見ると、ロンドンの労働者のほうが実に140時間も余計に通勤時間がかかった形だ。
とりわけロンドン中心部への通勤は往復平均で1時間48分と一番長かった。鉄道利用の場合は2時間18分になった。
国家統計局の別の昨年の報告書を見ると、ロンドンは世界の他の大都市と同じく、周辺部と衛星都市からの何百万人もの通勤客を受け入れるうえで、公共交通システムに依存していたことが分かる。
感染拡大前、ロンドン中心部で働く人の3分の2は地上の鉄道、地下鉄、バスといった公共交通を利用していた。中規模都市では通勤の公共交通利用比率は15%、その他地域では10%弱にとどまった。
マイカーよりも公共交通で通勤する方がずっと省エネにつながる。だからこそロンドンの輸送分野における1人当たりエネルギー消費量は、国内の他の地域の半分未満だ。
その半面、通勤者は料金や時間などの面で重い負担を強いられ、体と心にマイナスの影響を被ってしまう。新型コロナの出現前でさえ、専門家は公共交通機関の混雑が、インフルエンザなどの呼吸器系疾患の感染を助長すると警告していた。
需給のミスマッチ
交通機関は19世紀と20世紀に発達し、都市の規模と形態に変容をもたらしたが、今や通信技術の進歩が再び都市の様相を新たにする可能性が高い。
リモートワークの増加は、都市中心部にオフィスを構えたり、これに伴うさまざまなサービスを提供したりする必要性が薄れることを意味する。反比例するように、近郊や中規模都市、地方で働く場所を拡充する動きの強まりが見られる。そうした拡充のほとんどは住居内ということになるため、より大きく、部屋数のある家を大都市中心部から一段と離れた地域で見つけようということになる。
ところが不動産市場はそれほど柔軟ではない。これがリモートワーク普及の第一の制約になる可能性が高い。イングランド地域にある住宅は約2,440万戸だが、過去10年間の新規供給数は毎年平均で18万戸しかなく、年間の伸びでわずか0.7%だ。
短期、中期的には、都市周辺部での在宅勤務需要が増えても、基本的に固定化された中古住宅在庫で対応するしかない。住宅在庫が硬直化しているからこそ、コロナ禍によって需給のミスマッチが高じ、都心の住宅価格や家賃が落ち込む一方で、他の地域は高騰する姿が鮮明になっている。
商業不動産も似たような問題に直面している。都心部では労働やサービス提供用のスペースが供給過剰となり、他の地域では逆に足りていない。都心部の商業不動産を居住用に転換したり、他の地域に新たなスペースを建設したりするには何年もの時間が必要だ。
「ハイブリッド勤務」のリスク
商業不動産オーナーや企業経営者は、コロナ禍とリモートワーク需要に対応するため、「ハイブリッド勤務(在宅と出社の組み合わせ)」を推奨している。
だが各種調査によると、経営者は出社の割合を60%と想定する一方、従業員は最大でも4割、場合によっては2割の出社が好ましいと考えるなど、認識にはずれがある。
その上、ハイブリッド勤務は出社、在宅双方のデメリットを顕在化させかねない。従業員は毎週2日から3日だけ職場に行くために、引き続き都心近くに住むことを強いられ、遠く離れた場所の、より安く広い家に引っ越せない。また在宅勤務をする以上、住居そのものは大きなものにする必要が出てきて、住宅費がかさむ。揚げ句の果てに少なくとも週数日分の通勤代は続くので、恐らくトータルの負担は増加する。
経営者にしてもハイブリッド勤務を導入すると、確保しておく必要のあるオフィス面積が40〜80%減るとみられる半面、その前提には交代で出勤する従業員が職場で机や機器を代わる代わる共有したりする態勢が必要になる。新型コロナ感染拡大の中で、机や機器の共有が果たして適切かどうかは議論を呼ぶだろう。
商業用不動産オーナーの立場からすると、ハイブリッド勤務が採用されてもスペースの需要はかなり減少に向かうので、供給過剰が何年も続き賃料を押し下げる可能性が高い。
公共交通事業者にしてみれば、毎日の通勤客の大幅減少を目の当たりにし、「規模の経済」を享受できにくくなることから、料金の引き上げを迫られるかもしれない。
つまり、コロナ禍と在宅勤務の拡大が、職場と家をどこにするかという点で革命的な変化を起こしておかしくないことは明示されるのだが、不動産と交通のシステムの問題が大きな阻害要因となり、遅々として変化が進まないということになりかねない。
*この記事は、Reutersのコラムを転載したものです。
このトピックに関する最新情報をお見逃しなく
無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
最新の情報をお届けします:
労働力と雇用
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。