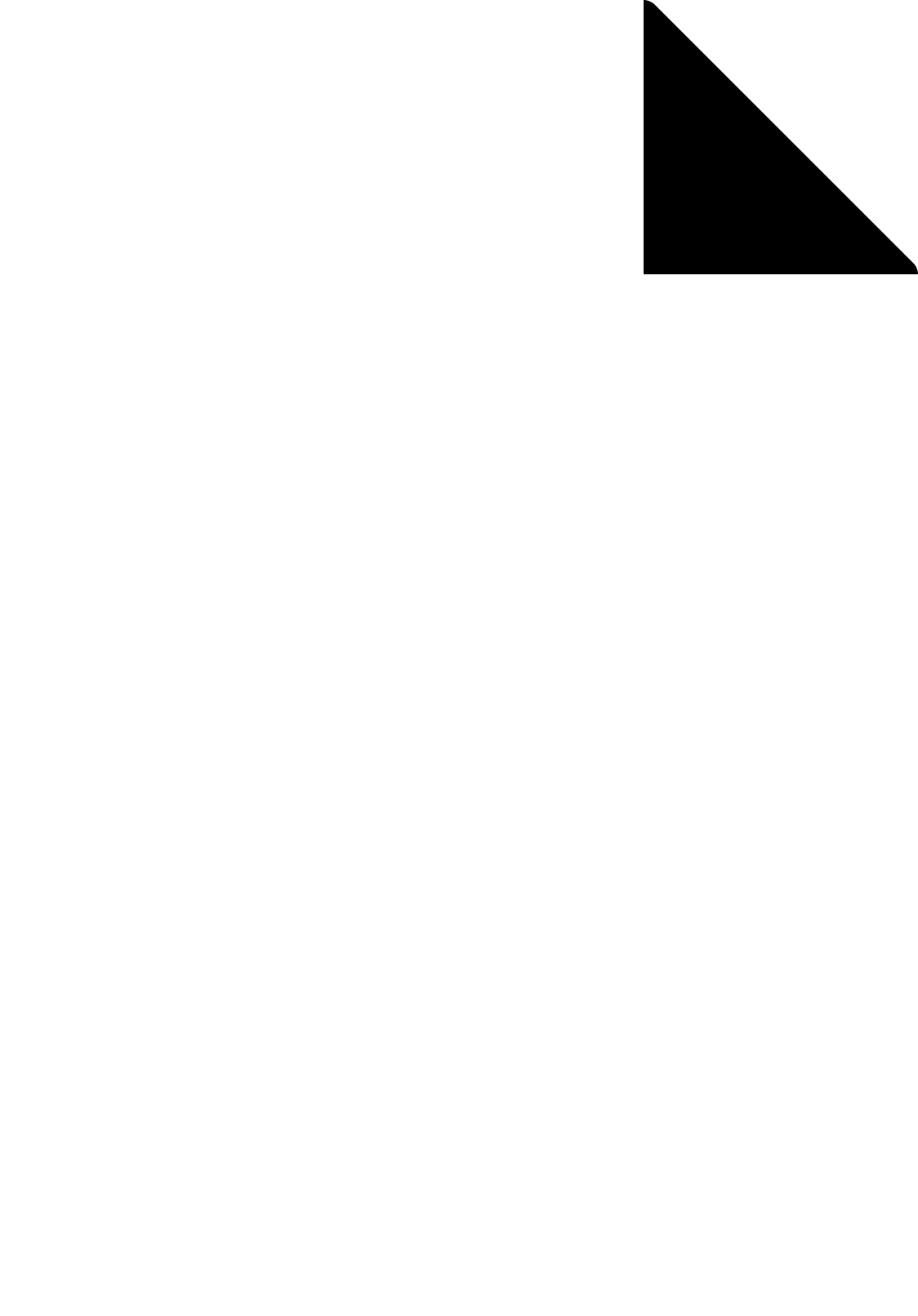エネルギー転換:新型コロナ感染拡大からの回復の取り組みが示す、5つの重要な教訓

Image: Gustavo Quepón/Unsplash
世界のエネルギー転換は過去10年間で多くの節目を迎え、大部分で期待を上回る成果を上げています。技術イノベーションや起業家精神、政策立案者と企業のリスクテイクのおかげで、2010年以降、設備能力は太陽光発電で7倍に、陸上風力発電で3倍に増加しました。かつては夢物語だと考えられていた再生可能エネルギーも、一部の国では発電構成に占める割合が化石燃料を上回っています。また、この10年間で、近代的なエネルギーにアクセスできない人の数は大幅に減少しました。
それでも、まだ長い道のりが先に待っています。2019年の時点で、世界の一次エネルギー供給の81%は依然として化石燃料に頼っています。また、発電構成に占める石炭の割合が着実に減少しているにもかかわらず、石炭を用いた発電量は、エネルギー需要が増大している地域を中心に絶対量でみると増加しています。
2021年世界経済フォーラムエネルギー転換指数における10年間のベンチマークデータ分析によると、分析対象の115カ国のうち、エネルギー転換に向けて安定的に上昇軌道を描いている国はわずか10%でした。大半の国で何らかの前進がみられるものの、それを持続させることが困難だったのです。誓約やコミットメントが具体的な行動に移されることが期待される「実現と行動の10年」に向けて一貫して前進を続けることが、タイムリーで効果的なエネルギー転換にとって最も重要になります。また、スピードや方向性とともに、エネルギー転換のレジリエンス(適応、回復できる力)にも重点を置かなくてはなりません。レジリエンスを高めることで後退する事態を防ぎ、混乱が生じた場合でもそのプロセスの早期回復が可能になります。

世界的なエネルギー転換が進むにつれ、転換に伴うリスクの状況も急速に変化していきます。前進を積み重ね、これを加速させていけるかどうかは、技術進歩を継続させるだけでなく、エネルギー転換の社会経済的および地政学的な結果に対処することにもかかっています。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)からの復興に向けた取り組みは、この点に関して5つの重要なポイントを示唆していると同時に、苦労して実現した前進を阻害しかねない幾つかの盲点も明らかにしています。
1. エネルギーは依然として経済成長と強く結びついている
この相反する関係に対処することが、エネルギー転換の核心となります。新型コロナウイルス感染拡大による経済的ダメージを軽減するための復興に向けた取り組みは、グリーン化の大きな起爆剤になるものと期待されていました。ロックダウンを受けて歴史的減少をみせた排出量は、多くの国でまたたく間にパンデミック前の水準に戻りました。また、エネルギー転換の関連セクターに数兆ドルが確約され、効果的な資金注入が行われていますが、ほとんどの国ではその大半が炭素集約型セクターに割り当てられており、今後数年間は排出量が変動しない可能性があります。グリーンで未来対応のインフラへの投資は、さらなる経済成長と雇用創出を促す強い原動力になります。

2. 経済回復がすべて等しくエネルギー転換を後押しするわけではない
国際通貨基金(IMF)によると、世界経済の正常化がなかなか進まない中、新興国および発展途上国の経済回復はさら遅れる予測が示唆されており、多くの国のGDPがパンデミック以前の水準に戻るのは2023年以降になるとの見解が示されています。経済回復がばらつくことやそれに伴う財政上の問題が、こうした国におけるエネルギー転換への投資を促す力を限定させることになります。短期的には、ワクチンの生産と流通を加速させ、公平な分配を徹底することが、新興国および発展途上国の迅速な経済回復を実現するために重要です。
3. 最も脆弱な層を保護しなければならない
パンデミックは、所得の不平等がもたらす破壊的な影響が「感染リスクの増大」と「所得・雇用喪失がもたらす経済的コスト」にあることを浮き彫りにしました。同様に、エネルギー転換の影響も、不均衡に社会の脆弱層に及ぶと考えられます。例えば、従来型エネルギー源のバリューチェーン全体で起こる労働市場の混乱や、補助金制度の改正または炭素税に起因する支払い能力の問題などです。このため、エネルギー政策や投資判断の評価に包摂的なアプローチをとり、「公正な移行」の道を優先して分配的思考に対処することが、エネルギー転換を包摂的に実現するために不可欠です。
4. 国際協調の課題は今後も残る
パンデミックは、国際協調によってグローバルヘルスの非常事態を早急に鎮静化し、この事態に対応することの限界をあらわにしました。エネルギー転換の主因である気候変動は、すでに世界の多くの地域で食料や水不足を引き起こしています。炭素税が貿易と競争力に影響を及ぼすと見込まれることに加え、近い将来には、気候変動の影響から前例のない規模で移住の波を引き起こすと予想されます。こうした事態を受け、グローバルな連携の強さと有効性がこれまで以上に試されることとなり、すべてのステークホルダーグループを対象とした強固な協力メカニズムを構築し、この世界共通の課題に対処することが不可欠になります。
5. すべての市民の支持を取り付けなければならない
抑制策への市民の協力が得られないことや、ワクチン接種を躊躇する声も上がっている現状により、急速に拡大する非常事態への対応支援を市民に促す難しさが明らかになりました。調査によると、人々は、急拡大し期間が長期に及ぶ危機や、遠く離れた地で起きている危機の影響を過小評価するということがわかっています。同時に、一貫性のないコミュニケーションや行政の誤算は信頼喪失を招き、誤った情報を生むことにもなりかねません。
現代の経済・社会全体にエネルギーが普遍的に存在していることを考慮すると、エネルギー転換はシステミックな影響を及ぼすものであり、転換には個人の積極的な参加が必要になります。予定を数十年先に延長し、人類の共通問題に対する個人の行動の不足や、世界の遠い場所で起きている極端な気候現象を把握しているだけでは、エネルギー転換の規模とスピードの必要性が個人に伝わらない可能性があります。このことは、エネルギー転換に関わるリテラシーの強化と社会のあらゆる層から積極的な参加を得ることが急務であることをはっきりと示しています。
着実で安定した日本の前進
2021年エネルギー転換指数において、日本は115カ国中37位につけています。過去10年間、日本のエネルギー転換指数のスコアは全般的に比較的安定して推移してきました。エネルギー輸入国という元来不利な立場にありながらも、エネルギー源および輸入元を多様化することで、日本はエネルギー安全保障において高いスコアを維持しています。
環境の持続可能性の分野で日本のスコアは上昇しています。さまざまな需要セクターにおいてエネルギー効率と生産性を向上させる取り組みを継続してきた結果、GDP当たりのエネルギー強度が低下したことが、その主な要因です。しかし、福島第一原子力発電所の事故を受けた原子力発電停止の影響で発電に使用する石炭や天然ガスの比率が増え、日本のエネルギー構成における炭素強度はこの10年で上昇する結果となりました。この問題に対処する上で、グリーン水素や二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS)を中心とした新興のエネルギー技術を役立てられる可能性があります。
政治の関与、イノベーションのための投資と協力、ESG投資の増加など、日本ではエネルギー転換を実現するための環境が着実に改善しています。日本がこのほど実質ゼロ目標を表明したことで、エネルギー転換のモメンタムは一段と加速するとみられます。ただし、セクターごとのロードマップを作成し、排出削減が困難なセクターも含め、そのロードマップに中間目標を設け、期限どおりの前進を徹底させることが必須となるでしょう。
このトピックに関する最新情報をお見逃しなく
無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
最新の情報をお届けします:
日本
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。