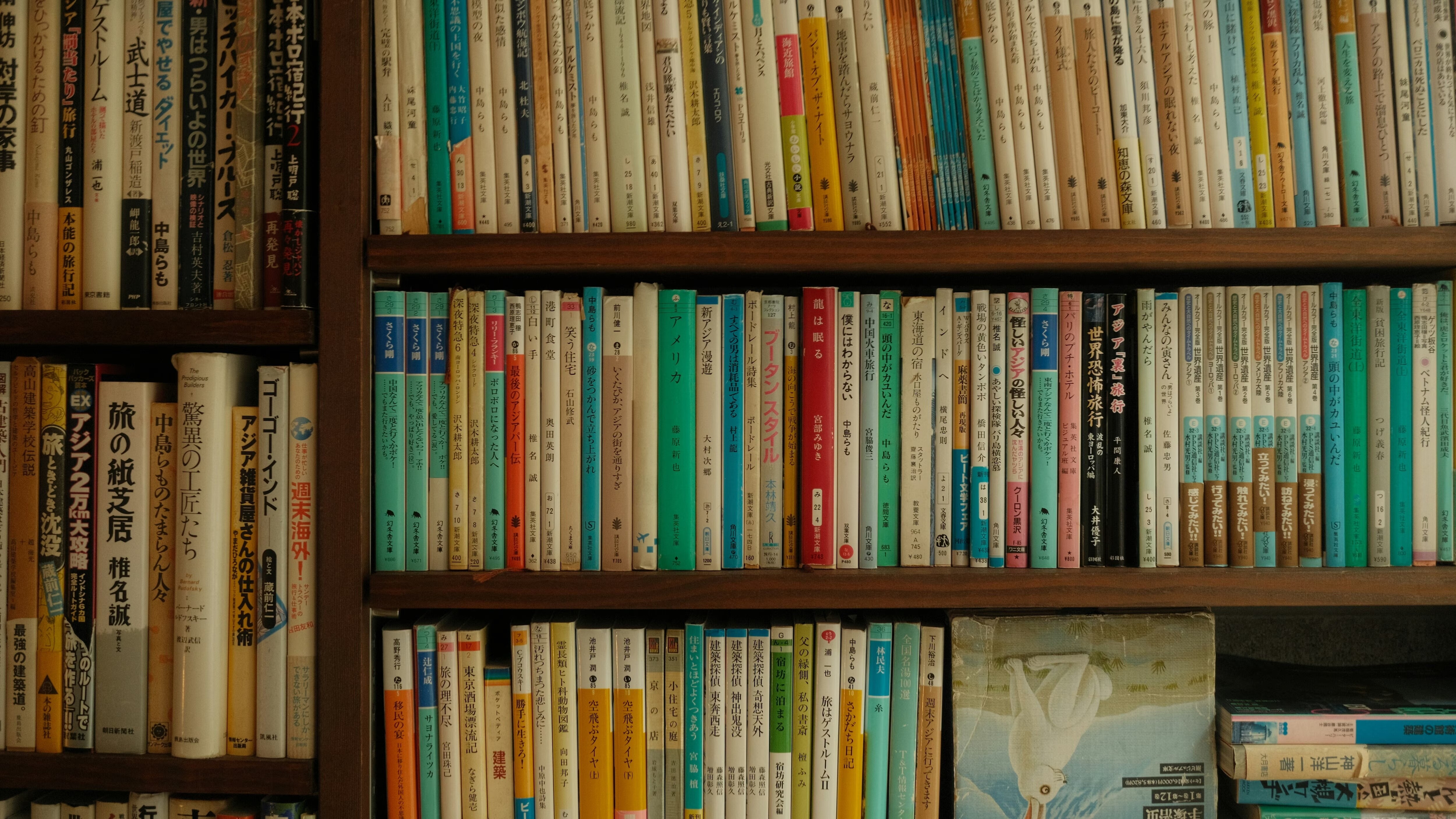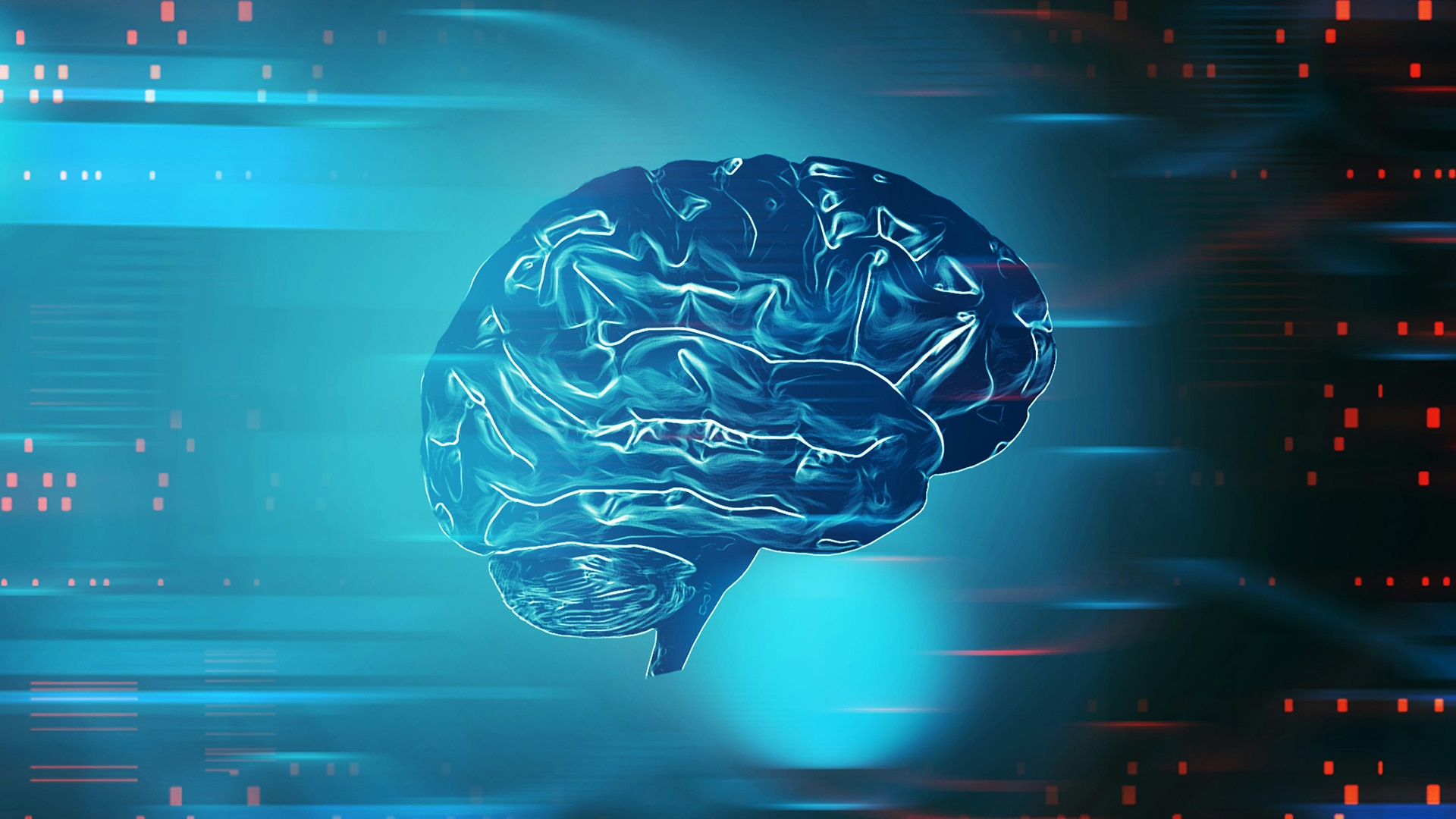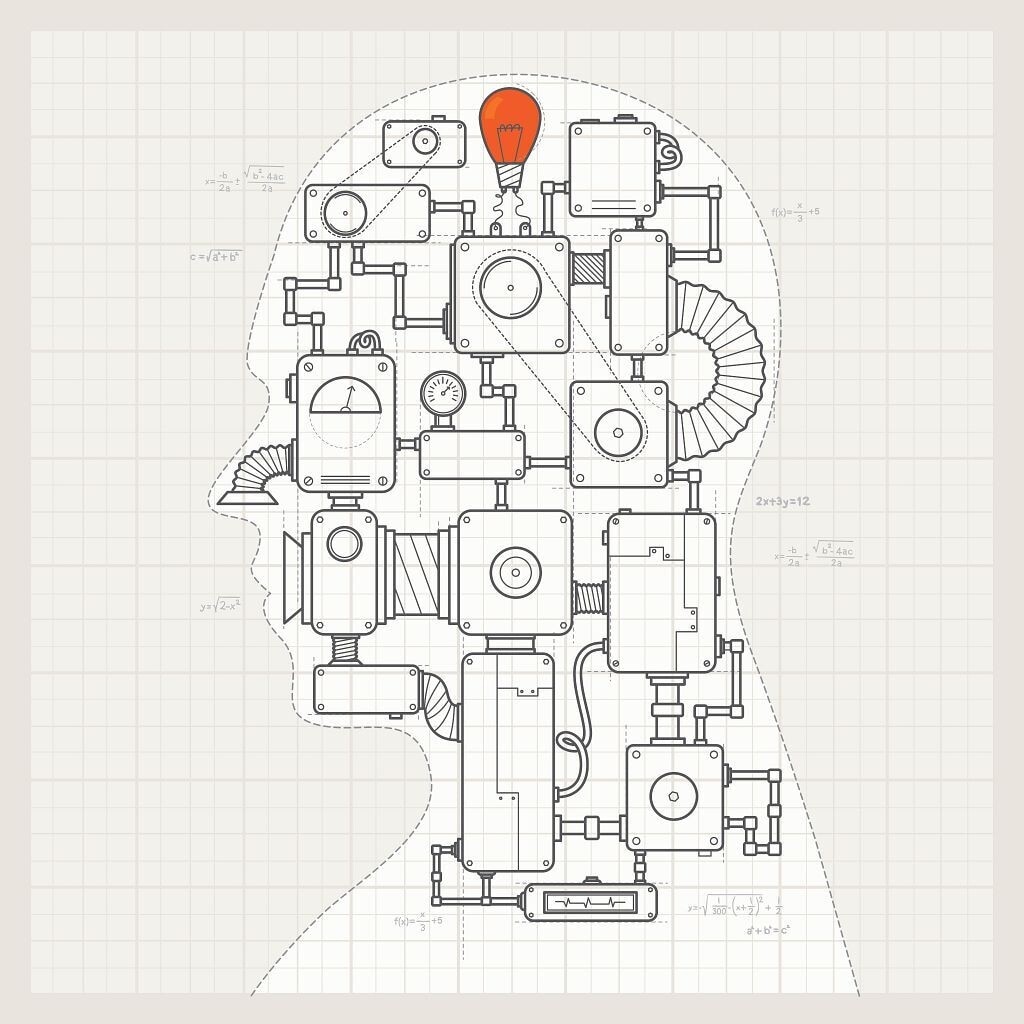職場での「食」が、ビジネスと社会にもたらす恩恵とは

栄養の改善において、職場が重要な役割を果たすようになっています。 Image: Getty Images
- 食料が十分にあるにもかかわらず、日本では現代型栄養失調が増加。その主な要因は、コンビニエンスストアの食品や外食への過度な依存にあります。
- 従業員の栄養改善において、職場が重要な役割を担うようになり、「置き社食」(オフィス内での健康的な食事提供サービス)などの取り組みが進んでいます。
- 政府や自治体の支援もこうした栄養重視の取り組みを後押ししており、企業がより良い食事の選択肢を提供することを促進しています。
日々の食事は、健康や精神状態に影響を与え、生活の質を左右する重要な要素です。深刻な食糧難に陥った第二次世界大戦以降、日本では経済の成長とともに食生活が豊かになり、現在では食べ物を手に入れることが困難な状況はほとんど見られません。一方、摂取カロリーは足りていても、必要な栄養素が不足している「現代型栄養失調」の増加が課題となっています。
自宅で料理せず、飲食店や24時間営業のコンビニエンスストアを頻繁に利用し、すでに調理された商品で食事を済ます人も少なくありません。ある調査では、調査対象者のほぼ半数が2日に1回コンビニエンスストアの惣菜を購入。さらに、一人暮らしの人々の17.7%は「毎日購入する」と回答しています。また、国民健康・栄養調査によると、惣菜や弁当を購入し、持ち帰って食べる「中食」を「週2~3回」以上行っているのは、男女共に20代から50代で2割以上。外食に関しても、特に男性の20代から40代で「週2~3回」以上となっており、中食や外食の利用頻度が働く世代で高い傾向にあることがわかります。
中食や外食は利便性が高い一方、栄養面での課題が指摘されています。コンビニ弁当など70商品を対象に行われた別の調査では、「食塩相当量が過剰の傾向にあった。また,副菜となる惣菜を選択したとしても,1 品のみでは野菜等重量が十分確保できない可能性があると示唆された」と考察。さらに、中食や外食の頻度が高いほど野菜の摂取量が低い傾向を示す調査もあります。
栄養の偏りは、生活習慣病など様々な病気の原因となるだけでなく、生活習慣病は労働生産性の低下と関連していることが指摘されており、労働生産性にも影響を与えます。また、近年では、就職先の選択において食事補助を含む福利厚生を重視する傾向が高まっています。こうしたことから、日本の企業と政府は、働く世代の栄養バランス改善を通じ、生産性や人材確保・定着につなげるための取り組みを進めています。
栄養価の高い「置き社食」
近年、社員の栄養状況が仕事における生産性に影響を与えることを認識し、栄養バランスに配慮した食事や食品を提供する企業が増えています。社員食堂がある企業では、提供する食事をより健康に配慮したメニューに変更し、社員食堂がない中小企業などにおいても、「置き社食」などの活用により、社員の栄養向上を図っています。「置き社食」とは、オフィスに冷蔵庫を設置し、社員に食品を提供するサービス。月に数万円程度で利用可能です。
同サービスを提供する、スタートアップのKOMPEITOでは、2024年までの3年間で「置き社食」用冷蔵庫の導入台数が6.5倍に増加。また、野菜やサラダを提供する同社の「OFFICE DE YASAI」サービスは、2024年8月までの4年間で地方での導入率が19%から52%に拡大しています。
栄養は健康維持の手段のみならず、社会や経済の根幹を支える要素となっています。
”食に関する教育プログラム
栄養バランスの取れた食品を提供するだけでなく、社員に食と健康についての知識を深めてもらう「食育」への取り組みも進んでいます。ハリウコミュニケーションズでは、月に2回、「社食の日」を設け、総務部や役員が中心となり、社内のキッチンで食事を作ります。これを全員で食べることにより、社員が調理の方法を覚え、食材の栄養素など学ぶ機会となっています。さらに、共に食事を取ることにより、会話がはずみ、コミュニケーションも活発化しました。
政府や自治体による支援
政府や自治体も、こうした企業の取り組みを支援しています。政府は、企業が社員に提供する食事支援における非課税額の上限を、現在の一人当たり月3,500円から引き上げる議論を進めています。非課税で食事支援に充てられる額が増えると、企業が食事支援の拡充に取り組みやすくなります。また、東京都では、中小企業向けに、若手の人材確保のサポートとして、「職場で従業員に食事等のサービスを提供することに係る経費」に対し、上限50万円の助成金を提供。さらに、様々な知見を有する専門家を最大3回派遣し、企業の取組計画の作成を支援しています。
栄養バランスの良い食事は、経済の支えとなる
厚生労働省の「国の栄養施策の動向について」に明記されているように、栄養は、「人が生涯を通じてよく生きるための基盤であり、活力ある持続可能な社会を実現する上で必須要素」です。世界経済フォーラムもまた、「過体重に関連する疾患は、今や飢餓よりも多くの人の命を奪って」いると報告し、バランスの取れた栄養が人々の健康やレジリエンス向上において重要であることを強調しています。
このように、栄養は健康維持の手段のみならず、社会や経済の根幹を支える要素となっています。栄養バランスの改善は、生産性向上や医療費の削減といった経済的インパクトにつながります。個人、企業、政府が連携し、より広い視野と長期的なビジョンのもと栄養政策を推進めることは、持続可能な経済成長と社会のレジリエンスを支える基盤となるでしょう。
このトピックに関する最新情報をお見逃しなく
無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
最新の情報をお届けします:
労働力と雇用
関連トピック:
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。
もっと知る ウェルビーイングとメンタルヘルスすべて見る
Naoko Tochibayashi
2026年2月24日