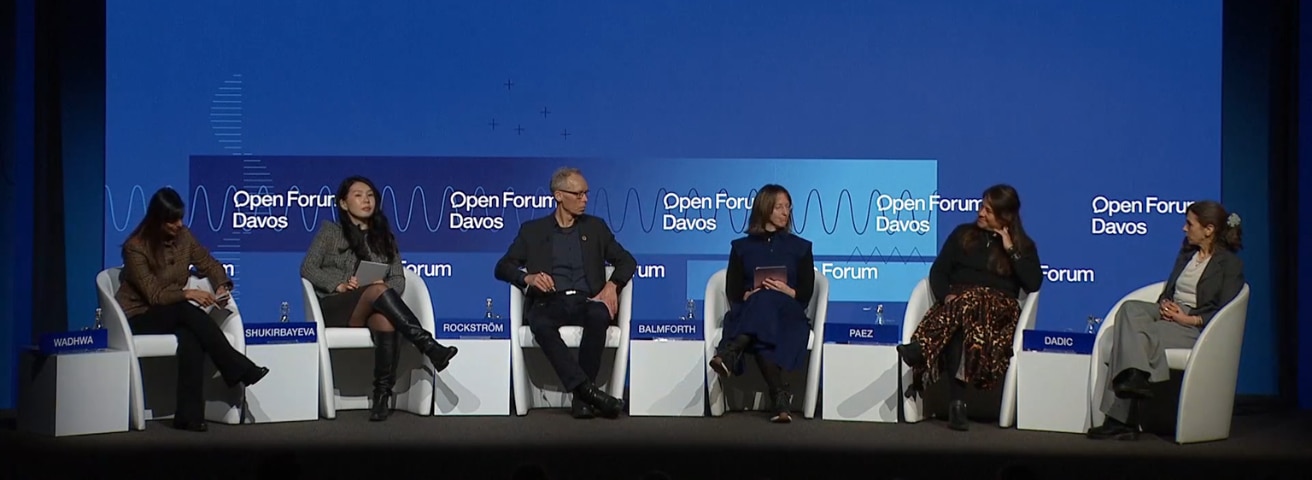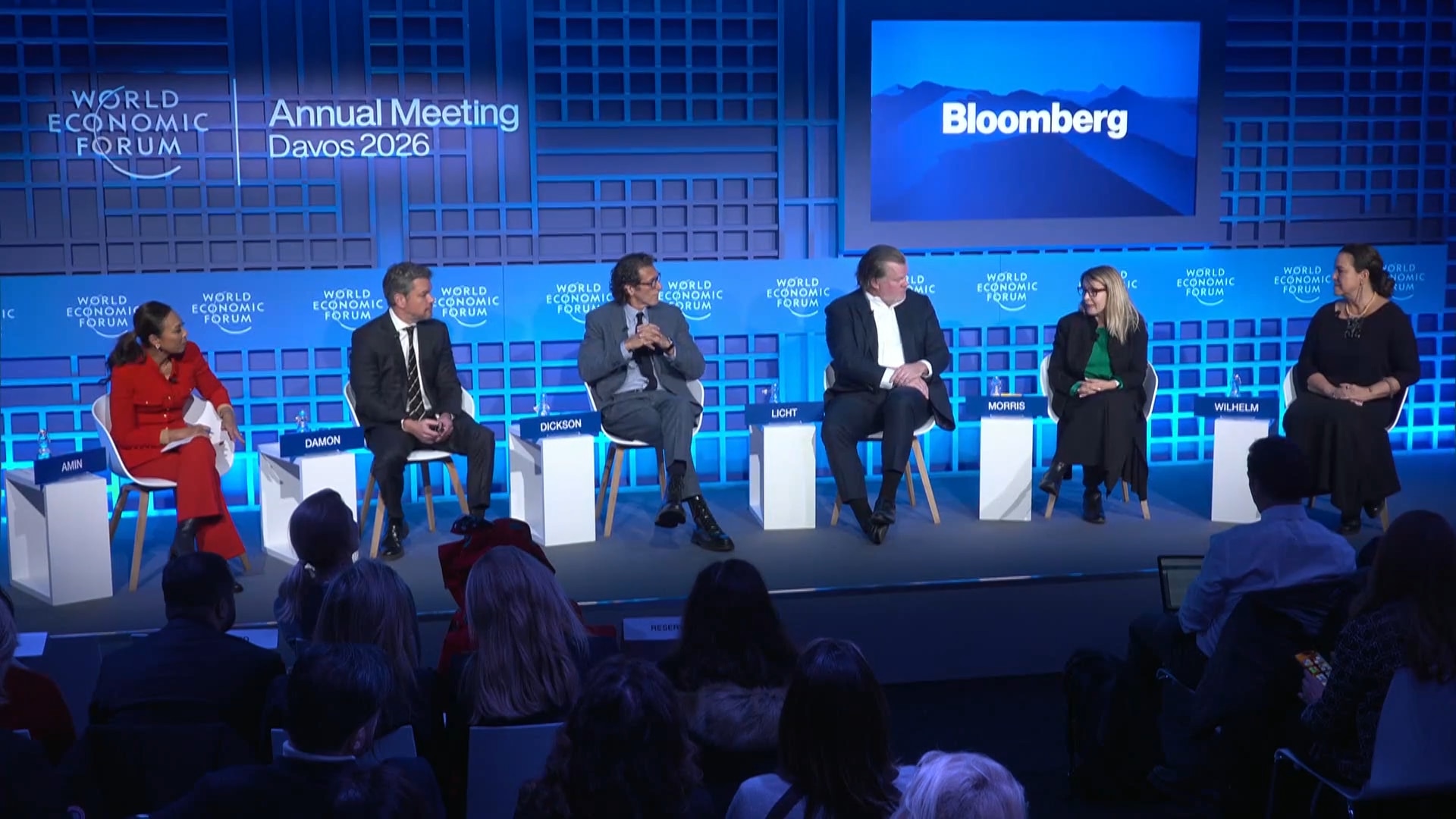家庭の食品ロス対策〜日本における持続可能性の鍵〜

日本の食品ロス削減は、コスト削減と持続可能性の向上の両立を目指す取り組みです。 Image: Getty Images/iStockphoto/simonkr
- 2022年に102の国々で約10億5,000万トンの食品が廃棄されました。
- 食品ロスは、世界の温室効果ガス排出量の8〜10%を占めるとされています。
- 日本では、家庭からの食品ロス削減に向け、官民学の連携による取り組みが進められています。
気候変動や地政学的要因などにより、世界的な食料価格のさらなる上昇が見込まれる中、依然として著しい量の食料が廃棄されています。食品ロスの削減は、家計の節約だけでなく、廃棄物処理に伴う温室効果ガスの排気抑制にもつながるため、官民が連携して様々な対策を講じています。
国連環境計画(UNEP)の「フード・ウェイスト・インデックス報告書2024」によると、2022年に102か国で約10億5,000万トンの食品が廃棄されました。そのうち約60%は家庭から発生したものです。また国連は、食品ロスと廃棄が世界の年間温室効果ガス排出量の8〜10%を占めていると推計しています。
日本では、2020年の閣議決定により、2000年度の食品廃棄量約980万トンを基準とし、2030年度までにこれを半減するという目標が設定されました。2022年度には、推計で472万トンまで減少し、内訳を見ると、「家庭系」の食品廃棄量が約236万トン、事業系(飲食店など)が約236万トンと、同程度の割合を占めています。全体として目標を達成し、事業系は目標を8年前倒しで達成している一方、家庭系は依然として216万トンという目標値に達しておらず、対策の強化が求められています。
消費者庁によると、2022年度の食品ロスによる経済損失は約4兆円、温室効果ガスの排出量は1,046万トンCO2にのぼります。そのため、食品ロスの半分を占め、削減目標に達していない家庭での食品ロスの削減が急務です。
政府および自治体による、意識向上への取り組み
官民での取り組みが進む中、2024年に発表された世代別の食品ロスに関する研究が、今後の取り組みを、より実効的なものにするための一助となることが期待されます。
2025年3月、日本政府は「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」を閣議決定し、2030年までの新たな削減目標を示しました。家庭系ではこれまでと同じ、2000年比で半減、すでに当初目標を達成した事業系では60%減を掲げています。
同方針では、農林漁業者から小売業者まで、食品サプライチェーン全体の関係者に対し、食品廃棄を減らすための行動と意識改革を求めています。また、学校や地域、店舗を拠点に、消費者向けの情報発信や意識啓発キャンペーンも推奨されています。
自治体においても、各地で積極的な動きが出ています。富山県では、ウェブサイト「とやま食ロスゼロ作戦」を展開し、家庭での食品廃棄を減らすためのアイディアやレシピ、イベントをまとめています。さらに、キャラクターを用いた啓発動画を配信し、子供たちにもわかりやすく食材を無駄にしない方法を発信しています。
スマート冷蔵庫で食材管理を効率化
2024年11月には、ネットスーパー企業のイオンネクストとパナソニック傘下の暮らしアプライアンスが連携し、スマート冷蔵庫を用いた実証実験を開始しました。冷蔵庫に入れたまま忘れられる食材や消費期限切れを防ぐことを目指し、その利便性や食品ロス削減への効果を検証しています。
AI搭載カメラや専用アプリを備えたこの冷蔵庫では、食材の鮮度をAIが把握し、食べ頃や消費を推奨する食材を表示。さらに、その食材を活用したレシピの提案に加え、イオンネクストが運営するネットスーパー「Green Beans(グリーンビーンズ)」と連動し、必要な食材をリスト化してインターネットから注文することも可能です。
世代別分析により、ターゲットを絞った対策が可能に
政府、企業、研究機関が、より効果的かつターゲットを絞った食品ロス削減策を展開するには、他にどのような対策が考えられるのでしょうか。世代別に家庭から出る食品ロスを分析し、2024年11月に発表された研究報告が、その手がかりとなるかもしれません。
立命館大学の研究チームによると、家庭における食品ロスには世代別の傾向が見られます。もっとも廃棄量が多い70代以上(46.0kg/人)と最も少ない29歳以下(16.6kg/人)では、3倍弱の差がありました。
若い世代は外食機会が多いこと、高齢層は廃棄リスクの高い食材を多く購入する傾向にあることが背景にあります。さらに、廃棄の原因は、高齢世代では、調理時に可食部も含めて捨ててしまう「過剰除去」、若い世代では「食べ残し」が多いことが明らかになっています。
こうした調査結果をもとに、今後はより的確な世代別対策を策定することが可能となり、家庭系食品ロスのさらなる削減につながることが期待されています。
持続可能な社会の実現に向けて
まだ食べることができる食品を無駄にすることは、食費の増加や二酸化炭素排出の増大につながり、深刻なグローバル課題となっています。世界経済フォーラムは、バーレーンにおける食品ロス削減プロジェクトを推進。同国では、年間216,161トンの食品が廃棄され、ラマダンの期間中は廃棄量が増えることが課題となっています。また、2025年のヤング・グローバルリーダーに、「ゼロ・ウェイスト・ジャパン」代表の坂野晶氏を選出するなど、食品ロスがグローバルな議論の中でも注目されていることが反映されています。
日本では、革新的なテクノロジーの活用に加え、公共の啓発活動を通じて食品ロス削減に取り組んでいます。さらに今後は、世代ごとの意識や行動傾向による調査を基にした戦略的なアプローチが期待されており、より詳細な行動傾向などの分析の重要性が高まるでしょう。
官民および学術機関の連携による日本の取り組みは、家庭での食品ロス削減において参考となるモデルとなり得るでしょう。食品ロスを減らすことは、経済的、環境的な課題の解決に寄与すると同時に、よりレジリエンスのある社会の実現に向けた重要な一歩でもあります。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。