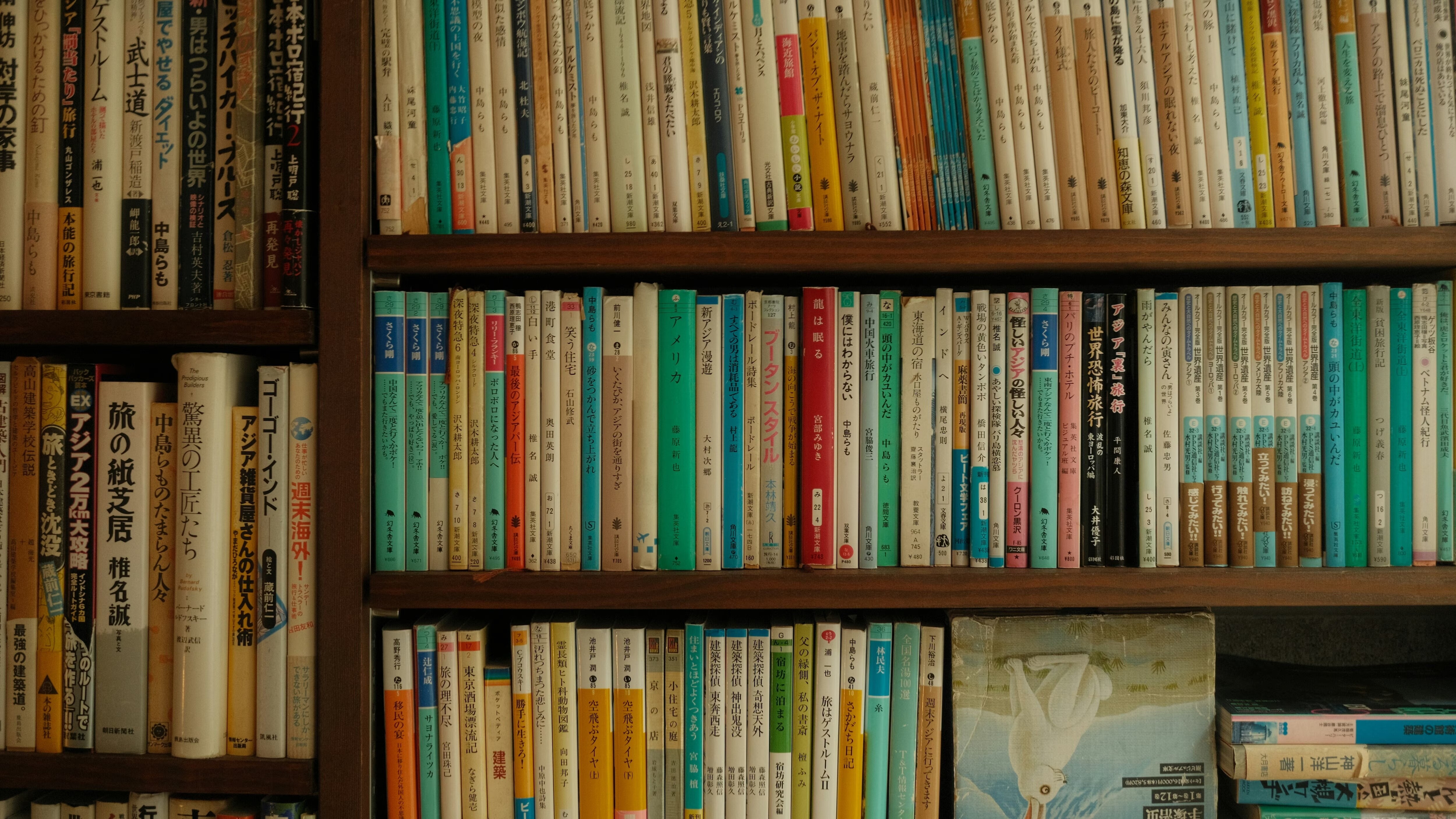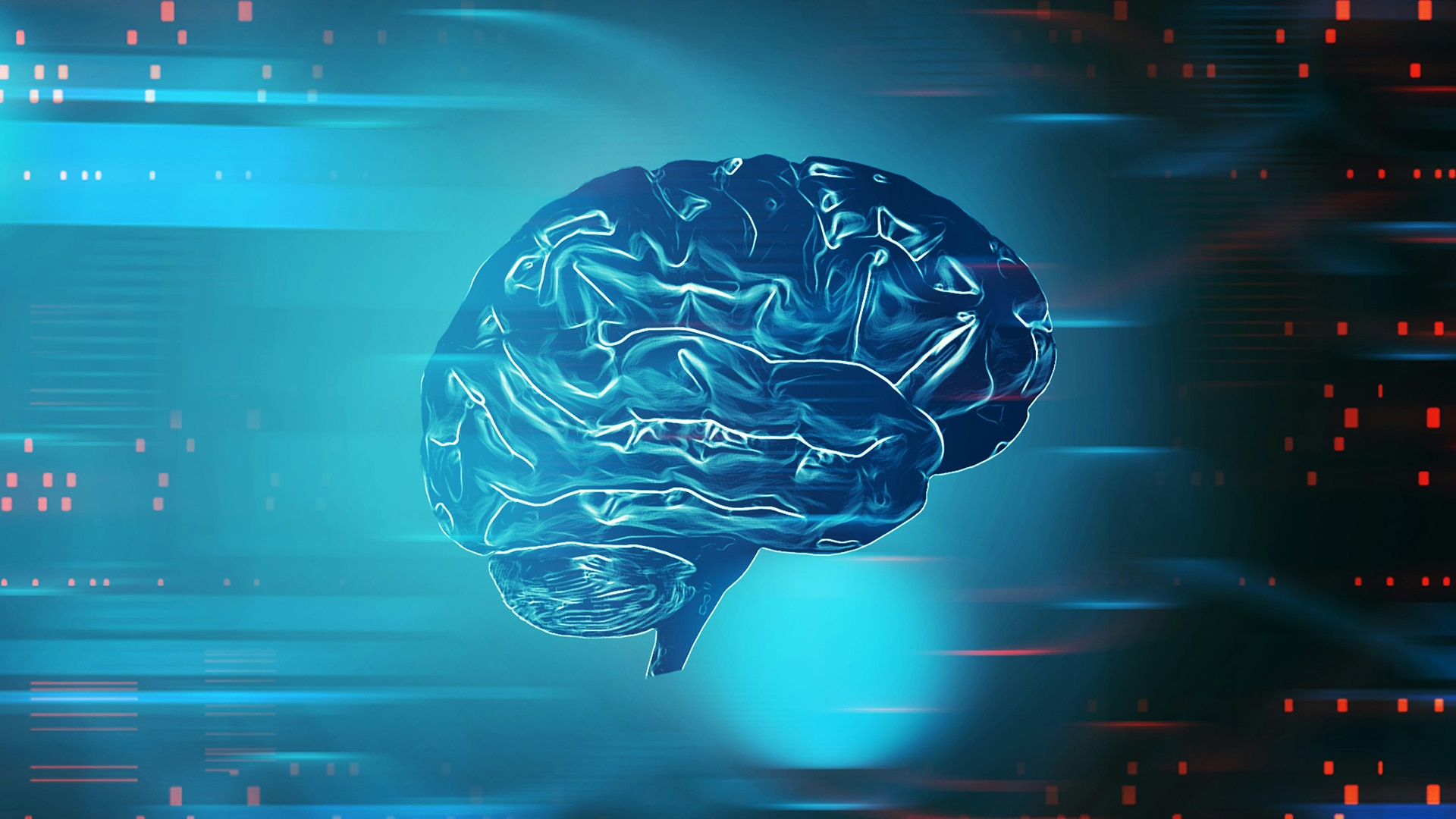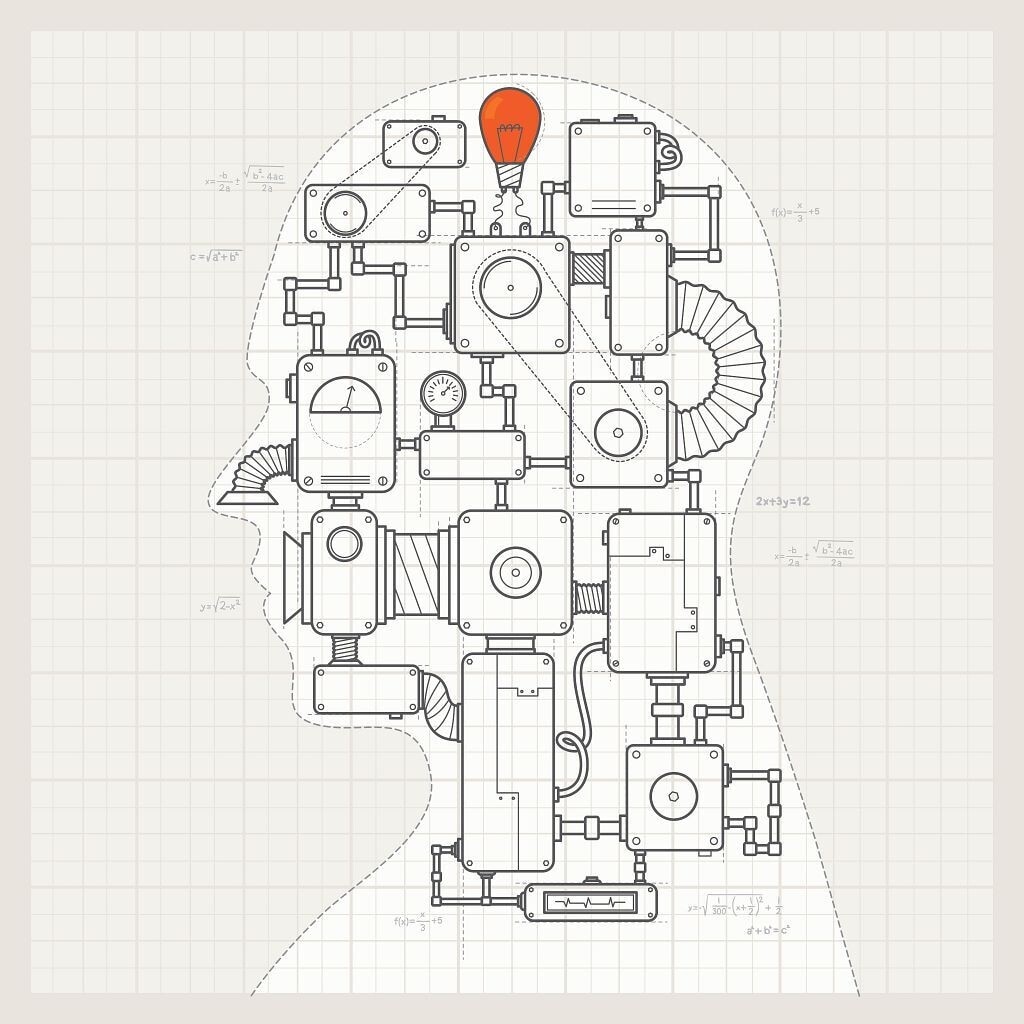インテリジェント時代における、職場のウェルビーイングとその重要性

米国、英国、カナダを含む多くの国で、実際に職場で幸せだと感じる従業員は25%に過ぎません。 Image: Unsplash/Duc Dao
- 研究によると、職場で幸せだと感じる従業員は25%に過ぎません。
- 世界経済フォーラムの報告書によると、職場のウェルビーイング向上により、グローバル経済は11.7兆ドル成長する可能性があります。
- 世界安全衛生デーにちなみ、経済学と行動科学の教授であるヤン・エマニュエル・デ・ネーブ氏が、職場のウェルビーイングが重要である理由を説明します。
2025年に生きる多くの人々にとって、仕事の世界は「必ずしもポジティブな場所ではない」とオックスフォード大学経済学・行動科学教授のヤン・エマニュエル・デ・ネーブ教授は述べています。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより職場でのメンタルヘルスとウェルビーイングへの注目が高まった5年後、「振り子は以前の時代に戻りつつある」と同氏。また、職場のウェルビーイングへの投資の必要性に関する議論が、人間中心の視点から離れつつあるとも指摘しています。
世界経済フォーラムの報告書『活気ある職場(Thriving Workplaces)』によると、従業員のウェルビーイング(幸福)への投資は世界経済を11.7兆ドル増加させる可能性があることが、マッキンゼー・ヘルス・インスティテュートの調査で明らかになりました。同報告書には、同教授の研究も引用されています。
世界経済フォーラムのヘルスとヘルスケア部門は、パートナーと協力してホリスティック(全体論的)な職場健康対策の優先順位付けを行っています。これは、生産性向上とグローバルな労働力の健康のレジリエンス強化を目的としており、投資根拠と証拠基盤の両方を強化する取り組みです。また、「健康な労働力」と「チーフ・ヘルス・オフィサー」コミュニティを通じて、同氏および他の研究者と協力し、最も重要な職場の測定指標とメトリクスを明確化し、これらを調和させる取り組みを進めています。
こうした取り組みは喫緊に必要とされています。同氏がインディードと共同で実施した調査によると、米国、英国、カナダを含む多くの国で、職場で実際に幸せを感じる従業員は25%に過ぎません。この調査結果は、同僚のジョージ・ワード氏と共著の同氏の新刊、『Why Workplace Wellbeing Matters: The Science Behind Employee Happiness and Organizational Performance(職場のウェルビーイングが重要である理由:従業員の幸福と組織のパフォーマンスの科学)』で詳細に説明されています。
「多くの改善の余地があります。また、経営層の言動と実際の行動の間には大きなギャップが存在します」。
同氏とそのチームが調査したマネージャーの80%以上が、人材への投資がビジネスに良い影響を与えることに同意しています。「しかし、人材への投資を戦略的優先事項として位置付け、それをビジネスの核心に据えるための具体的な行動を取っているマネージャーはわずか19%です」。
本書では、職場のウェルビーイングが企業パフォーマンス、生産性、人材定着、採用に重要な理由をビジネスケースとして説明しています。
世界経済フォーラムのヘルスとヘルスケア部門長、シャム・ビシェンは「これは、従業員が最大の資産であるという事実を認識し、従業員を大切にすれば、従業員がビジネスを大切にするというメッセージです。
私たちは、職場での成功の定義を再考する必要があります」と述べています。
「長らく、ウェルビーイングはオプションとして扱われてきました。しかし、エビデンスは明白です。組織が人々の健康とウェルビーイングを戦略の中心に据えると、イノベーションからレジリエンス、ビジネスパフォーマンスまで、すべてが改善されるのです。これは、リーダーシップチーム全体で職場の健康を共有の優先事項にする転換点となるでしょう。従業員のため、そして組織の将来の強さと持続可能性のために、優れたリーダーはウェルビーイングの環境を創造します」。
4月28日の「世界安全衛生デー」で、AIとデジタル化の役割に焦点が当てられました。新型コロナウイルス感染症のパンデミックから5年間で、生成AIが導入され、ChatGPTのようなプラットフォームが職場でますます採用されるようになっています。しかし、これらは職場のウェルビーイングにどのような影響を与えるのでしょうか。
職場のウェルビーイングを推進する要因とその利点、そしてテクノロジーが働き方の未来をどう変えていくのか、デ・ネーブ教授へのインタビューを以下にまとめています。
職場のウェルビーイングとは何か、なぜ測定が重要か
「職場のウェルビーイングとは、最終的に私たちが職場でどのように感じるかであり、それが職場への定着、エンゲージメント、生産性、他者への推奨といった行動を決定します。
職場での感情は、ポジティブな感情の体験を通じて捉えられます。職場で幸せでしょうか。過剰なストレスを感じていないでしょうか。仕事に満足し、目的や意味を見出しているでしょうか。幸福感、ストレス、仕事への満足度、目的や意味の感覚が、アウトカムとしての指標になります。なぜそう感じるのかという説明にはなりませんが、職場にいる時や仕事について考える時の人の感情を捉えるものが指標です」。
「人事部門の幹部やCFO、CEOと話をすると、彼らは一般に職場のウェルビーイングを、公正な報酬から所属感、信頼、仕事への満足度、エンゲージメントまで、良いことの羅列として捉えています。しかし、人々の感情に影響を与える要因(インプット)と、職場で人々がどのように感じているかを把握するための包括的な指標(アウトカム)を概念的に分けて考えられてはいません。これは重要なことです。このように整理することで、職場のウェルビーイング向上に限られたリソースをどこに優先的に投資すべきかを判断しやすくなり、同時に従業員の実際の状態を示すKPI(重要業績評価指標)を得ることができるからです。
職場での感情が変われば、従業員の行動が変わります。人々の感情は、彼らがエンゲージメントを示すか、生産的か、会社を推薦するか、または会社に残るかどうかに影響するのです。結果として、指標を適切に測定、捕捉することによって、離職率、従業員推奨度スコア、顧客満足度、そしてその先の生産性とエンゲージメントといった、客観的な結果指標を予測できるでしょう」。
「ウェルビーイング100」で測定する、ウェルビーイングとパフォーマンスの関連性
同氏とワード氏は英国の通信会社、BTのコールセンター従業員を調査し、ウェルビーイングと生産性との因果関係を見出しています。
天気データを分析に組み込むことで、従業員は晴れた日に幸せを感じ、そのために生産性が向上し、売上増加につながることが分かりました。
その後、インディードのサイト、Indeed.comで職場におけるウェルビーイング調査に回答した2,000万人以上の回答者から収集したクラウドソーシングデータを使用し、「ワーク・ウェルビーイング100」指数を作成。これは、幸福感、仕事満足度、目的意識、ストレスの少なさという主要指標において従業員から最も高い評価を得た100社を認定するものです。
過去5年間、および2024年(下図参照)を通じて、この指数は他の株式市場指数を常に上回っています。
「私たちが発見したことは、職場のウェルビーイング向上に取り組む企業は、その内容や投資額にかかわらず、数十億ドルの粗利益と利益率の向上という形で報われるということです」と同氏は述べています。
「職場のウェルビーイングの高さは、将来の株式市場パフォーマンスの先行指標となります。ウェルビーイングの高い企業に投資すればよいのです。これは本当に心躍る発見でした。
職場で人々がどう感じているかは、将来的なビジネス成果を予測する先行指標です。というのも、職場での気分が良くなれば、生産性の向上、離職率の改善、人材採用の強化など、パフォーマンスにつながる効果が短期・中期・長期の各段階で最終的には業績に反映されていきます。その結果、市場ではこうした企業の業績が予想を上回る『サプライズ』として現れ、それに反応して投資家が価値を再評価し、株式価値が上がるのです」。
職場のウェルビーイングの主な要因とは
「管理職と従業員の両方が報酬や柔軟性を最優先に挙げます」と同氏。
「しかし、実際に分析を行い、人や組織間の違いを最も大きく説明する要因を探ると、社会的要素、特に組織への帰属意識が最も重要な要素であることが分かります。
つまり、従業員は組織が自分を一個人として尊重し、配慮してくれていると感じたいのです。フォーカスグループの中では、そのような言葉が実際に頻繁に用いられており、職場での友人関係や社会的なつながりの重要性と並んで、帰属意識への欲求が顕在化しています」。
朝起きて会社に行き、組織にとどまり、そこで幸せを感じる理由は、ポジティブな社会的つながりです。
”「従業員がどのように感じるか、組織が自分を大切にしていると実感できるかどうかは、主に上司をはじめ、組織全体や同僚との関係性を通じて明確になり、伝わるものです。
また、職場に尊敬できる人、憧れる人、共に働きたいと思える人がいる場合、そうした人間関係は職場におけるウェルビーイングにおいて、人々が想像する以上に大きな影響を与えます。それが、業務内容自体や報酬以上に、人々がその組織にとどまる理由となるのです」。
在宅勤務が人々に与える影響
「在宅勤務がもたらす柔軟性を高く評価する従業員は多いですが、在宅勤務、特に完全リモートワークは、社会的つながりや所属感など、他の多くの要因に負の影響を及ぼします。
新型コロナウイルス感染拡大の初期段階、企業がオフィスの終焉を予測していた頃、私は『注意が必要だ』と指摘していました。短期的に見れば、柔軟な勤務形態にもメリットはあり、生産性レベルも同様を維持できるかもしれません。しかし、中長期的に見れば、私たちの社会的、知的資本は時間経過と共に侵食される資本ストックです。
通勤がなく、通勤コストもかからず、1日のスケジュールに多少の柔軟性があったものの、人々は社会的、知的資本の面で限界に近づき始めていました。給湯室での雑談がなくなり、部門を越えた影響力が思考を刺激する機会も減りました。
週3日のハイブリッド勤務が最適ですが、全員がオフィスに出勤し、社会的資本を回復するメリットを享受できるように、協調したアプローチが必要です。
オフィスに戻った際のタスクの種類についても調整が必要です。ブレインストーミング、クライアントとのミーティング、インスピレーションを得ることのできる同期型タスクは、一緒に取り組む方が効果的で、ウェルビーイングと生産性を向上させます」。
AIが職場のウェルビーイングに与える影響
「自動化とAIが、仕事の未来、あるいは正直に言えば現在の職場に与える影響は、明らかに巨大です。しかし、それが良いことか悪いことかは、予測が困難です」と同氏は語っています。
「本書では、一歩引いて、AIと自動化が職場のウェルビーイングの要因にどのように影響を与えているかを分析しています。
私たちの発見は、AIが柔軟性といった要素にポジティブな影響を与え、興味の薄いタスクを排除する点でした。しかし、人々が懸念し、私たちも懸念している点は、AIが、場合によってはすでに実現している可能性を含め、私たちの帰属意識、ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)、そして職場におけるポジティブな人間関係を損なう潜在的なリスクがあることです」。
もしあなたの上司がアルゴリズムによるプラットフォームになってしまったとしたら、それは人間の立場からするとやや不安を感じる状況です。
”「人とのやりとりの一部が失われてしまうかもしれない、そうしたデジタルツールや大規模言語モデルの導入は非常に懸念されます」。
働き方の未来とウェルビーイングに関する議論は、定量的な側面だけでなく、定性的な側面にもより焦点を当てるべきでしょう。こうしたツールは主に生産性と効率性に焦点を当てていますが、仕事の質を損なう可能性はあるのでしょうか。
「1週間ごとの気分の変化が、その週の生産性に大きく影響することが分かっています。そのため、人間的な要素を排除するような生産性向上ツールは、一見効率的に見えても、その週全体では従業員のウェルビーイングを損ない、結果としてエンゲージメントや生産性の低下を招く可能性があります。
こうした大規模言語モデルの設計においては、人事部門や現場のマネジメント層を巻き込み、従業員自身も導入プロセスに参加させる必要があります。テクノロジー部門だけでツールを設計し、経営陣が承認してトップダウンで一方的に展開するようなやり方では、リスクが高すぎます。このような手法は、業務の質的側面を損なう恐れがあり、期待された生産性向上の効果を帳消しにしてしまう可能性すらあるのです」。
職場のウェルビーイング向上に向けて企業ができること
「まず注意すべき点は、個人に過度に焦点を当てないことです。個人のスキルセットやレジリエンスを強化し、職場のウェルビーイングを改善しようとする取り組みは重要です。しかし、実際に職場のウェルビーイングを生み出す主な要素は、構造的、環境的、組織的なものです。
マインドフルネスのアプリを導入したり、ヨガクラスを企画したりすることは良いことで重要です。しかし、働き方そのものに深刻な問題がある、職場でハラスメントが横行している、あるいは業務過多によるストレスや燃え尽き症候群が蔓延しているような状況では、実際の業務負荷の軽減が必要です。根本的な対策をとることなく、ヨガクラスなどのウェルビーイングに向けた取り組みを導入するだけでは、むしろストレスを増幅させて逆効果になりかねません」。
組織における構造的な課題を、ヨガで解決することはできません。
”オックスフォード大学のウェルビーイング・リサーチ・センターでは、この点について非常に明確な立場を取っています。個人と向き合うことは重要ですが、組織として責任を負い、適切な報酬を支払い、自律性と発言権を提供することもまた必要です。企業への帰属意識は個人から生まれるものではなく、上司、同僚、そして組織のトップから浸透する『人間として人々を大切にする』文化から生まれるからです。
「ポジティブな企業文化、心理的安全性、メンタルヘルスに関して自由に発言できる風土は、必ずしも莫大なコストを要するものではありません。こうした環境を構築するには、前向きな姿勢やマネジメントの意識改革を通じて、心理的に安全な空間を組織内に広げていくことが鍵となります。
この責任は、決して最高人事責任者(CHRO)だけが担うものではありません。企業文化を形成するのはCEOであり、多くの場合トップダウンで決まる部分も大きいのです。これからのCHROや最高人員責任者(CPO)には、組織全体の各部門をつなぐ『橋渡し役』としての役割が求められるようになるでしょう。例えば、CFOと連携して報酬設計を行い、CEOと共に組織文化を築き、現場のマネージャーと協働して、彼らが優れたミドルマネジメントになれるよう育成していくことが必要になります。
CHROの役割は今後大きく変化していくと考えられます。それに伴い、人事部門リーダーにとっての業務は一層複雑になり、他の経営幹部と連携しながら、職場で働く人のためにより良い環境を築いていくための影響力が、これまで以上に重要になるでしょう」。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。
もっと知る ウェルビーイングとメンタルヘルスすべて見る
Naoko Tochibayashi
2026年2月24日