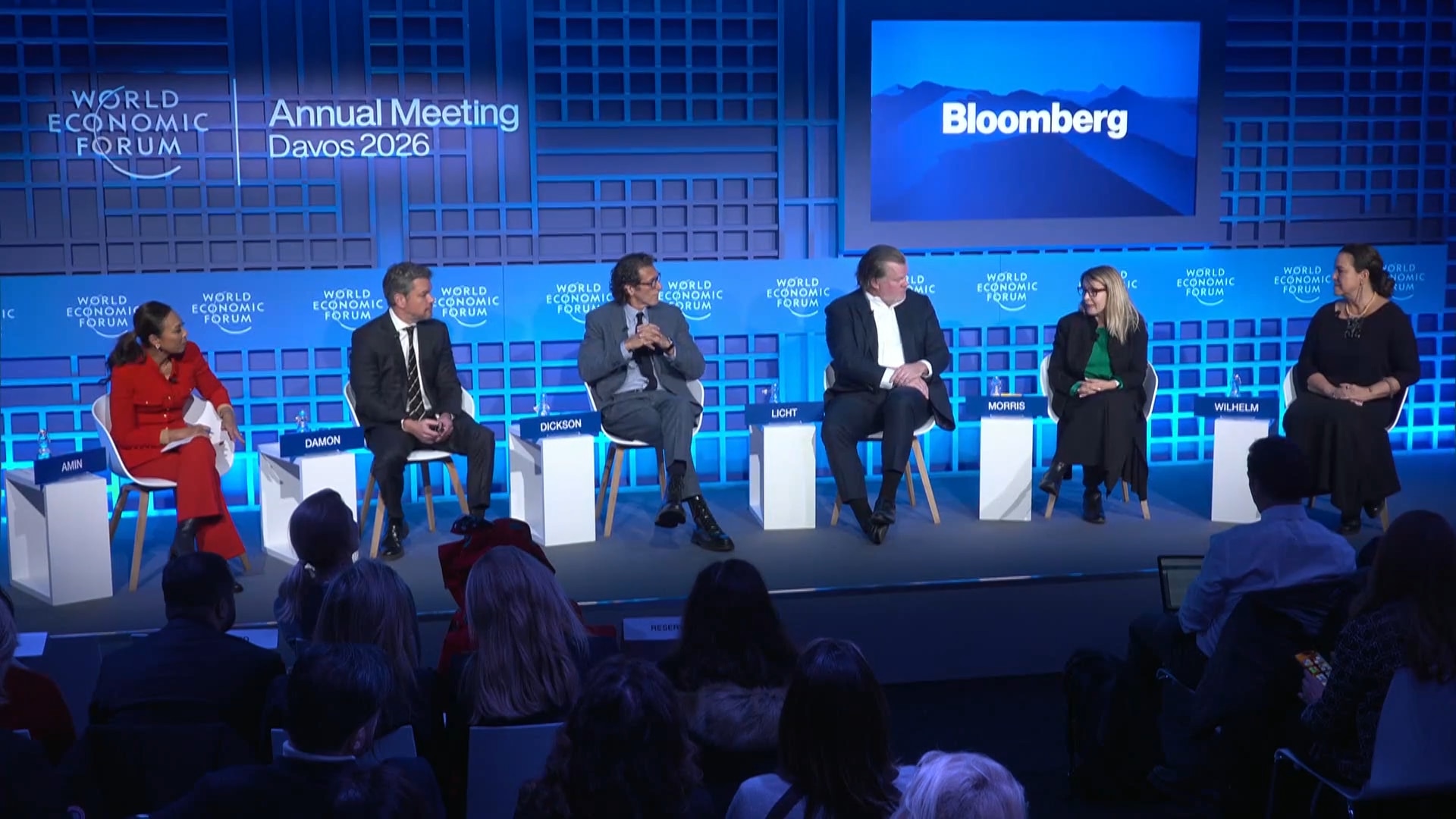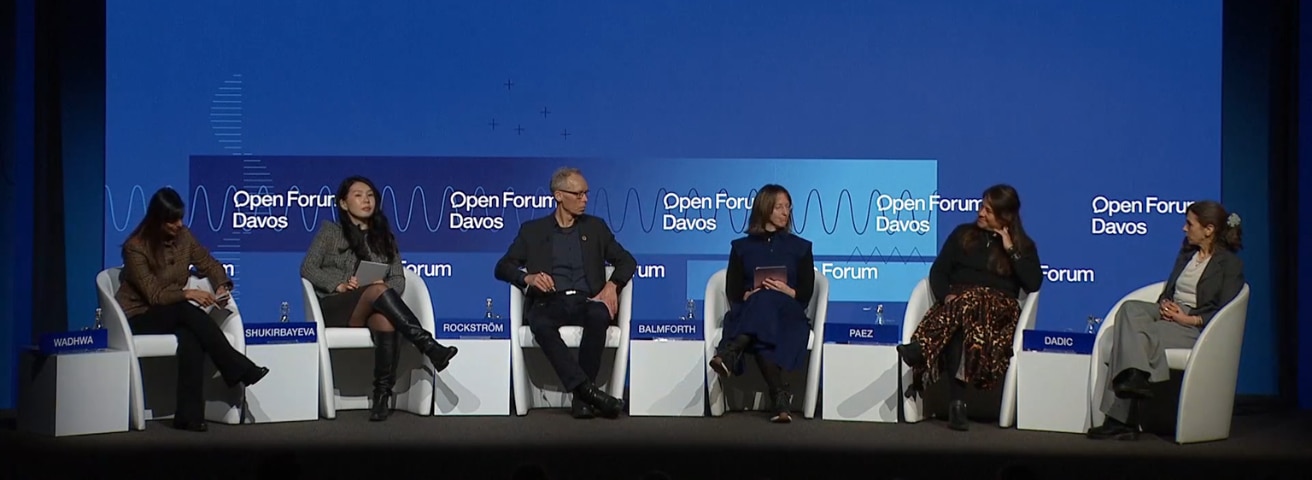過去に習う持続可能な食の未来、インド流「ゼロ・ウェイスト」

今日、食品ロスは単なる豊かさの副産物ではなく、私たちが食とのつながりを失っていることの表れでもあります。 Image: The Kindness Meal
- 世界では、生産される食品の3分の1が廃棄されており、その原因は先進国における過剰消費と、発展途上国における保存・流通の不備にあります。
- 伝統的なインド料理の調理法は、無駄を出さない工夫を凝らす必要があったため、食品ロス削減の一つの手本となります。
- 昔ながらの知恵を活かしながら、テクノロジーによる革新を組み合わせることで、持続可能かつ廃棄物を出さない食料システムの構築が可能です。
インドの野生のスイカ「マティラ」は、私の祖母にとって夏の相棒でした。淡い緑色の皮に軽々と包丁を入れ、砂漠の暑さにも関わらず、最初の一切れは冷たく、甘いものでした。また、祖母やその世代にとってこのスイカは、単に涼を取るための食べ物ではなく、「無駄を出さない工夫」を教えてくれる存在でもありました。皮をすぐに食べない場合は、カレーにし、また、食料の少ない季節に備えて天日干しにしました。種は炒ってシャツのポケットに忍ばせ、手軽なおやつとして持ち歩きました。
こうした創意工夫は、かつてインド亜大陸の多くの家庭では当たり前のことでした。すべての食材は最大限に活用され、必要性から生まれた習慣でありながら、そこには深い知恵が根付いていました。しかし、現代的な利便性が台頭するにつれ、このような意識的な消費は徐々に姿を消し、深刻な食品ロスが常態化するようになったのです。
この危機は世界的なものである一方、その原因は地域によって異なります。先進国では、過剰生産、見た目による選別、消費者の習慣など、豊かさゆえの問題が食品廃棄につながっています。一方、開発途上国では、保存設備の不足、不安定な輸送、非効率な流通が原因で食品が失われています。
その結果、今日の食に関する数値は驚くべきものとなっています。国連食糧農業機関(FAO)によると、毎年、人間の消費を目的として生産された食品の約3分の1が損失もしくは廃棄されています。また、2024年に発表された国連の食料安全保障に関する報告書によると、2023年に約23億3,000万人が中程度から深刻なレベルの食料不安に直面。そのうち8億6,400万人以上は、1日以上食事を取れないなどの極度の食料不足を経験しています。これらの統計を総合的に見ると、問題は「不足」ではなく、「分配」「消費習慣」、そして「伝統的な食の知恵との断絶」にあることが明らかです。
豊かさの代償
今日の食品廃棄は、単なる豊かさの副産物ではなく、「食との断絶」の表れです。サプライチェーンのあらゆる段階において、まだ食べられる食品が大量に廃棄されています。スーパーマーケットでは、形が悪い、サイズが不揃い、少し傷があるといった理由で果物や野菜を拒否。レストランでは余った料理が捨てられ、まとめ買いした食材は使用前に賞味期限を迎えることも珍しくありません。
こうした広範な食品廃棄は、現代の食文化が、食材を育て、収穫し、調理するまでの労力に対する意識を遠ざけてしまった結果でもあります。豊かであることの利便性が、食品を「使い捨て可能なもの」に変えてしまったのです。
食品の廃棄がもたらす環境的負担も非常に深刻です。食品ロスは、世界全体の温室効果ガス排出量のほぼ10%を占めており、気候変動の主な要因の一つとなっています。食品を廃棄することで、食品の生産に使われるエネルギー、水、労働力もすべて無駄になります。研究によると、食品ロスの80%以上は、生産、加工、消費の各段階で発生し、その多くは埋め立てられる、もしくは焼却処分され、いずれも環境に悪影響をもたらしています。
食は神聖なもの
食料の分配には、より大きな地政学的・経済的政策が関与していますが、歴史的な視点から現状を見直すことにも価値があります。1947年にインドがイギリスから独立した前後に起こった飢饉、干ばつ、深刻な食料不足、経済的困難、大規模な移住といった出来事は、あらゆる食材の可食部分を保存し、再利用し、再活用するという文化を形づくりました。インド哲学における「Annam Brahmam(アナム・ブラフマン)」は「食は神聖なものである」を意味し、食品を無駄にすることは、神や自然に対する不敬に等しいと考えられています。
インドの各地域では、果物や野菜のすべての部分を異なる調理用途に活用してきました。バナナは、花、茎、葉、皮まですべてが料理に使われます。ヘチマなどの野菜の皮はチャツネになり、ジャックフルーツの種は炒っておやつに、ザクロの皮さえも天日干しして薬用のお茶として飲まれました。前日に作られたチャパティ(小麦の平パン)は、スパイスと一緒に調理し、おやつとして食べられました。
インド南部や東部では、残ったご飯が無駄にされることは決してありませんでした。南インドのタミル・ナードゥ州やカルナータカ州では、残りご飯を一晩水に浸して軽く発酵させ、暑さに耐えるためのプロバイオティクスが豊富に含まれる「パザヤ・サーダム(発酵粥)」として食べられます。オリッサ州、ベンガル州、アッサム州では、発酵させた残りご飯をマスタードオイル、青唐辛子、漬物などと一緒に食べるのが、朝食の定番となっています。
意図的な食習慣を育む
今日のスピード重視の社会では、利便性が持続可能性よりも優先されることが多く、食品ロスの削減は難しい課題に思えるかもしれません。忙しいスケジュール、誤解を招く消費期限表示、完璧な見た目の野菜や果物に対する要求などが、この課題に拍車をかけています。一方、食品ロスへの取り組みに、大きなライフスタイルの変化は必要ありません。視点を少し変えるだけで良いのです。
最もシンプルな解決策の一つは、かつて実践されていた伝統的な調理法に宿る工夫の精神を再発見することです。根から葉まで食材を余すことなく使い、すでにあるもので献立を立て、残り物を別の料理に活用することで、家庭における食品ロスを大幅に減らすことができます。こうした小さな行動も、大勢で取り組めば大きな変化につながります。
個人の努力に加え、システム全体の変革も重要です。大量包装されたスーパーマーケットの商品ではなく、地元産かつ旬の食材を選ぶことで、出荷段階から食品ロスを減らすことができます。余剰食品を再活用する企業を支援し、レストランに余った料理の寄付を促し、避けられない食品くずを堆肥化することも、より持続可能な食文化に貢献します。
興味深いことに、かつてインド、アフリカ、ラテンアメリカの台所で当たり前だったゼロ・ウェイストのアプローチが、今、西洋で再発見されつつあります。「ノーズ・トゥ・テイル(鼻から尾まで)」や「ファーム・トゥ・テーブル(農場から食卓へ)」のような動きが勢いを増しており、これらは何世代にもわたって多くの開発途上国で日常的に行われてきた実践と重なります。
先進国がフードロス削減アプリや「アグリープロデュース(見た目の悪い農産物)」の市場などのテクノロジーを活用する一方、多くの開発途上地域では、伝統的な枠組みの中で革新が進められています。インドの農村部では、古くからの天日干し技術を現代化し、太陽光乾燥技術を用いた余剰作物の保存が行われています。こうした技術革新は、伝統の知恵と現代の解決策をつなぐチャンスをもたらしています。
最終的な目標は、完璧を目指すことではなく、「意識的に食べる」という姿勢に戻ることです。食材や、その背景にある労力に敬意を払うことこそが大切なのです。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。