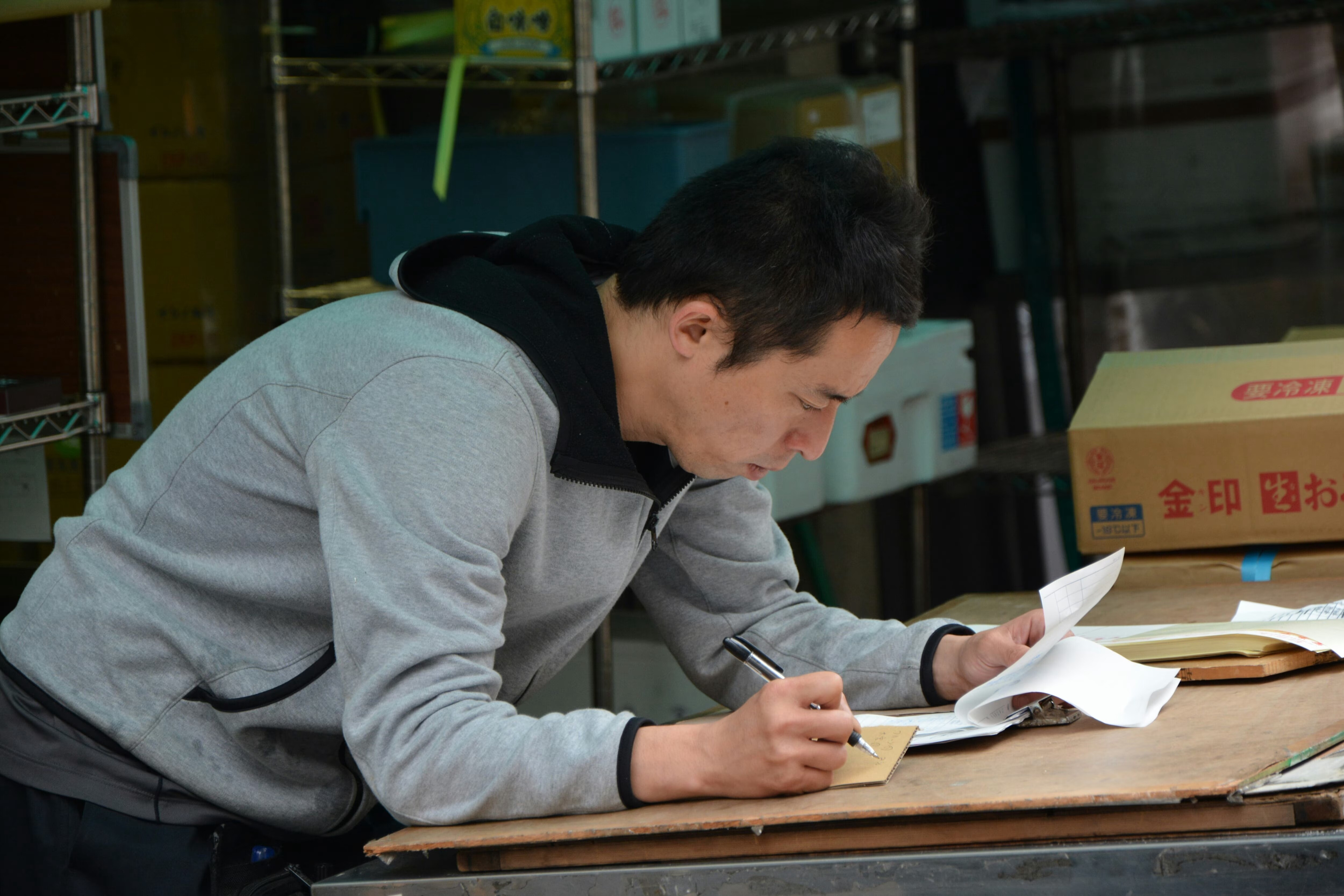持続可能な社会の構築に向けた、教育格差解消の取り組み

パンデミックは日本の教育制度における格差を浮き彫りにしました。 Image: Reuters/Issei Kato
- 新型コロナウイルスのパンデミックにより教育における格差が露呈する中、日本では官民の連携により、格差解消の取り組みが進められています。
- 高等学校等就学支援金制度が更新され、公立・私立高校の授業料が今後実質無料になる予定です。
- オンラインの教育ツールは、地域の教育格差を解消する上で大きな可能性を秘めています。
4月から新学期が始まった日本。世界的に基礎学力の水準が高い国である一方、新型コロナウイルスによるパンデミックにより、教育格差が顕在化し、その解消に向けた取り組みが進められています。
教育基本法では、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられ」、「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と定められています。また、同法に基づき、9年間の義務教育が定められており、この期間中は国立および公立の小中学校において授業料は発生しません。
さらに、日本の義務教育における学力は世界的に見ても高い評価を受けています。2023年のIEA国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)では、算数・数学と理科において、小学校・中学校ともにほぼ全てでトップ5(小学4年生の理科は6位) に入っています。OECDが実施する学力調査「PISA」の最新調査(2022年)においても、日本の15歳の生徒は数学および科学リテラシー、読解力すべての分野でトップ5入りを果たしています。このような実績もあり、これまで日本では教育格差が大きく取り上げられる機会は限られてきました。
しかし、新型コロナウイルスによるパンデミックを経て、子どもたちが受ける教育における格差の存在が浮き彫りになってきました。政府の調査によると、家計所得が高いほど大学への進学率が高く、大学・大学院への進学率が東京や大阪などの大都市圏で特に高い傾向が見られます。こうした家庭の経済状況や居住地域による教育格差を解消するため、政府や企業による支援策が進められています。
教育支援の拡充
日本政府は、より公平な教育機会を提供することを目的に、2025年の4月から、高等学校に通う生徒への支援金である「高等学校等就学支援金制度」を拡充。従来は、親の所得が一定額を超えると、支援金が支給されませんでした。また、国とは別に都道府県が支給する就学支援金の額にはばらつきがあり、同じ高校に通っていても居住する都道府県により学費の負担額が異なるという不公平がありました。
これに対し、2025年4月からは親の所得に関係なく、全国一律で年間11万8800円の支援金が支給されます。これは、公立高校の授業料と同額であり、実質的に公立高校の授業料が無償化されることになります。さらに、2026年4月からは、私立高校の生徒を対象とした支援金(上限45万7000円)についても所得制限が撤廃され、私立高校も実質無償化される予定です。
また、鎌倉市では、経済的に困窮な家庭の子供に対して、公益団体や企業と連携して多様な学びの場で使うことのできるクーポンを支給するなど、自治体による支援も進められています。日本では、子どもの相対的貧困率が11.5%に上ると報告されており、こうした取り組みにより、経済的理由から高校への進学を諦める状況の防止が期待されています。
オンラインツールで地域格差を埋める
都市圏と地方では、学校の数や選択肢、学習塾・予備校などの教育支援施設に差があり、学習環境にも格差が生じていることが指摘されています。このような地域による格差を埋めるための手段一つのが、オンライン学習の活用です。
株式会社すららネットやベネッセなどの企業は、ゲームやアニメーションのキャラクターを活用したオンラインの学習ツールを提供しています。こうしたツールは、個人の理解度に応じて繰り返し学ぶことができる設計となっており、学習、練習、テストを繰り返すことにより、理解を促進し、知識を定着させることができます。リクルートもまた、低価格の定額制で大学受験に向けたオンラインの授業などを繰り返し受けられるサービスを提供しています。すららネットのオンライン学習ツールは、特に不登校の子どもの自宅学習支援として自治体による導入が進んでおり、ベネッセのツールも多くの高校で採用されるなど、学校内外での活用が広がっています。
さらに、高等学校レベルでは、住む場所に縛られずに幅広い学習や生徒同士の交流、課外活動が可能な環境を提供し、地域による教育格差の解消に貢献する、N高等学校などのオンラインスクールの存在も高まっています。
公平な教育機会の提供が、レジリエンスの高い社会をつくる
公平な教育へのアクセスは、すべて子どもたちに保証されるべき権利であり、国連の持続可能な開発目標(SDGs)にも掲げられています。こうした目標に向けた官民の取り組みは、イノベーションを促進し、レジリエンスを高め、長期的な経済の持続可能性にもつながる重要な要素です。今後も、政府、企業、地域社会が継続的に連携し、公平な教育の機会を提供することが、教育の可能性を最大限に引き出し、誰一人取り残されない、包摂的かつ未来志向の社会の実現の鍵となるでしょう。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。