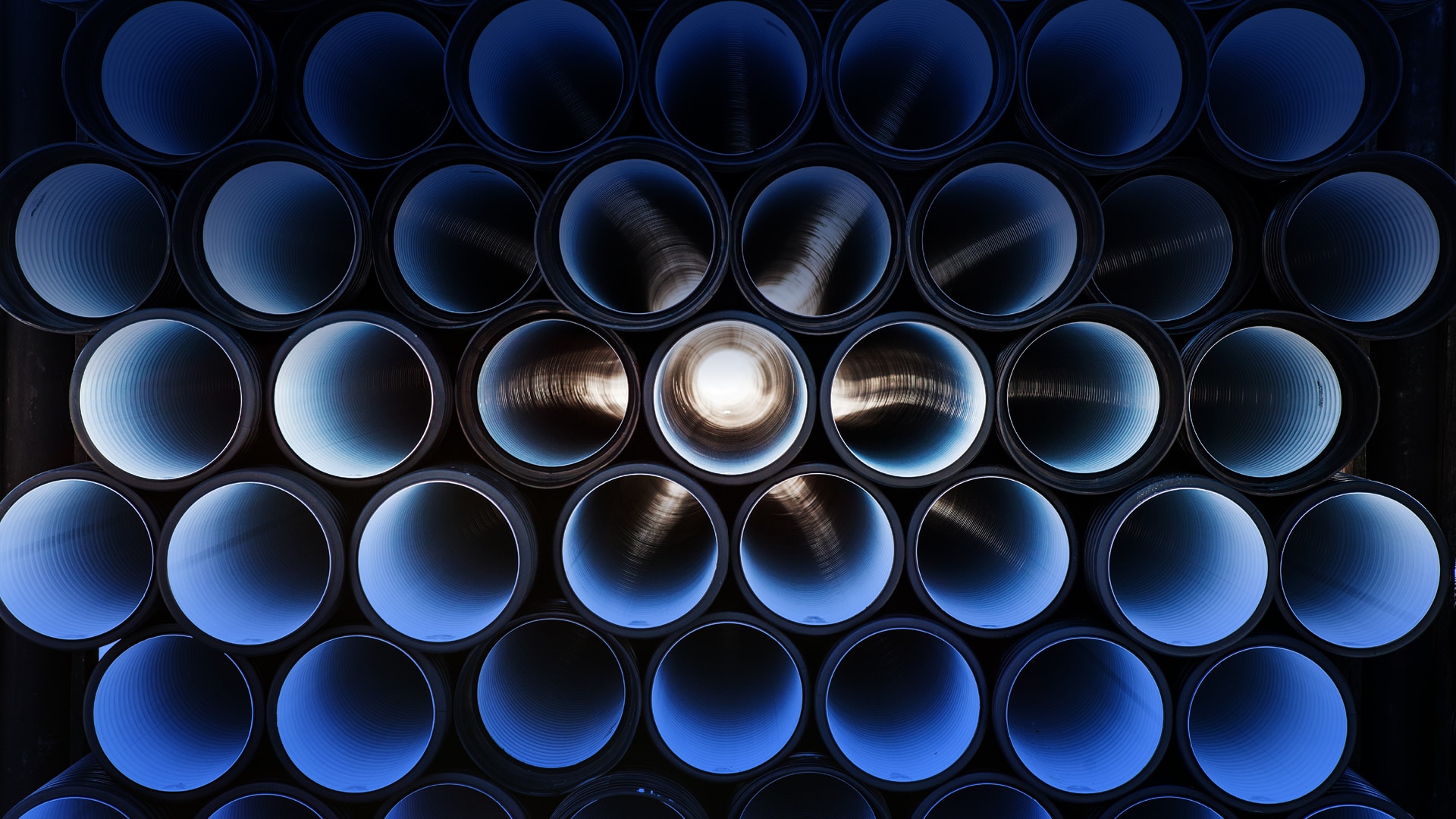「バウクルトゥール」が、人間中心の住環境に導く理由とは

「sθәqәlxenәm ts’exwts’áxwi7」はカナダ・バンクーバーにある公園です。公園の名前は、ブリティッシュコロンビア州の原住民の言語であるハルコメレム語 およびスクォミッシ語で「虹」を意味します。 Image: Brett Hitchens, courtesy of DIALOG
- 人類の歴史を通じ、人々は地域の気候や素材に基づいた居住環境を作り上げ、それが文化を反映し、形成してきました。
- 産業革命とグローバル化がこの地域密着型のアプローチに取って代わり、建造環境の製造が大きく変化しました。
- 世界の都市化が急速に進む中、都市づくりの理論と実践のバランスを取るには、地域社会づくりの中心に再び文化を据えた包括的なアプローチが求められます。
築家や環境デザイナーは長い間、理論と実践と科学、美と実用性、主観性と客観性の間にある緊張関係と闘ってきました。緊張関係というより、矛盾する概念が一致する「リミナルスペース(狭間の空間)」という方が正確かもしれません。これこそが、人類が最も豊かに生きる場所なのです。
近年の認知神経科学や環境心理学の研究により、私たちが建物やコミュニティ、道路や景観などの生活環境をどのように創り、維持するかが、思考や感情、行動、社会的交流、さらには身体的な健康に大きな影響を与えることが明らかになっています。
建築評論家であり、ハーバード大学デザイン大学院の元講師であるサラ・ウィリアムズ・ゴールドゴールドハーゲン氏は、こうした科学的研究の成果を取り入れ、「我々は建物を形作り、その後、建物が我々を形作る」というウィンストン・チャーチル氏の直感的な洞察を発展させています。
ゴールドゴールドハーゲン氏や他の実証的研究者は、建築家、都市計画家、政策立案者、開発業者が理論と実践のどちらか一方にとどまるのではなく、その「リミナルスペース」において設計・建築を進めるべきだ、と説得力のある主張をしています。特に、世界の都市化が進む現代において、その重要性は高まっています。
私たちの建築が私たちを形作るための方法
サステナビリティのチェックリスト、ゾーニング法、デザインのガイドラインはそれぞれ重要な役割を果たしますが、それだけでは本質を捉え損ね、時には大きく的外れになることもあります。ゴールドハーゲン氏の著書『Welcome to Your World(ウェルカム・トゥ・ユア・ワールド)』が2017年に出版された後も、同氏は2021年のインタビューでこうコメントしています。「私は、建築家たちが依然として建造環境における人間の知覚や認知を十分に理解していないことに気づきました。直感的にある程度は分かっているかもしれませんが、この分野で必要とされる変革の大きさ、そして改善の余地の広さを理解している人はごくわずかです」。
私たちが作り出す人間の居住環境と、認知神経科学や環境心理学が密接に結びついているという考え方、つまり、それが愛されるか嫌われるか、手入れされて長く残るか放置されて崩れ去るかは、新たな国際的な取り組みであるDavos Baukultur Alliance(ダボス・バウクルトゥール・アライアンス)にとって極めて重要なテーマです。
この多分野・多業種にわたる会員制組織は、「Baukultur(バウクルトゥール)」 という概念に基づき、スイス政府が世界経済フォーラムの協力を得て立ち上げました。バウクルトゥールとは、ドイツ語で「建築文化」を意味する複合語であり、人間の居住空間を設計・建設・維持する際に、地域に根ざした建築手法と、それを生み出す文化を重視する、包括的なアプローチを指します。
Davos Baukultur Quality System (ダボス・バウクルトゥール・クオリティ・システム)では、単なる機能性や経済性、スタイルの追求を超えた視点が求められます。2018年に発表されたDavos Declaration(ダボス宣言)には、質の高い空間を創出するための8つの基準(ガバナンス、機能性、環境、経済、多様性、コンテクスト(文脈)、場所のアイデンティティ、美しさ)が示されています。これらは、何百万年にもわたり、自然の生態系とともに進化してきた私たちの認知的、感情的、美的ニーズや欲求に深く共鳴し、大切にされてきた基準であり、永続する場所を創造するために不可欠な要素です。
価値を築く
何千年もの間、人々は地域で調達した材料を用い、長年の経験と文化に根ざした知識をもとに「ヴァナキュラー(地域特有の)」な建築やコミュニティを築いてきました。しかし、産業革命とグローバル化により急速な都市化が進み、人間の建築と生活のあり方は大きく変化しました。
1928年、アメリカのアーバニスト(都市論者)であり建築評論家のルイス・マンフォード氏は次のように記しています。「言うまでもなく、私たちは依然としてコミュニティデザインの科学と技術において大幅な改良を加える必要があります。さもなければ、すべての人々が機械的な進歩を遂げ、人間らしい生活の他の本質的な側面を犠牲にすることになってしまうでしょう」。
その後、ジェイン・ジェイコブズ氏やウィリアム・H・ホワイト氏といった批評家たちは、都市環境における人々の行動を丹念に観察し、地域計画における「人間中心のデザイン」の必要性を訴えました。しかし、これらは、過去に逆戻りせずに未来へと進むために必要な、科学的な研究には乏しい批判でした。
必然的に、ガラスと鋼鉄の高層ビル、八車線の高速道路、郊外のスプロール現象(無秩序な都市拡大)が、進歩と富の象徴となり、最も雄弁な批評家でさえもその流れを押しとどめることはできませんでした。つまり、建築のあり方を変えるためには、まず建築文化を変える必要があるのです。この考え方は、ダボス・バウクルトゥール・アライアンスの中心にあります。
この理念を実践した一例として、インドネシア・バンドン市の若者たちによるプレイスメイキング(場所づくり)の取り組みがあります。Safe and Sound Cities programme(安全な都市プログラム)の一環として、彼らは自分たちの地域を再構築する機会を得ました。彼らが選んだのは、同市のランドマークであるパソパティ橋の下にある空間を活用し、映画パーク、サッカー場、イベントスペースへと生まれ変わらせること。冷たく無機質で人を寄せ付けない1900年代半ばのインフラを、多機能かつ包摂的な公共空間へと再生させたことで、若者たちは力を得、地域社会により深く関わることができたのです。

建築文化を変える
イギリスの建築家で数学者のクリストファー・アレグザンダー氏は、異なる視点から同様の結論に達しました。同氏による三部作の書籍、特に『パタン・ランゲージ』は、建築や公共空間における美しさは、表面的な問題ではなく、機能的で美的に優れ、人々の周囲の環境に対する感じ方と深く結びついた進化的パターンの産物である、と論じています。
この考え方は、アレグザンダー氏の多くの協力者の一人であり、ギリシャ系アメリカ人のテキサス大学サンアントニオ校の建築学と数学の教授であるニコス・サリンガロス氏により、さらに進化しました。サリンガロス氏は、ネットワーク理論とフラクタル幾何学のアイデアを都市デザインや建築に応用しています。環境は、人間の脳が空間を処理する方法と一致する、自然の形や構造に基づくべきだと、同氏は主張しています。
これを実践するため、ダボス・バウクルトゥール・クオリティ・システムは、人間中心のデザインという基盤構造と、地理的、社会的、経済的な文脈の間にある緊張関係をバランスよく調整します。この点において、バウクルトゥール・システムの「ガバナンス」という基準が重要な役割を果たします。
規制は一般的に柔軟性がなく、変わりにくいものです。しかし、必ずしもそうである必要はありません。動的な規制システムは、生物学において長い間存在しており、この概念は今、ガバナンス構造に影響を与え始めています。人間中心のデザインの原則を動的な規制フレームワークに組み込むことで、人々が建築環境をデザインし、それがどのように進化し、私たちに適応するかを変えることができるかもしれません。これは、適応型建築として知られる新たな研究分野です。
ほぼすべての人が直感的に、建築環境が個人および集団の福祉を促進もしくは妨げることを理解している一方、直感的に知っていることが必ずしも最善の実践に結びつくわけではありません。これが、ゴールドハーゲン氏が「無意識」と「非意識」の認知を決定的に区別する理由です。
無意識的認知は知覚することもアクセスすることもできませんが、非意識的認知は知覚可能である一方、通常はアクセスできません。「私たちの認知の多くは意識的認知が検知できるラインの下にある」と彼女はインタビューで述べています。「認知の大部分は非意識的であり、専門家の中にはこれが90%に達すると考える人もいます」。
ダボス・バウクルトゥール・アライアンスは、その核心において、高品質な生活環境を実現するための8つの基準を通じ、「非意識的なものを意識的にする」ことを目的としています。これらの基準は選択肢のリストではなく、住みやすい場所に対する人間のニーズを、非意識的なものから意図的なものへと高める包括的なアプローチなのです。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。