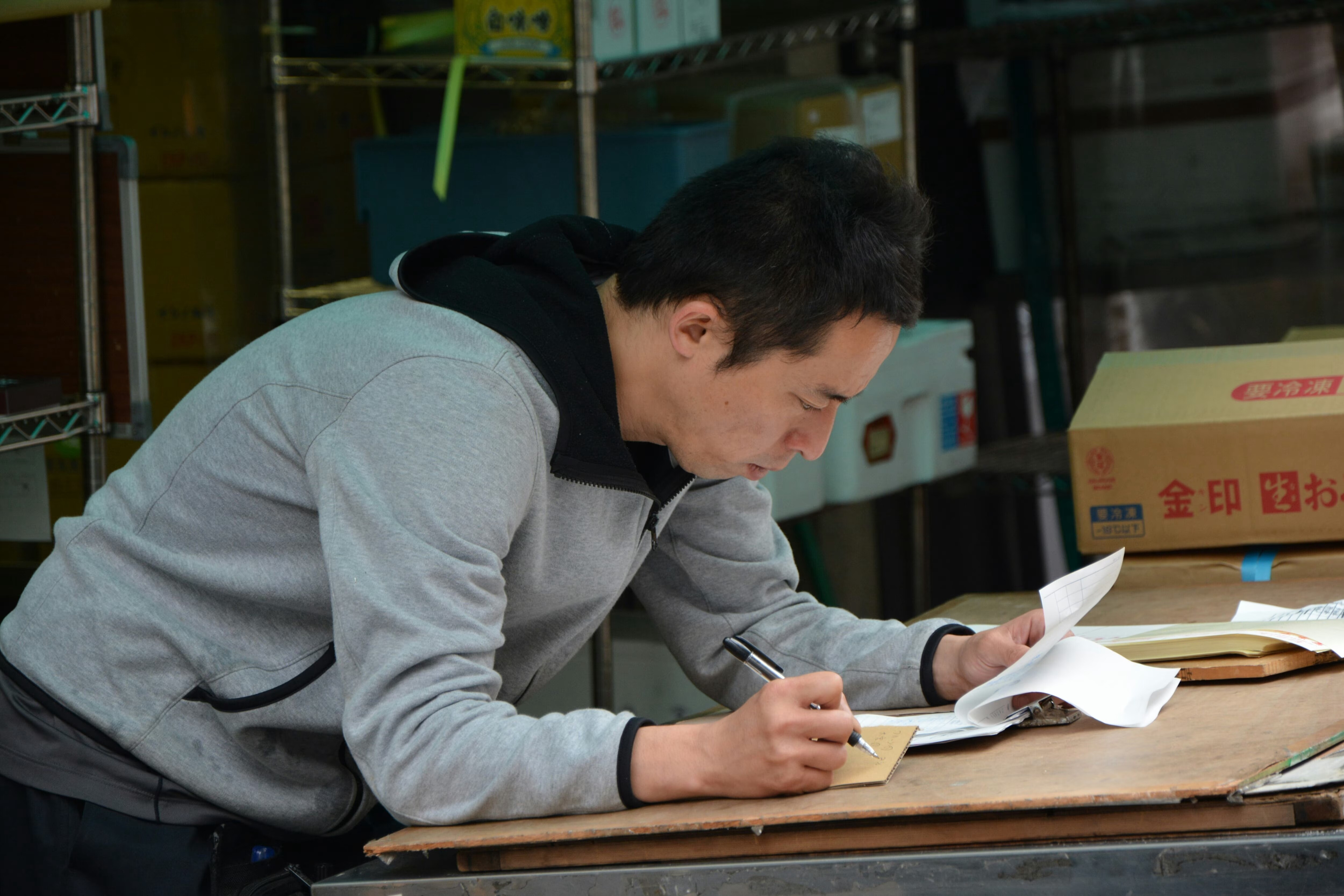多様性を育む学校制度で、レジリエンスある社会へ

不登校は、必要な学力や社会性を身につける機会を失うことに繋がります。日本では、不登校を最小限に抑えるためのシステム作りに取り組んでいます。 Image: Unsplash/Element5 Digital
- 日本の小中学校に在籍する全児童の3.7%が、1年間に30日以上学校を休んでいます。
- 日本では、学校に通うことが困難な子どもたちが通いやすいよう、多様な制度を取り入れた学校を設置する取り組みを行っています。
- 教育における包摂性を育むことにより、生徒たちだけでなく、社会のレジリエンスにもつながります。
レジリエンスのある社会を築くためには、すべての子どもが平等に質の高い教育を受けることのできる環境を整えることが極めて重要です。日本では、不登校の子どもたちの増加という大きな社会的課題に対し、さまざまな取り組みが行われています。
文部科学省は、不登校の子どもたちを、「不登校児童生徒」とし、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因などにより登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために、年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。同省の資料によると、2023年度には、義務教育の範囲内である小学校と中学校における不登校児童生徒は、在籍生徒数の3.7%に当たる346,482人に上り、11年連続で過去最多となりました。さらに、不登校児童生徒の半数以上は年間90日以上欠席し、3.1%は出席日数が0日となっています。
不登校になる背景にあるのは、いじめなどの他に、「やる気が出ない」、「不安・抑うつ」、「生活リズムの不調」、「学業の不振」、「友人関係をめぐる問題」など。基礎的な学習だけでなく、社会的スキル習熟の機会を逃すことにより、こうした子どもたちのウェルビーイングに加え、将来的な社会構築への影響が懸念されており、不登校児童生徒が安心して通える学校環境の整備が急がれています。
誰もが安心して通える「学びの多様化学校」の設置
文部科学省は、2023年3月に「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLO プラン)」を発表しました。同プランは、学校や地域社会、家庭、NPO、フリースクールなどと連携を図り、社会全体で「誰一人取り残されない学びの保障」の実現を目指しています。
その一環として目標としているのが、「学びの多様化学校」を全国で300校設置すること。不登校児童生徒の実態に配慮した、特別な教育を行う学びの多様化学校は、2025年2月現在、日本全国に小、中、高校合わせて35校あります。うち21校が公立、14校が私立。一般的な学校と同じ卒業資格を得ることが可能です。
札幌にある学びの多様化学校(中学校)では、学校の開始および終了時間や授業の時間、教室などは設定されているものの、生徒たちはこれにとらわれず、それぞれのペースで学習することができます。また、教師とマンツーマンで1日を振り返る時間を設け、ソーシャルスキルを身につけるゲームを導入するなど、コミュニケーションスキルを高めることにも注力しているのが特徴です。
学びの多様化学校などのように、安心して登校することができる学校環境を地域全体で整えることにより、従来の学校に馴染めない子どもたちも学びの機会を得られるようになることが期待されています。
どこからでもアクセス可能なオンラインスクール
高等教育においては、オンラインの選択肢も増えてきました。文部科学省は、2024年4月から、不登校となっている高校生の卒業支援を目指し、オンライン授業による単位認定制度を導入することを決定。同制度のモデル校を指定し、学習効果などの検証に着手しています。
また、KADOKAWAとドワンゴが2016年に創立した私立のN高等学校は、従来の学校形態に近い「通学コース」、自分のペースに合わせてオンラインで学ぶ「ネットコース」、他の生徒とともにオンラインで学ぶ「オンライン通学コース」など、多様な形態での学習環境を提供。従来の学校に馴染めない生徒だけでなく、自宅周辺の通学可能な学校が少ないなど、地域的に教育の選択肢が限られる生徒、特定の活動に注力するために柔軟なスケジュールが必要な生徒なども、学ぶことを継続し、卒業資格を取得することができます。2024年9月の時点で生徒は3万人を超え、生徒数は日本一、海外の大学の合格者数も全国で第二位となっています。
N高等学校では、学習だけでなく、希望に応じて生徒同士の交流も活発に行うことができ、物理的に離れた場所で学んでいても、友達を作り、クラブ活動などを行うことも可能です。このようなオンラインスクールは、多様な学び方の選択肢を提供する、新たな形態として注目されています。
性の多様性を包摂する新たな取り組み
日本の学校における、ジェンダーの多様性に関する認識も高まってきました。その一例として、制服の選択肢が増えたことが挙げられます。これまで、日本の学校の制服は一般的に、男性はズボン、女性はスカートというように、性別によりデザインが分かれていました。一方、学生服メーカー大手のトンボによると、ここ数年は、新しい制服を検討する学校の9割以上が「多様性に配慮した制服」の要望を出しています。
さらに、同社では新たな学校制服の取り入れ方に関し、公式サイトに、「『ジェンダーレス』や『多様性』を強調するのではなく、『選択の自由』を推進することにより、誰もが精神的負担を感じることなく新たな制服を選びやすくなる」と記載するなど、配慮を呼びかけています。
学校における多様性や包摂性が未来のレジリエンスにつながる
企業や経済における、多様性、公平性、包摂性の重要性は、世界経済フォーラムのレポート「Diversity, Equity and Inclusion Lighthouses 2024」でも提唱されています。これらは、教育現場においても不可欠な要素です。安心して学習できる多様かつ包摂的な環境を整え、子どもたちの社会的なスキル習得の機会を育むことは、社会のレジリエンス強化につながるのです。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
関連トピック:
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。