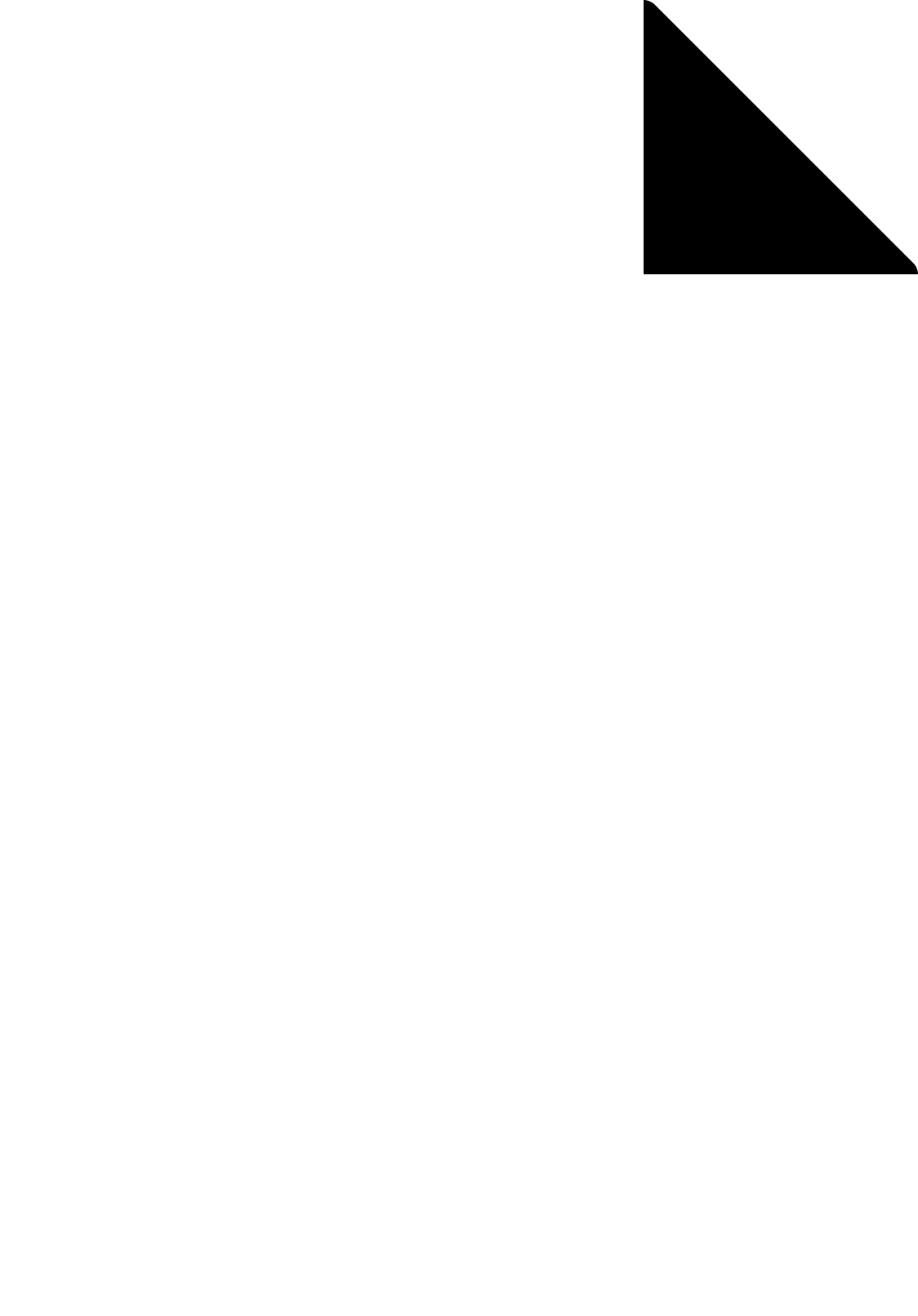同性パートナーを「配偶者」として福利厚生認めるのは1割以下。問われる企業の多様性

公正な福利厚生とは何か?家族とは?最新の調査結果が問いかける。 Image: Unsplash/Norbu GYACHUNG
同性婚が法制化されていない日本。最近は法の不足を補おうと、同性のパートナーも法律婚をしている配偶者とみなし、同様の福利厚生を提供する企業が増えている。
しかし最新の調査で分かったのは、多くの企業が制度設計で婚姻を重視し、そんな現状を改めるべきと考える人も少ないという現実だ。
法律婚の有無が家族手当を左右する
調査したのは日本労働組合総連合会(連合)だ。2022年7月、20歳~59歳の働く男女1000名にアンケートを取り、職場にある家族への手当についてたずねた。以下にその結果を紹介する(小数点以下、切り捨て)。
「配偶者」に対して、「子ども」に対して、自身の職場にそれぞれ手当があると回答した人は60%にのぼる。
支給条件としては、配偶者に関する手当は「婚姻届を提出している」が39%と最も多く、「事実婚」や「同性パートナー」に配偶者手当を認めているのは、それぞれ3%、2%と極めて少なかった。
他に「世帯主」(10%)、「主たる生計維持者」(8%)などもあった。
子どもに関する手当についても同様で、支給条件で最も多いのは「婚姻届の提出」(31%)だ。こちらも「事実婚」3%、「同性パートナー」 2%と少なく、家族の福利厚生は法律婚の有無によって大きく左右されていると分かる。
一方、「住宅」手当の支給条件は「世帯主であること」が 21%で最多だった。変わらないのは、「事実婚」が 2%「同性パートナー」が 3%と低いことだ。
企業は公正な制度設計を

これら配偶者・子ども・住宅の手当について、「同性パートナーにも支給すべき」と回答した人はいずれも9%と1割に満たなかった。
「事実婚の場合も支給すべき」とした人は、子ども手当については11%で、他は9%だった。
25日に会見を開いた連合は、こうした調査結果について
「企業は婚姻届を前提に福利厚生を考えるのではなく、それぞれの家族の形に合わせるべき。必要とする全ての人に支給できるよう、公正な制度設計をして欲しい」
”と指摘した。
「ダイバーシティ」や「LGBTQフレンドリー」を謳う企業は多い。その実現に向けて、社内制度から見直すべきだろう。
文=竹下郁子
このトピックに関する最新情報をお見逃しなく
無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
最新の情報をお届けします:
LGBTIインクルージョン
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。