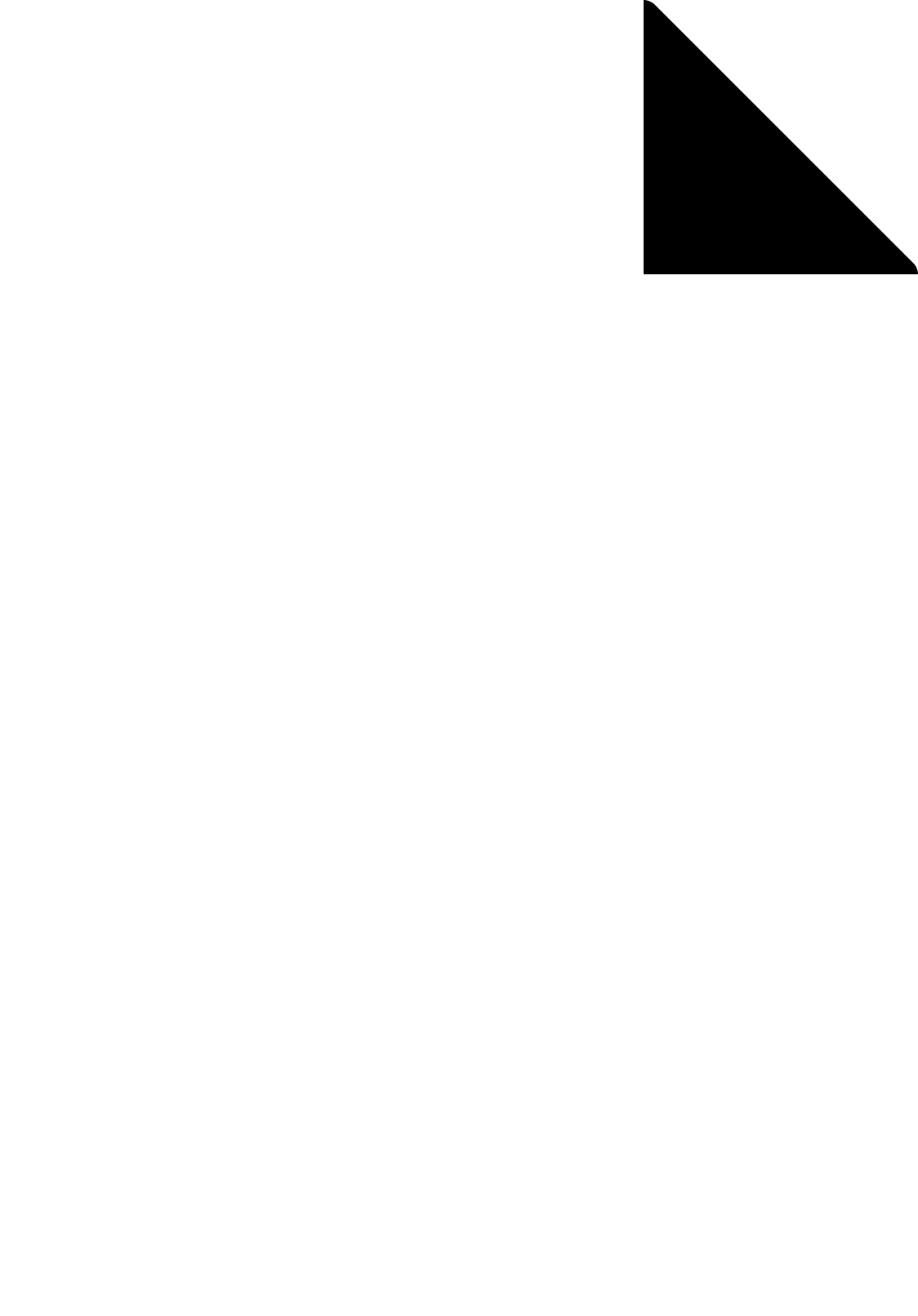コロナ明けのインフレリスク、意識するならいつか

コロナ禍からの出口は、まだ見えない。しかし、多くの国でワクチンの接種が始まったことなどから、今年後半以降の世界経済に一定の期待が持てるようになってきたことも確かである。 Image: 2021年 ロイター/Issei Kato
コロナ禍からの出口は、まだ見えない。しかし、多くの国でワクチンの接種が始まったことなどから、今年後半以降の世界経済に一定の期待が持てるようになってきたことも確かである。
同時に金融市場で浮上してきたテーマが、インフレである。株価好調の背景にある「低金利が長期的に続く」というストーリーは、インフレが訪れるなら根底から崩れる。多くの市場関係者がインフレを今年のリスク上位に挙げるのは理解できる。
インフレが話題になる理由
インフレの予兆は既にある。鋼材、非鉄金属、農産物など一次産品や素材の価格が上昇している。深刻な半導体不足やコンテナ輸送の混乱などのボトルネックも発生している。
背景にあるのは「モノ」に対する世界的な需要の急回復である。実際、日本の輸出もV字回復しており、昨年11月にはコロナ前の水準をあっさり上回った。
さらに今後ワクチン接種が順調に進めば、旅行、飲食、娯楽などサービスに対するペントアップ・ディマンド(繰越需要)が、例えば米国のケースでは今年後半にも強まる可能性がある。コロナ禍の間に増加した家計貯蓄も、コロナ明けの需要を押し上げる。
米国のインフレ率は昨年、原油価格の急落やサービス価格の低迷で大きく低下した局面があった。今年の4〜6月期はその反動で、物価の前年比は高い数字になる。米連邦準備理事会(FRB)の物価目標である2%を上回る可能性が高い。
もちろん、前年の反動による数字の高まりは、インフレの実態とは関係ない。しかし、それがコロナ収束を視野に入れるタイミングと重なれば、市場はインフレの到来をどうしても意識する。これは今年の金融・為替市場の波乱要因になりうる。
石橋をたたいても渡らないFRB
しかし、実際には金融政策の正常化に向けたFRBの動きは、極めて慎重なものになりそうだ。FRBは、昨年8月に打ち出した新戦略と、それを踏まえたフォワードガイダンスにより、利上げの開始に厳しい条件を課している。具体的には、1)最大雇用の実現、2)2%インフレの実現、3)その後しばらく2%超のインフレが続くという見通し──の3条件がすべて満たされない限り、利上げには「指一本」触れないことになっている。
そして、その状態に向けて十分な進展があったと判断されるまでは、資産買い入れの縮小(テーパリング)すら開始しない、という縛りも昨年12月に加えた。
製造業のV字回復によるボトルネック、コロナ収束によるペントアップ・ディマンドなどで、仮に高めのインフレ率が半年や1年続いたとしても、中長期を重視する中央銀行の時間軸でみれば、それらは短期的なノイズに過ぎない。
FRBをはじめ多くの中央銀行が目指しているのは「2%の物価上昇が、特別の理由なく日常に溶け込んでいる状態」である。一時的で特別な理由があるなら、物価が2%を超えて上昇してもインフレではない。
これは物価下落についても同じである。原油価格の下落や「Go Toトラベル」などで物価が下落してもデフレではない、という日銀の説明は正しい。
もちろん、当初は一時的と考えられていた物価上昇が、その後賃金の上昇などにも広く波及して、徐々に持続的な物価上昇につながっていく可能性はある。
しかし、一時的な物価の上昇がなぜ持続的なものに転じるのか、その正確なメカニズムはよくわかっていない。経済学的には「インフレ期待の上昇」によって説明がつくことになっているが、逆に言えばインフレ期待というつかみどころのない概念でしか説明できないのである。
インフレ期待は、それを推し量る多くの指標があるとは言え、最終的には実際のインフレで確認するしかない。インフレ期待の上昇でインフレが上昇するという説明は、トートロジー(同義語反復)の域を出ない。
持続的な物価上昇が起きるメカニズムがよくわかっていない以上、それが起きそうかどうかの見立てはかなりの程度、経験則によらざるをえない。
この点、金融危機から10年以上の間、米国のインフレ率はほぼ一貫して2%を下回ってきた。しかもその間、景気が悪かったわけではない。むしろその期間のほとんどは「史上最長の景気拡大期」であったし、失業率も半世紀ぶりの低水準まで低下した。それでもインフレが上がらなかったという事実は重い。
インフレ・レジームへの転換はあるか
ちなみに日本の場合は、1%をも下回る低インフレ基調が25年以上も続いている。日本が他国より圧倒的に早く低インフレになったことは、世界の経済論壇に1つの不幸をもたらした。それは、低インフレが日本固有の現象と認識されてしまい、バブル崩壊後の政策の失敗という切り口以外に議論が深まらなかった点である。
近年になってようやく、低インフレには先進国共通の要因も作用しているという問題意識が、アカデミズムや中央銀行コミュニティで共有されてきた。
インフレは完全に「貨幣的な現象」ではなく、実体経済の構造的な要因からも影響を受ける、という可能性を踏まえた議論がなされるようになったのである。構造的な要因の候補として、グローバリゼーションや情報技術の進歩など様々な仮説が言われているが、決定的な答えは出ていない。
そうした中で昨年出版された一冊の本が話題を呼んでいる。かつて英中央銀行の政策委員も務めたチャールズ・グッドハート名誉教授(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)らによる「The Great Demographic Reversal」である。
その中で著者らは、安価な製品の供給源となってきた中国の高齢化や、先進国自身の高齢化による労働力の供給不足などから、労働者の賃金交渉力が強まり、過去数十年の低インフレ時代は終わる、と主張している。
もちろん、これもあくまで仮説であり、インフレ時代への大転換を予想する識者は少数派である。最も早期かつ急速に高齢化が進んだ日本で、真っ先に低インフレとなった事実だけからみても、労働力人口の減少でインフレが進むと単純には言えないだろう。
株主リターンを重視する資本主義のあり方が大きく変容しない限り、いくら労働力不足になってもロボットやAIでそれを補う経営努力が強まるだけで、労働者の賃金交渉力は強まらないのではないかとも考えられる。
しかし、コロナ禍のような100年に1度とも言われるショックに見舞われると、ほかにも非連続な変化がいろいろ起きるのではないかという不安や期待を、人は抱きやすくなるものである。
米国以上にしぶとい低インフレと戦っている欧州中央銀行(ECB)でさえ、シュナーベル専務理事が年初のインタビューで、前述したグッドハート氏のインフレ転換論に、それを頭から否定しない形で言及している。
「ポストコロナをどうみるか」という議論の設定自体に、従来の延長線上での未来予想は知的ではない、という圧力めいたものを人々に感じさせるニュアンスがある。インフレ到来の予想もそういう雰囲気を反映したものに過ぎないと筆者は考える。
一方で、各国の中央銀行が低金利の長期継続をかつてない強さで約束し、あらゆる資産価格がそれを前提に形成されている現状には、未知の世界であるがゆえの一抹の不安も残る。今やインフレは、確率は低いがそれが起きた場合の影響は計り知れない、というタイプのリスクになってしまった。そうしたリスクがたとえ顕在化しても金融システムは盤石なのかどうか、金融機関も金融当局も備えを怠るべきではない。
時間はまだ十分ある。今年の半ばごろから人々が目にする物価の上昇は、とりあえず無視できる性格のものだ。ただし、2〜3年後には経済が本格回復し、労働市場がコロナ前の活況を取り戻している可能性はある。それまでにリスクの点検だけはしておくべきだろう。
*この記事は、Reutersのコラムを転載したものです。
このトピックに関する最新情報をお見逃しなく
無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
最新の情報をお届けします:
日本
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。