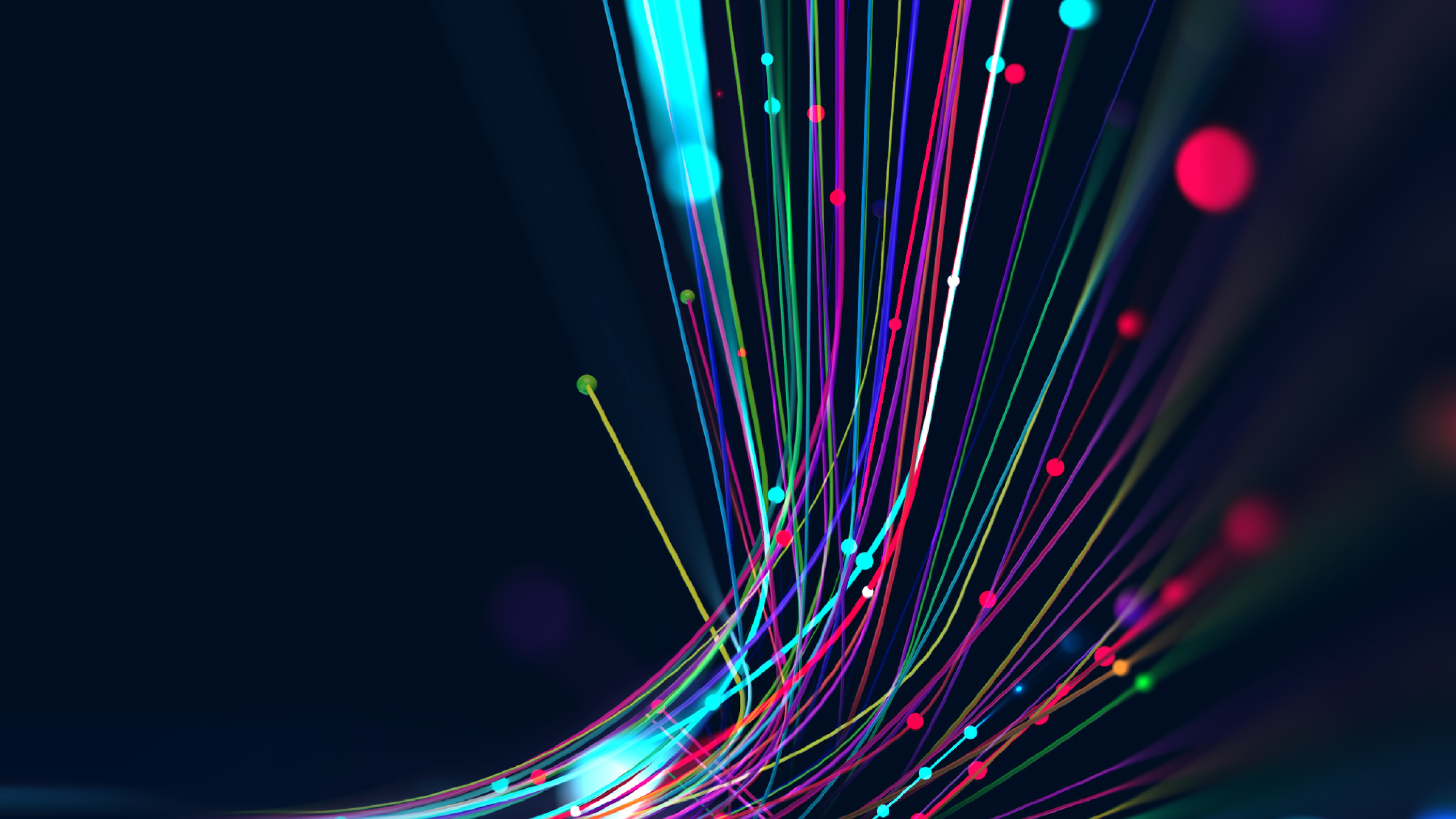アジアの超富裕層が動かす、新たなフィランソロピー

コインの入ったグラスから1本の木が芽吹いている。適切な戦略に基づくフィランソロピー(慈善活動)は、広く影響を及ぼします。 Image: Photo by micheile henderson on Unsplash
- アジアには、世界で最も多くの億万長者が集中しています。
- アジアの資産保有者は、慎重な慈善活動ではなく、触媒的なリスクとして資本を活用することにより、リスクを軽減しつつ、最も重要な投資を加速させることが可能になります。
- アジアの慈善活動は、気候安全保障、経済的レジリエンス、開発インパクトの未来といったグローバルな課題解決において大きな影響力を持ち、戦略的な柱となり得るでしょう。
アジアは世界で最も多くの億万長者を抱える地域でありながら、彼らの「善行」の方法は依然として慎重かつ伝統的な助成金提供に重点を置く傾向があります。このため、人々と地球が直面する喫緊の課題に対処することのできる膨大な可能性が、未開拓のまま残されているのが現状です。
国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成には、公衆衛生の改善、教育機会の拡大、気候変動への耐性強化などに年間2.5兆ドルの資金が必要です。現在、この資金が不足していることから、明らかに分かることがあります。この資金不足は、多くの政府が依然として新型コロナウイルス感染症の影響で縮小した予算に苦慮している時期、また政府開発援助(ODA)が減少傾向にある時期に起こっています。経済協力開発機構(OECD)の予測によると、寄付者の優先順位の変化により、2025年にはODAが9~17%減少する見込みです。
もしアジアの慈善家たちが積極的に行動すれば、この地域の規模が大きいこと、変化が起こる分野が多岐にわたることから、2030年までにSDGsを達成する可能性は大いに高まります。そうすることで、彼らは世界の安全保障、安定、繁栄の方向性に影響を与えることができるでしょう。
したがって、アジアの最も裕福な人々にとっての選択は単純ですが、非常に重大なものです。従来の助成金で小さな隙間を埋めるだけの現状維持を続けるのか、それとも大胆に行動するのかということです。
より多くの支援を行いましょう。アジアの寄付額が米国のGDP比2%という基準に達した場合、年間7,000億ドルの資金動員が可能となり、SDGsの資金不足の4分の1以上を賄えると推定されています。
一方、単に寄付額を増やすだけでなく、その方法も重要です。
慈善活動を触媒的なリスク資本へ
これは、譲歩的で忍耐強く、柔軟な資金提供を意味します。実現すれば、公的投資と民間投資のはるかに大きな資金プールが解放されるでしょう。この役割において、慈善活動は官民の資金を呼び込むブレンデッド・ファイナンスの基盤となり、戦略的に活用すれば、インパクトのある事業のリスクを軽減し、商業資本を呼び込むことが可能になります。「触媒的資本」とは、助成金の代替ではなく、その価値をレバレッジによって増幅したものです。
この触媒的資本の可能性を示す証拠があります。慈善活動による1ドルの資本投入により、SDGs関連投資として4~30ドルの資金が解放されることが実証されているのです。実例として、ロックフェラー財団の「ゼロ・ギャップ・ファンド」が挙げられます。同財団がコミットした3,000万ドルの資本は、アジア地域において10億500万ドル以上の雇用創出支援、生活改善、複数の投資促進を実現しました。
また、東南アジアにおける触媒的金融の好例が、アジア開発銀行の「グリーン・リカバリー・プログラム」です。緑の気候基金(Green Climate Fund:GCF)からの3億ドルの拠出によって実現した「ASEAN カタリティック・グリーン・ファイナンス・ファシリティ(ACGF)」では、37億ドルの資金が動員されました。このプログラムの重点分野は低排出インフラプロジェクトであり、現在15件が進行中です。
注目に値する成果ではありますが、このような事例はまだ非常に少なく、数十億ドルから数千億ドル規模へと拡大するために必要な構造的な転換を実現するには不十分です。
大胆な構想を具体的な成果に変えるための3つの転換
1. 共創への開放
一部の慈善家は、従来の考え方や本能的な抵抗感から、従来とは異なるアプローチを取ることをためらっています。具体的には、自分たちの資金が政府の資金援助と補完関係にあることや、利益の最大化を目指す企業の「富裕層」を支援することに抵抗を感じる場合です。このような考え方は改める必要があります。縦割りの壁を打ち破り、パブリックセクター、企業、慈善セクターの三者連携(PPPP)という新たな協働の文化を創造するのです。
インドのセントラル・スクエア財団(CSF)はこの可能性を実証しています。州政府と連携して、同財団は技術チームを配置し、教育方法を改革すると同時に、企業との連携を強化。学校における基礎的な識字能力と計算能力の向上を実現しました。これにより、公共予算から2,000億ルピー(約2億4,000万米ドル)の資金を引き出すことに成功し、基礎的な識字能力と計算能力の向上を国家的な使命として位置付けることができました。
医療分野では、日本の「グローバルヘルス技術振興基金(GHIT Fund)」があります。同基金は、注目されることが少ない疾患に対する研究開発における体系的連携を、先駆けて推進しており、ゲイツ財団とウェルカム・トラストからの約5,000万米ドルの慈善資金支援、日本政府と国連開発計画(UNDP)の支援を受け、世界の保健イノベーションのために2億米ドル以上の資金を調達しました。
これらの事例は、慈善活動がリスク資本として、各国政府がシステムリーダーとして、企業がイノベーションの推進役として機能する、双方にメリットのある道筋を示しています。
2. 人々の生活と生計を改善する、大規模かつ触媒的な慈善活動の有効性を説得力を持って実証
東南アジアでは、フィランソロピー・アジア・アライアンス(PAA)とその加盟団体が資金提供するオーストラリアのNPO、クライメートワークス・センターの「東南アジア海洋気候緩和フレームワーク(SEAFOAM)」プロジェクトが、海洋を活用した気候変動緩和策に関する戦略の推進に貢献しています。同プロジェクトは、ブルーカーボンエコシステム、海上輸送、洋上再生可能エネルギーといった要素を各国の政策に統合することにより、触媒的な慈善活動が公共政策を支援し、沿岸地域のコミュニティを強化し、気候変動対策のための持続可能な資金調達を可能にする方法を示しています。
また、シンガポールのテマセク生命科学研究所が手がける、受賞歴のある「脱炭素化稲作プロジェクト」は、低炭素農業の実践導入、水利用効率の向上、気候変動に強い稲品種の普及を実現する可能性を秘めています。一方で、インド、インドネシア、ラオスでは現在、寄付者資金による実証実験が進行中ですが、その真価が問われるのは実際の導入段階です。慈善資金は普及を促進し、地方自治体、商業的買い手、サプライチェーン関係者を連携させることができるのでしょうか。
今後の展開が注目されます。
3. 知識共有と信頼関係構築のためのプラットフォーム
リスク資本としての慈善資金の活用とは、直感的に理解できるものではないため、取引構造や異業種間のモデル構築は複雑な作業となります。また、単に協力関係を築くこと も容易ではありません (「こちら側の条件を飲むなら協力しよう」とは、よく聞かれる言葉でしょう)。このため、多様なステークホルダーを集め、相互の信頼関係を構築し、何が成功し、何が失敗したかを共有するプラットフォームには高い価値があります。
アジアではこの必要性が徐々に認識されつつあります。シンガポールで開催された「フィランソロピー・アジア・サミット」や香港で開催されたAVPNグローバル会議など、近年このテーマに関する率直な議論を行う地域会議が相次いで開催されています。さらに、アジア最大の社会投資家ネットワークのAVPNと、コンサルティング企業のBCGが主導する「アジア・パートナーシップ・フォー・インベストメント・イントゥ・レジリエント・エコノミー(ASPIRE)」のような新たな協働イニシアチブも登場しており、慈善家やエコシステムがブレンデッド・ファイナンスの分野を理解し、効果的に関与していくための支援を行っています。
アジアの世紀、アジアの好機
求められるパラダイムシフトは、単に金融面だけでなく、リーダーシップに関するものです。アジアの慈善活動は、気候安全保障、経済的レジリエンス、開発インパクトの未来といったグローバルな課題解決において大きな影響力を持ち、戦略的な柱となり得るでしょう。資本を慎重な慈善事業としてではなく、触媒的なリスク投資として展開することにより、リスクを軽減しつつ、最も重要な投資を加速することが可能です。そうすることによって、アジアの資産保有者は世界が直面する最大の課題に対処するための新たなルール形成に主導的な役割を果たすことができるでしょう。
本寄稿文の著者であるショーン・スォウ氏はフィランソロピー・アジア・アライアンスのCEO、バラド・パンデ氏はボストン・コンサルティング・グループのパートナー兼ディレクターを務めています。いずれも2025年夏にロックフェラー財団ベラージオ・センターに招聘され、その経験がASPIREイニシアチブの立ち上げと、アジアにおける革新的ブレンデッド・ファイナンスの拡大につながっています。
このトピックに関する最新情報をお見逃しなく
無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
最新の情報をお届けします:
日本
関連トピック:
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。