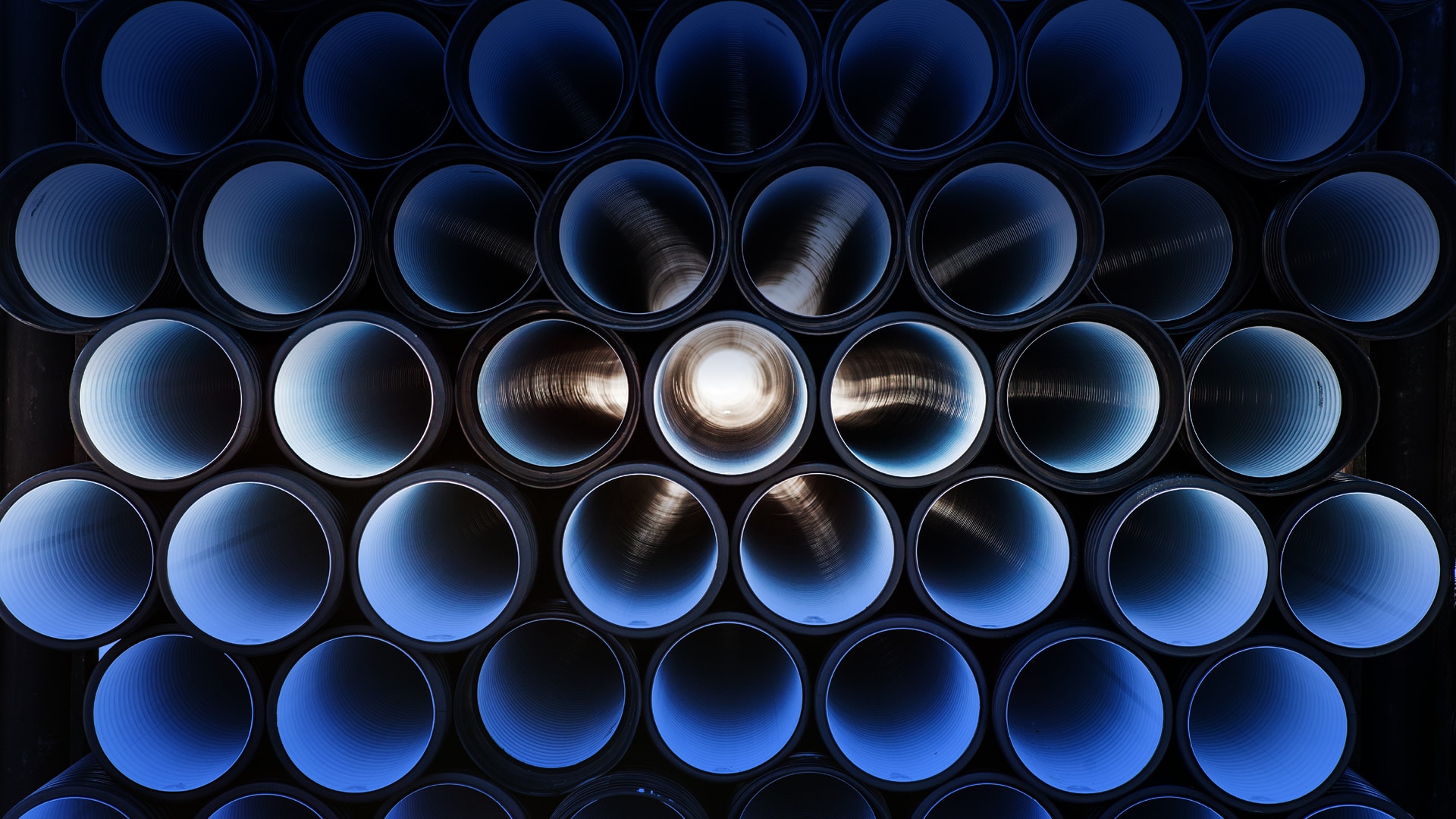よりスマートかつレジリエントな交通に向けた日本の取り組み

交通をはじめとする公共サービスの維持は、日本においてこれまで以上に重要な課題となっています。 Image: Unsplash/Michael Pfister
- 日本では、交通をはじめとする公共サービスを維持することの重要性が増しています。
- 現在、日本の人口の20%以上が、最寄りの鉄道駅から500メートル以上、バス停から300メートル以上離れた場所に暮らしています。
- こうした状況を踏まえ、政府や企業はデジタル技術を活用しながら交通サービス全体の再設計を進め、地域社会の移動手段を将来にわたって確保する取り組みを強化しています。
人口動態の変化は、社会インフラの維持に大きな影響を与えます。過疎化と高齢化が進む日本では、人手不足により地域の交通サービス維持が深刻な課題となっています。その一例が、駅やバス停が一定距離以内に存在しない「交通空白」です。ある調査では、居住地から500メートル以内に駅、300メートル以内にバス停がない住民は人口の20.7%に達しています。中にはタクシー事業者が撤退した地域もあり、国民の3割を上る高齢者や車を保有しない層の移動手段が制限され、日常生活の不便が拡大しています。
交通事業者もまた、乗務員の不足や収益悪化など複合的な課題に直面しています。全国のバス、鉄軌道、旅客船事業者を対象にした調査では、現状では路線維持が困難だと回答した事業者が55%に上り、特にバスでは約7割に達しました。また、2019年比でバスでは9割以上、鉄軌道では約6割の事業者が従業員減少を経験しており、4割の事業者が制度改革の必要性を強く訴えています。
こうした状況を受け、日本では政府や企業がデジタル技術などを活用し、業務効率化および交通サービスの改革に取り組んでいます。
国が率いる交通の改革
国土交通省は、2024年7月に「交通空白」解消本部を設置しました。これは、タクシーやライドシェアなどを要請してから30分以内に利用できない地域を対象に、その解消を目指すものです。現在、自治体や交通事業者と連携し、地域ごとに課題や対策、必要な支援の調査が進められています。
さらに同省は、2025年度から「地域交通DX:MaaS2.0」プロジェクトを開始しています。同プロジェクトは、「サービス」「データ」「マネジメント」「ビジネスプロセス」の4つの観点からデジタル活用を推進し、地域交通を「リ・デザイン」することで「交通空白」の解消を目指すものです。2025年度には、15の実証プロジェクトが採択されています。
その一つが、経営とITをデザインするフューチャーアーキテクト社と連携した、「ビジネスプロセス」部門のバス業務標準化プロジェクトです。バス事業における業務手順やシステム、データ仕様は事業者ごとに異なっており、事業者間での連携が難しいことが課題とされてきました。本プロジェクトではこれらを全国的に標準化することで、システム導入やリプレイス、データ連携にかかるコスト削減と業務効率化を図ります。個別最適化から共通基盤への移行を促進することにより、利用者の利便性向上だけでなく、データ活用による新たなサービス創出や産業構造の強化が期待されています。
また、富士通との連携で行われているのが、「マネジメント」部門の地域交通の総合シミュレーションシステムの技術実証プロジェクトです。交通分野では、新たな仕組みを導入する際、その効果やコストを事前に見極めることが難しく、導入の障壁となってきました。同社はデジタルリハーサル技術を活用し、車両数や運行ルート、サービス提供時間などを条件ごとに繰り返しシミュレーション。利用者の利便性と収益・コストを総合的に評価することを提案しています。これにより、地域特性に適した持続可能な交通モデルの設計が可能となり、可視化された結果は、自治体や事業者、住民の合意形成にも寄与します。
新たな技術の実証実験を可能にする、トヨタの実験都市
企業主導の取り組みも進展しています。トヨタ自動車は、約70万8,000平方メートルにおよぶ工場跡地を活用し、実証都市「ウーブン・シティ」を2025年9月に開業。「生活する実験都市」をコンセプトとし、将来的に約360人が実際に暮らし、働き、遊ぶことで、モビリティ分野を含む様々な製品やサービスにおける新技術の検証を行います。
敷地内では、車の接近に応じて歩行者信号が自動切り替わる仕組みなど、公道では実現が難しいコネクテッド技術の実証が可能となっています。また、地下には約100メートル四方の周回路が整備されており、自動運転ロボットによる宅配やゴミ収集など、次世代物流の実証も進められています。これにより地方交通や物流を含むモビリティ全体のさらなる効率化が期待されるとともに、人々の生活に密着した形で新たなサービスや産業モデルの創出が見込まれています。
交通システムを革新し、レジリエンスのある社会へ
バス、鉄道、タクシーといった交通インフラは、人々の日常生活に欠かせない基盤です。日本では、過疎化と高齢化の進行に伴う、地域交通を取り巻く課題が深刻化する中、交通インフラを維持するための業務の効率化や運行の最適化を図る取り組みが、進められています。
これらの取り組みは、単なる効率化やコスト削減にとどまらず、デジタル技術やデータ活用により、地域特性に合わせた柔軟な交通モデルを設計することが可能とします。人々の移動の自由を支えるだけでなく、持続可能で包摂的な社会への移行を後押しする役割も果たしています。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。