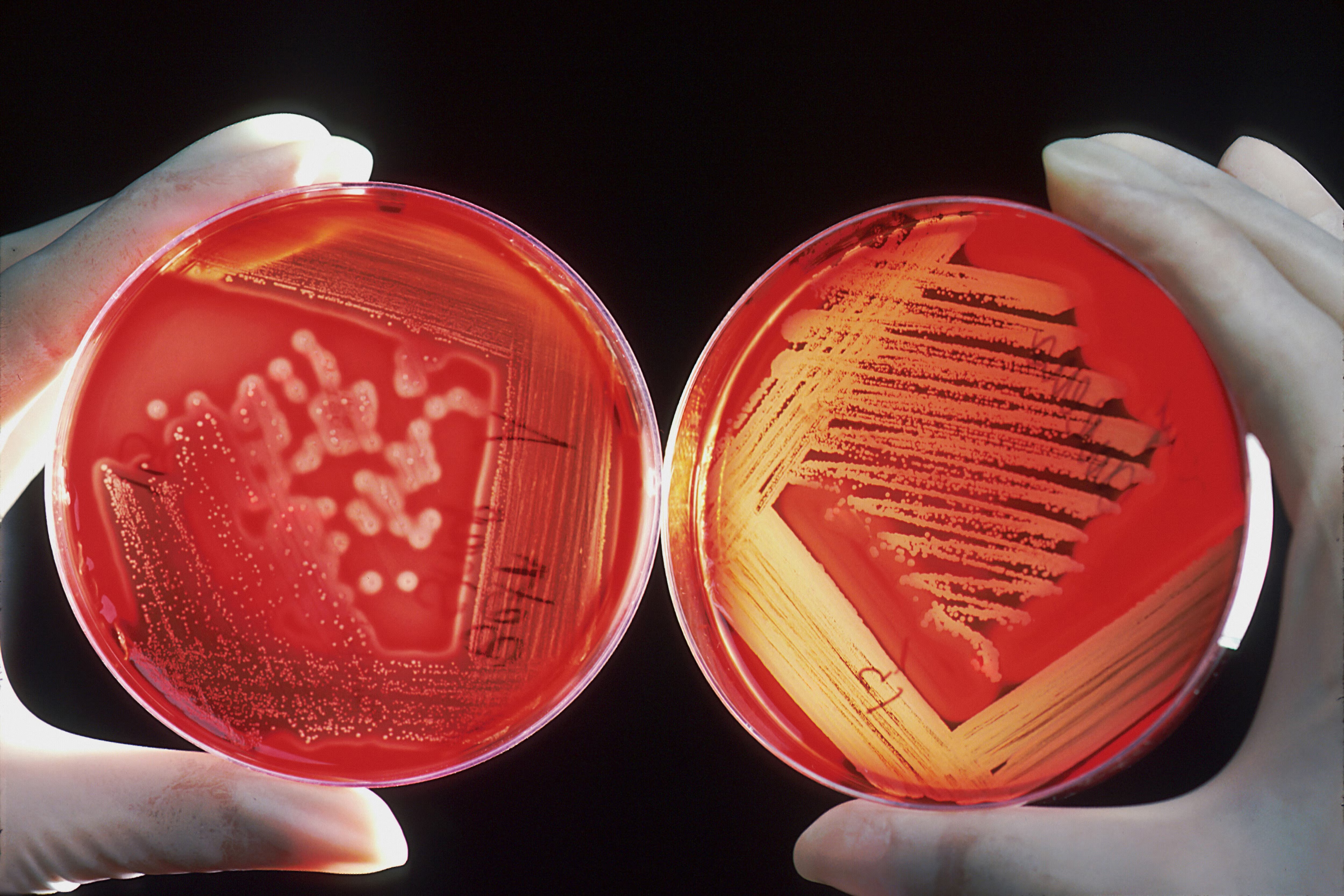健康寿命と地域を支える、日本の運動習慣とは

日本では、長年にわたる運動習慣が、公衆衛生や職場での生産性、そして地域社会のレジリエンスを支えています。(東京都八王子市南大沢) Image: Unsplash/FumiakiHayashi
- 日本人の1日あたりの座位時間は国際的に見ても長く、在宅勤務の普及に伴い歩数も減少しています。
- 一方、日本では週に1回以上スポーツをする人が半数を超え、1992年の24%から大幅に増加しています。
- ラジオ体操や「スポーツの日」といった取り組みも、健康的な高齢化、職場環境の充実、レジリエンスのある地域社会の実現に寄与しています。
心身の健康にとって、日常的な運動は欠かせません。しかし、世界的には、成人の約30%、青少年の80%青少年が十分な運動を行っていないとされています。世界保健機関(WHO)は、身体活動が非感染性疾患の予防・管理や心身の健康維持に寄与し、子どもや青少年においては骨や筋肉の成長や運動能力、認知能力の発達を促進すると指摘しています。さらに、現在と同じレベルの運動不足が続く場合、2020年から2030年の間に世界の公的医療システムにかかる推定コストは約3,000億米ドル(年間約270億米ドル)に達すると見込まれています。
日本でも運動量の低下が報告されています。過去50〜60年間で職業における身体活動は平均約10%減少し、座位時間は1日平均420分に達しており、世界最長水準とされています。また、在宅勤務の増加に伴い、1日の歩数も徐々に減少傾向にあります。一方、2024年に18歳以上の男女3,000人を対象に行われた調査では、週1回以上スポーツをすると回答した人は54.8%に達しました。これは、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以前からはわずかに減少しているものの、1992年の23.7%からは大幅に増加しており、着実な進展も見られます。
こうした状況の中で注目されているのが、日本社会に根付いた運動習慣です。その代表例であるラジオ体操や運動会に加え、国民の祝日「スポーツの日」もまた、体を動かすきっかけを提供しています。スポーツの日は1964年の東京オリンピック開催を記念して制定され、現在は10月第2月曜日に設定されています。毎年全国各地で関連イベントが行われ、普段運動習慣のない人々にもスポーツに親しむ機会を広げています。
また、日本には21万カ所以上の体育・スポーツ施設があります。そのうち約5万カ所が公共施設であり、公立学校の86%が体育施設を一般開放。低料金で利用できる施設も多く、運動会やスポーツの日のイベントだけでなく、日常的に体を動かすための基盤が広く整備されています。
手軽に取り組めるラジオ体操
ラジオ体操は1928年、逓信省簡易保険局(現・かんぽ生命)により制定され、現在も毎朝6時半から放送されています。約3分のプログラムには関節や筋肉の柔軟性、バランス、下肢筋力、全身持久力などを維持するために必要な要素が組み込まれており、「いつでも、どこでも、誰でも」取り組める手軽さから、教育現場や地域社会に広く浸透しています。認知率は96.9%に達し、日本人にとって最も身近な運動習慣の一つとなっています。
また、建設業など身体的負担の大きい職場では、作業開始前にラジオ体操を実施する企業も少なくありません。血行促進や柔軟性の向上を通じて疲労や怪我を防ぐ効果が期待され、全員で同じ動作を行うことで、チームワークの強化にも繋がっています。高齢者を対象とした調査では、12週間の実施によりバランスや持久力が改善し、介護予防に有効であることが確認されています。さらに、1万1,219人を対象とした追跡調査では、ラジオ体操を実践している高齢者はそうでない人に比べ、認知症のリスクが18%低いことが示されており、高齢社会における健康維持の手段としても期待がもたれています。健康面にとどまらず、ラジオ体操は世代をつなぎ、日常生活に運動を根付かせる共有の儀式として、文化的な連続性を体現しているのです。
コミュニティをつなぐ運動会
運動会は、1872年の近代学校制度の発足とともに高等教育機関で導入され、その後小中学校へ広まりました。現在では学校教育の一環として定着するだけでなく、企業や地域社会でも開催され、コミュニティの形成や世代間交流を促進しています。一般的に、二つのチームに分かれて競技を行い、数ヶ月前からの準備や練習も含め、多くの人々が体を動かす機会を得ます。
また、「健康経営」の取り組みの一環として運動会を開催する企業も増えています。その一例が、「UNDOKAI WORLD CUP 2025」の開催を予定しているパソナグループです。同グループは、誰もが楽しむことのできる競技を通じ、ウェルビーイングを体感できる場を提供するとしています。こうした企業主導の大規模運動会は、従業員だけでなく地域や社会全体を巻き込み、健康づくりと交流促進の新しいモデルとなっています。このような背景から、近年では運動会を専門に企画・運営するサービスも登場しています。
社会インフラとしての運動習慣
高齢化が進む日本では、長寿化のみならず、健康寿命の確保が強く求められています。身体機能に加え、精神的・認知的な健康を維持するためにも、適度な運動が不可欠です。ラジオ体操や運動会のように、世代を超えて共有される運動習慣は、人々の健康を支えるだけでなく、職場の結束や地域社会のレジリエンス向上にも寄与しています。低コストかつ広く利用可能な習慣や設備がハイテク医療や政策的介入を補完し、人々の健康だけでなく社会全体のウェルビーイングを強化する解決策となり得るのです。
日本におけるこれらの取り組みは、単なる健康習慣を超え、社会全体の持続可能性を高める「インフラ」として機能しています。高齢化が進む世界において、心身の健康を維持し、地域のつながりを育み、経済のレジリエンスを強化する仕組みは、ますます重要性を増しています。日本の経験は、健康的かつ包摂的な社会を築くための重要な示唆を提供するとともに、持続可能な未来を形づける上で、国際社会にとっても重要な示唆を提供しています。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。