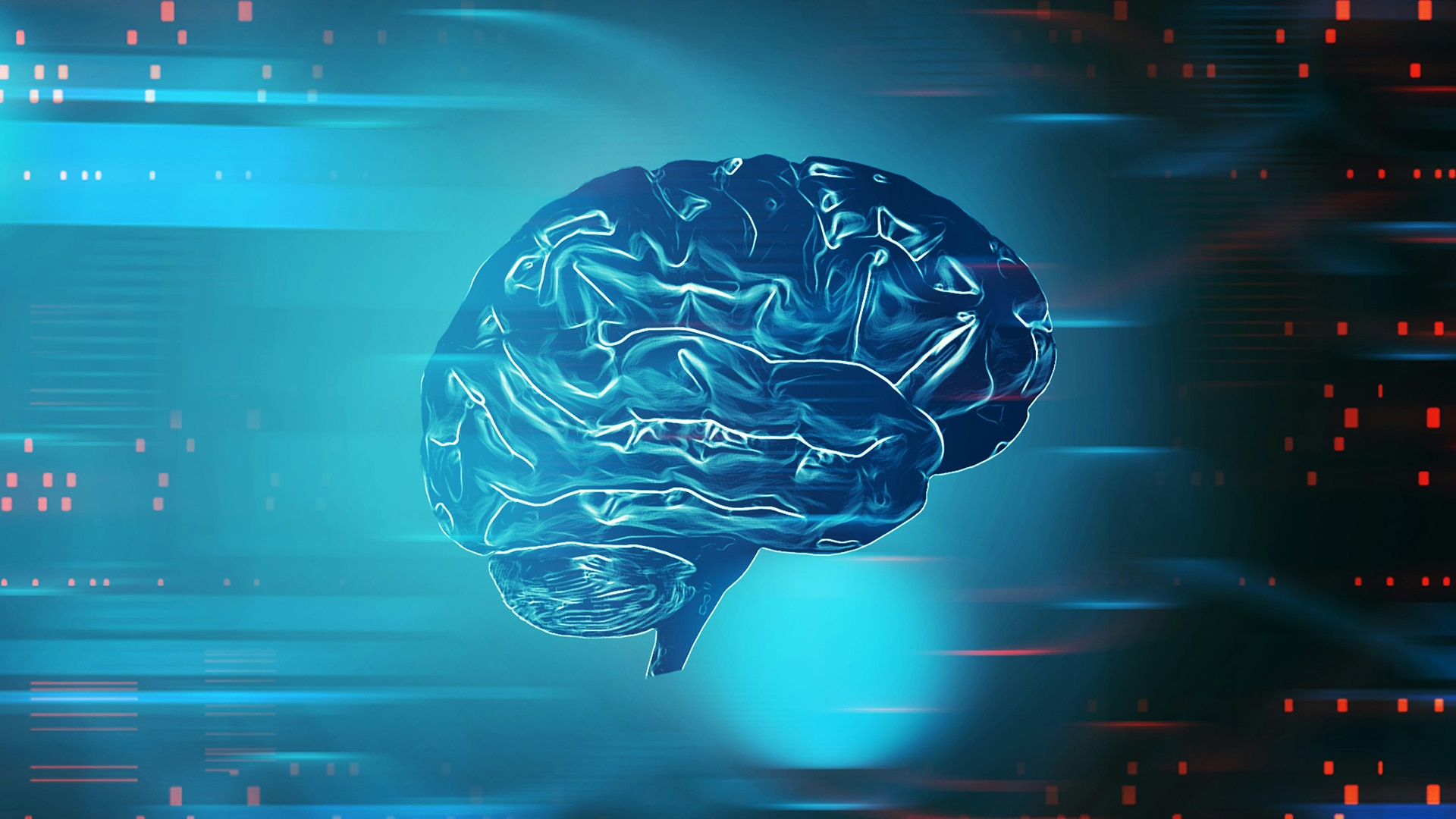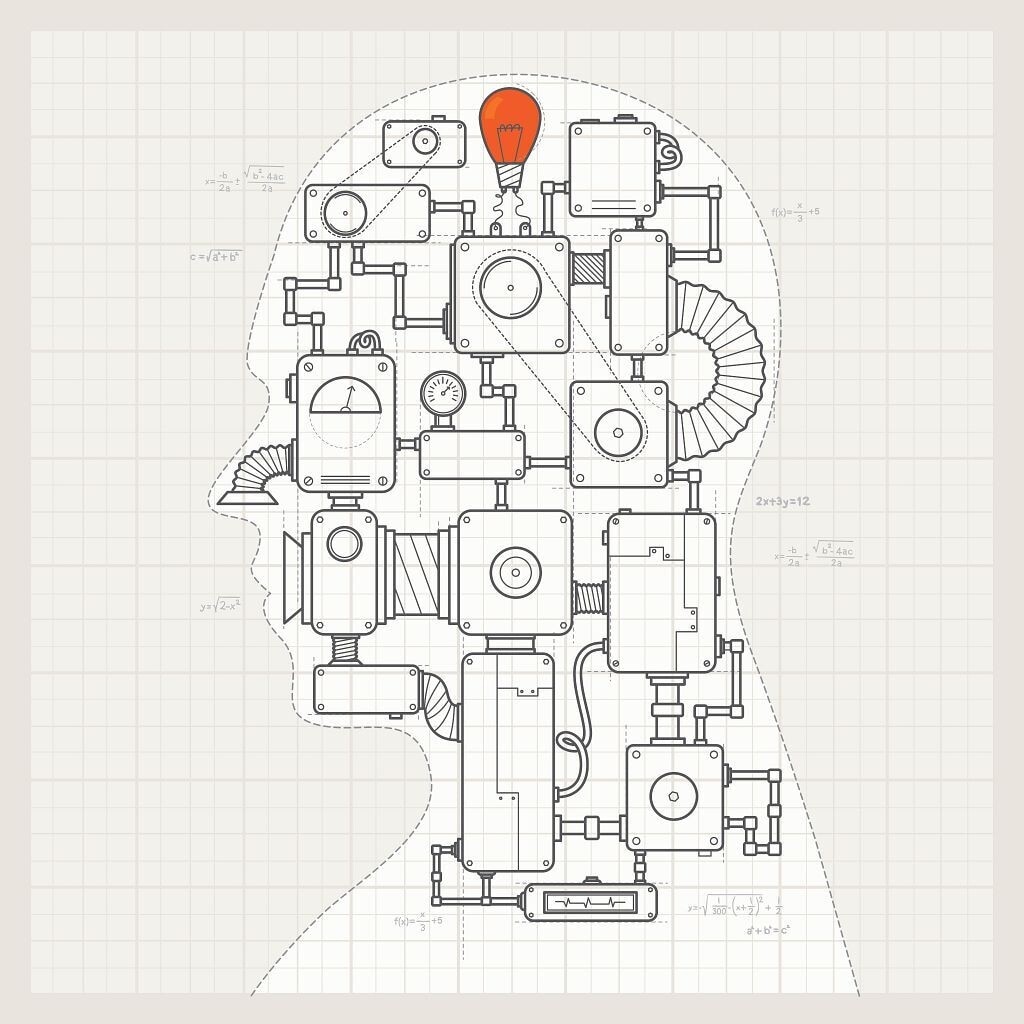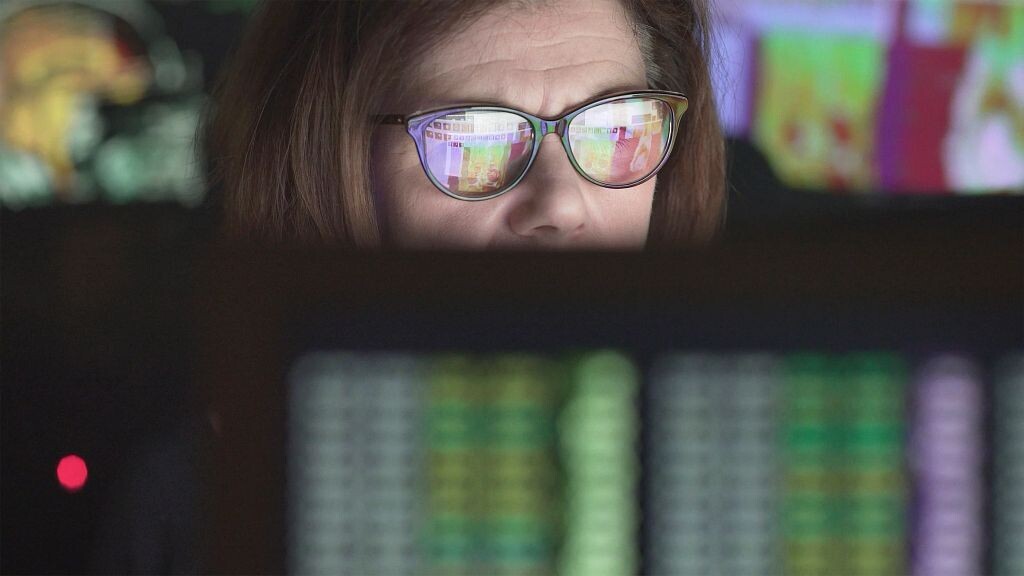スマートフォン依存拡大に対する、日本の新たな取り組み

日本における平均的なスマートフォンの使用時間は、1週間に約20時間と推定されています。 Image: Pexels/Talha Resitoglu
- 日本の比較的短い平均使用時間の背後には、特定の層におけるスマホ依存という課題が隠れています。
- こうした課題に対処するため、日本では先駆的な自治体条例の制定、および「スマホ認知症」に特化した東京の外来クリニックなど、新たな取り組みが進められています。
- これらの取り組みは、世界メンタルヘルスデーで掲げられている「心の健康を守るための幅広い取り組み」にも通じています。
スマートフォンは、今や生活に欠かせない存在です。電話やメッセージのやり取りに加え、インターネット検索やオンラインショッピング、健康状態のモニターなど、その利便性は社会や経済に多大な恩恵をもたらしてきました。一方、過度な使用や依存が進むことで、健康や人間関係に負の影響を及ぼす可能性も指摘されています。
スマートフォンの使用は世界的に拡大しています。2024年には使用台数が45億台に達し、日々の利用も長時間化しています。ある調査によると、1日あたりの平均使用時間はフィリピンが5時間21分と最も長く、ブラジル(5時間12分)、南アフリカ(5時間11分)と続きます。別の報告書では、米国における使用は1日5時間16分とされています。このような長時間の使用は、スマートフォンが現代の生活様式において不可欠な存在であることを示す一方、バランスや持続可能性に関する課題も提起しています。
長時間にわたるスマートフォンの使用は、視力の低下、睡眠障害、脳の発達や集中力への悪影響など、多岐にわたる身体への影響を及ぼします。そのため、世界各国ではスマートフォンの使用を制限する取り組みが進んでいます。フィンランドでは2025年8月から、小中学校でのモバイル端末使用を制限する法律が施行されました。フランスやイタリア、オランダ、中国でも学校でも同様の規制が導入されており、韓国でも2026年3月から実施予定です。また、オーストラリアやノルウェーでは、未成年をSNSの過剰利用から守るため、その使用に年齢制限を設けています。これらの規制は、デジタル技術の普及に伴い、安全策が不可欠であるという認識が高まっていることを示しています。
日本におけるスマートフォンの使用時間は、1週間で20時間程度、1日平均にして3時間弱とされています。この平均使用時間は世界的に見ると長くはないものの、その影響は多方面に及ぶことが明らかになっています。内閣府が2024年に実施した調査では、スマートフォンの使用時間が長い人ほど「孤独を感じる」傾向が高いことが示されました。さらに、使用を自ら制御できなくなり、学業や仕事、日常生活に支障をきたす「スマホ依存症」も深刻化。高校生の約10%、大学生の約25%に依存の疑いがあり、社会的な課題として認識されつつあります。こうした状況から、日本においても規制を含む新たな取り組みが進んでおり、教育や家庭での使用習慣の見直しを促しています。
日本における新たな試み
愛知県豊明市では、国内初となる、「スマートフォン使用時間の目安」を定める条例が執行されました。対象となるのは、約6万9000人の同市民および同市の学校に通う18歳未満の子どもです。2025年9月に可決され、10月から執行された同条例は、仕事や学習などの時間を除く余暇時間でのスマートフォンの使用を1日2時間に抑えることを推奨。また、小学生以下は午後9時まで、中学生以上は午後10時までといった時間帯の目安も示し、各家庭でルールを作るよう促しています。
条例化に至った経緯について小浮正典(こうきまさふみ)市長は、スマホを手放せなくなり、学校にも外にも出なくなった子供について相談が寄せられていたことを明かしています。同条例に強制力や罰則は設けられていませんが、条例化することで、スマートフォンの使用に関するセルフチェックや対話を促進したいとしています。
「スマホ認知症」に特化した外来クリニック
2025年6月には、東京で国内初となる「スマホ認知症」に特化した外来クリニックが開設されました。「スマホ認知症」とは、長時間使用により脳が大量の情報にさらされ、情報処理が追いつかなくなることで、一時的に物忘れなどの認知症に似た症状が現れる状態を指します。同クリニックは、スマホ認知症の予備軍は1,000万人から2,000万人ほどいると推定し、その早期発見と介入が不可欠であると警鐘を鳴らしています。診察はアプリによる受付から始まり、問診票を基にライフスタイル改善の提案や必要に応じた投薬による症状の改善を行っています。7月の時点で1日に10人ほどが診察に訪れ、その大半が30代という点も注目されています。
適切な使用で利点を最大化する
スマートフォンは、利便性や社会的つながりを提供する強力なツールです。一方、世界経済フォーラムの報告書「The Intervention Journey: A Roadmap to Effective Digital Safety Measures(介入の道筋:効果的なデジタル安全対策へのロードマップ)」が指摘するように、過剰な使用は「個人および地域社会の安全、健康とウェルビーイングに悪影響を及ぼす可能性」があります。
適切な使用の習慣を身につけることは、心身の健康を守るだけでなく、社会全体のレジリエンスを高めることにつながります。つまり、社会においてウェルビーイングを支える環境の構築が重要性であり、これは、世界保健機関(WHO)が毎年10月10日に定める「世界メンタルヘルスデー」の趣旨とも呼応しています。日本における取り組みは、自治体の条例から専門医療の対応に至るまで、政府、地域社会、企業が連携し、デジタル技術の利点を損なうことなく、新たに生じるリスクに対処できることを示しています。スマートフォンがもたらす恩恵を最大限活かしつつ、そのリスクを管理することは、日本のみならず世界にとっても重要な課題です。日本での取り組みは、健全かつ持続可能なデジタル社会の実現に貢献するものとなるでしょう。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
関連トピック:
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。