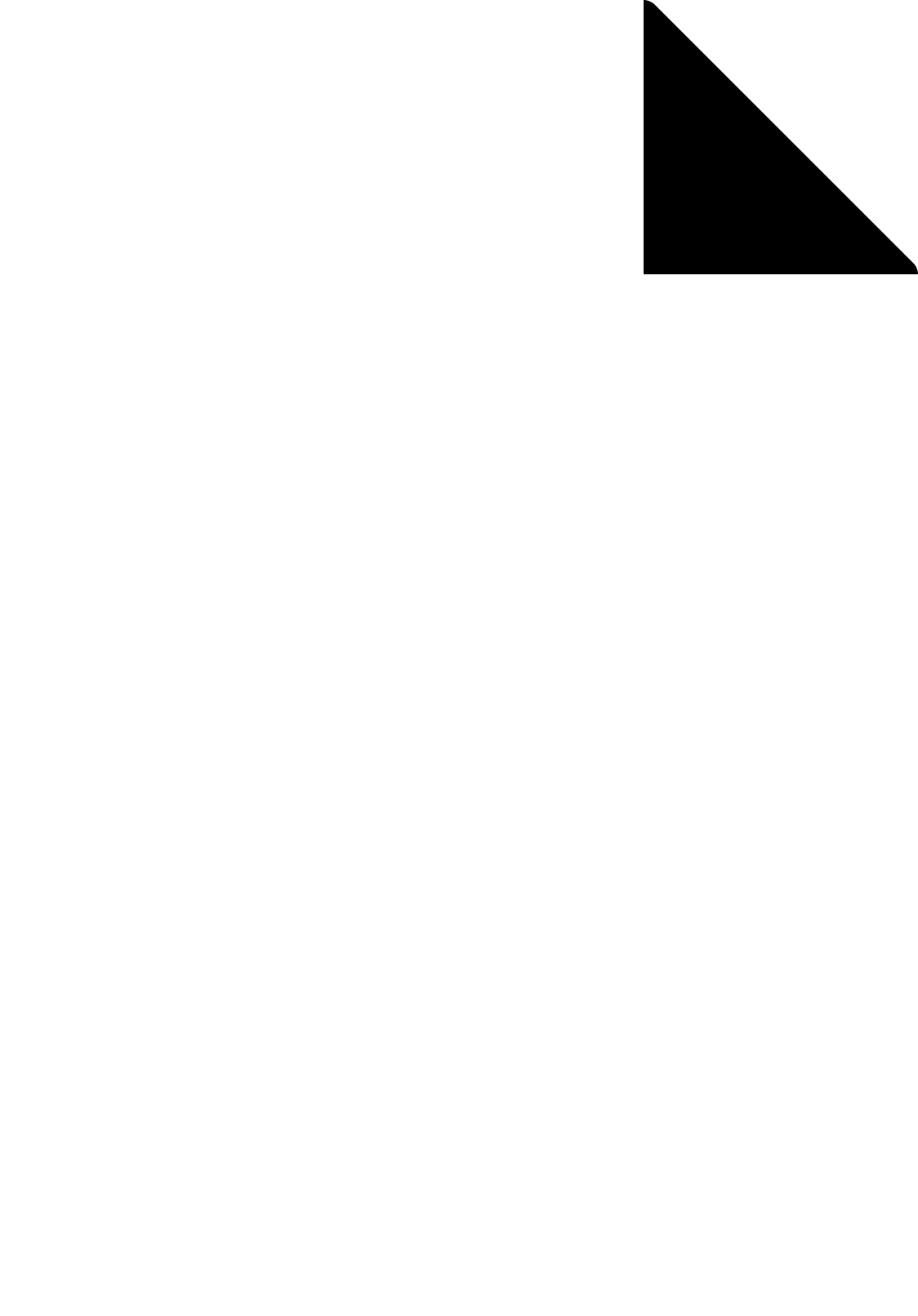官民の連携で実現する、ネイチャーポジティブな未来

2030年に向け、日本ではネイチャーポジティブに関する取り組みが進んでいます。 Image: Unsplash/Adam Dillon
- 生態系の劣化は、深刻な経済損失や世界全体の生産性の低下を招く可能性があり、国際社会は2030年までに陸域と海域の少なくとも30%を保全するという共通目標を掲げています。
- 日本においても、企業によるネイチャーポジティブな行動を後押しするための政策枠組みやガイドラインの整備が進み、自然資本の可視化や保全を促すイノベーションが広がりつつあります。
- 官民連携を基盤とした取り組みは、環境保全のみならず、サプライチェーンの強靭性や地域経済の活性化にも寄与し、持続可能な成長を支える新たなモデルとして注目されています。
健全な生態系の保全は、持続可能な経済の基盤です。2025年9月に公表された報告によると、生態系の劣化により、世界では年間最大4,300億ドルの経済損失が生じる可能性があります。この影響は5年間で2兆1,500億ドルに達し、食品生産や消費財小売業、林業、鉱業など8つの主要セクターに及びます。この推計は、世界銀行が2021年に報告した「2030年までに世界のGDPが年間2.7兆ドル減少する可能性がある」との予測とほぼ一致し、国際的な協調と国内外での迅速な対応の必要性を明確にしています。
2022年のCOP15では、生態系保全を世界的に推進するため、2030年までに陸域および海域の30%以上を保全する国際目標「30by30」が採択されました。以降、各国がこの目標に向けた具体的な取り組みを進めています。タイでは、市民主導の「30x30タイランド・コアリション」が発足し、官民および地域レベルの保全活動や取り組みを支援するガイドラインが策定されました。また、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、パナマの4カ国は、「東部熱帯太平洋海洋回廊(CMAR:Eastern Tropical Pacific Marine Corridor)」を設立。政府間の協力の枠組みとして、海洋生物多様性の保全と持続可能な利用を推進しています。
日本では、環境省が2022年に「30by30ロードマップ」を策定しました。同ロードマップでは、2030年に向けた具体的な目標として国立公園等の保護地域の拡張と管理の質の向上、保護地域以外で生物多様性保全に資する地域(OECM) の設定・管理、生物多様性の重要性や保全活動の「見える化」などを進めています。さらに、2024年3月には、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を策定し、自然資本を基盤とする経済成長の機会として、企業による実践を促しています。
日本における政策的取り組み
2030年まで残り5年を控えた2025年、日本での取り組みは加速しています。
環境省は「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を踏まえ、その実現のために各ステークホルダーに期待する行動をまとめ、2025年7月、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ(2025-2030年)」を発表。地域の自然資本を活かした地域づくり、ネイチャーポジティブ経営実践の拡大、国際競争力の強化という3つの柱をもとに、ステークホルダーとの連携を推進しています。
また、2025年8月には、政府の最新施策、関連情報情報を発信する、「ネイチャーポジティブ・ポータル」を開設し、官民の知見の共有を支援しています。
企業による実践とイノベーション
企業による行動も、ネイチャーポジティブの実現は不可欠です。2023年9月に「自然関連財務情報タスクフォース(TNFD)」の開示枠組が公表されて以降、日本では開示に取り組む企業が増加。2025年7月時点で開示を表明した日本企業は182社に上り、世界最大となっています。
生物多様性の保全と自然資本の回復を通じ、生活基盤を守り、次世代のレジリエンスを高めることができるでしょう。
”その一例が王子グループです。同社は、2024年12月に「森林破壊・転換ゼロコミットメント」、2025年2月に「生物多様性コミットメント」を策定。持続可能な森林経営や木材資源の調達、バリューチェーン全体で自然喪失要因の回避・削減を継続し、生態系の回復・再生を目指しています。
また、NTTグループ6社とバイオームは2025年3月、衛星画像解析技術と国内最大級の生物データベース「BiomeDB」を活用した広域かつ継続的な植生・生物データの収集・分析技術の開発に着手しました。これにより、自然資本の状況把握および、効果的な保全施策の立案が可能になることが期待されています。
ネイチャーポジティブ経済への移行がもたらす意義
世界経済フォーラムの報告書「The Future Of Nature And Business(自然とビジネスの未来)」(2020年)は、世界のGDPの半分以上が自然の喪失によるリスクにさらされていることを指摘しています。日本の官民による取り組みは、国内経済の安定のみならず、グローバル経済への移行を支える鍵でもあります。生物多様性の保全と自然資本の回復を通じ、生活基盤を守り、次世代のレジリエンスを高めることができるでしょう。その未来を実現するためには、官民連携による行動の加速がこれまで以上に求められています。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。