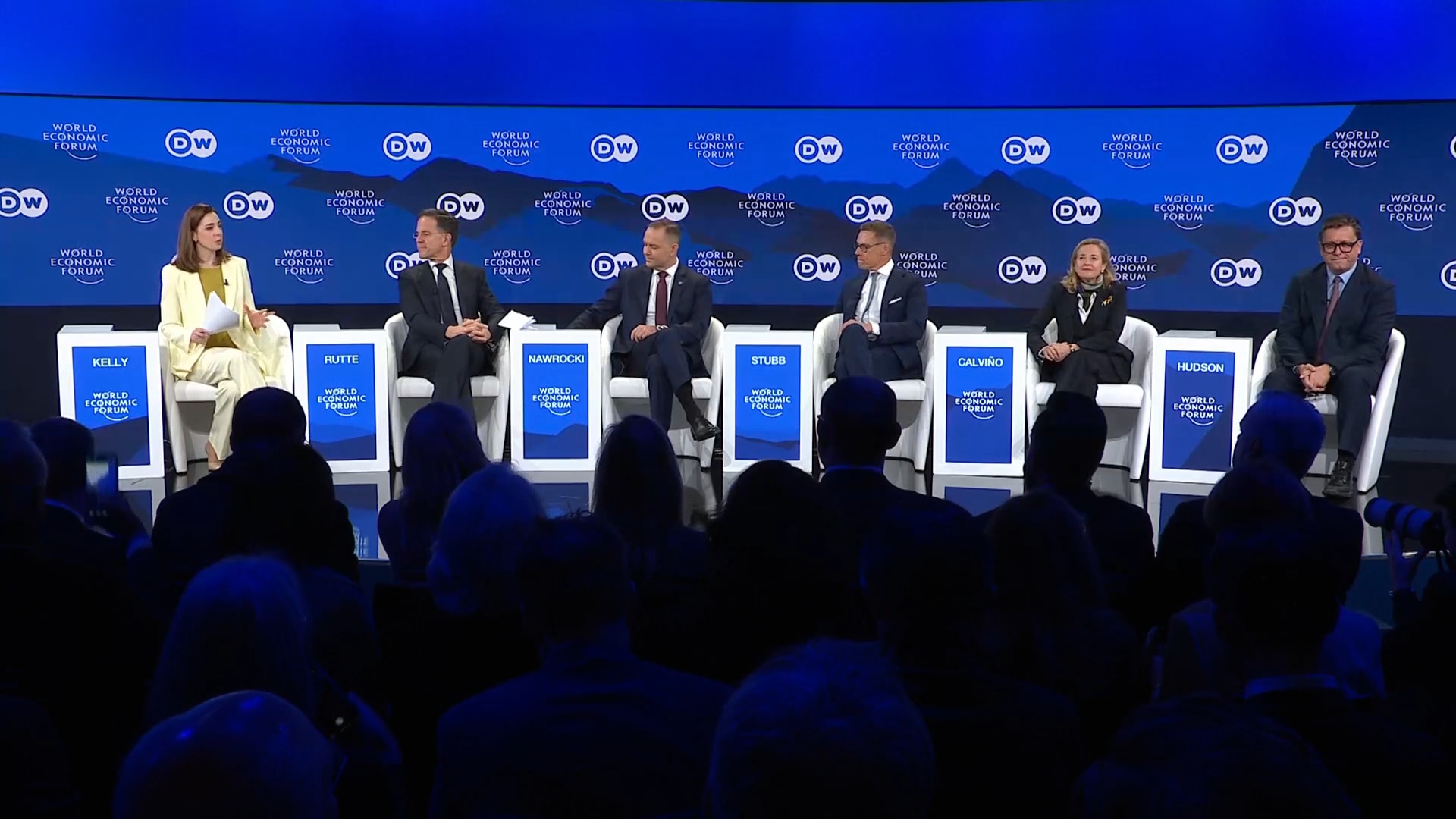歴史を継承し未来を築く、日本の平和への取り組み

広島の原爆ドームの前を流れる元安川に、1945年の原爆犠牲者を追悼する灯籠が流される様子。 Image: Reuters/Kim Kyung-Hoon
- 第二次世界大戦の終結から80年を迎えた今、平和を守り続けるために、過去の戦争から教訓を学ぶことが極めて重要です。
- 日本は唯一の被爆国として、核兵器の非人道性を伝える特別な責任があります。
- 年々高齢化する戦争経験者は、自らの体験を「語り部」となる若い世代に語り継ぎ、さらに次の世代へと物語を受け継いでいます。
2025年は、第二次世界大戦の終結から80年の節目の年です。地政学的な不安定さが高まりつつある中、過去の戦争から得た教訓を将来世代へと継承し、平和を維持するための取り組みを続けることの重要性は、かつてないほど高まっています。
日本では、戦争を直接経験した世代の高齢化が進み、その記憶や体験を次世代に受け継ぐことが課題となっています。総務省統計局によると、1945年の終戦後に生まれた日本人は、2024年10月時点で全人口の88.8%に当たる約1億991万人を占め、大多数が戦争を知らない世代です。

戦争の惨禍を正しく理解し、その記憶を風化させないことは、同じ過ちを繰り返さないための基盤です。特に、日本は世界で唯一の被爆国として、核兵器の非人道性を語りつぐ責任を担っています。そのため、戦争体験を未来に継承していくことは、国家的課題と言えるでしょう。
政府や自治体は、地域の高齢者が若い世代に体験を伝え、彼らが「語り部」としてその体験を語り継ぐための仕組みづくりを支援しています。厚生労働省は2025年度、語り部育成のための補助金を前年の4倍となる1億円に拡充しました。広島や長崎、沖縄などの被爆地・戦跡はじめ、全国各地で地域の戦争体験を継承する取り組みが広がっています。
テクノロジーを活用した新たな継承方法
若い世代の語り部育成が重要である一方、若年層が語り手となる場合、戦争当時の社会背景や感情を実体験として共有できないことから、共感の形成が難しいとの指摘もあります。このような課題を補完するする手段として、テクノロジーの活用が注目を集めています。
神奈川県は、原爆被爆者の証言をAI技術で継承する「対話型語り部講話システム」を国内の自治体として初めて導入しました。同県が設置するかながわ平和記念館は、ソフトウェア・アプリケーション開発事業などを行うシルバコンパスと連携し、同システムを開発。これは、利用者が、スクリーン上の被爆者に質問を投げかけると、録画された証言映像がAIによって解析・再生され、あたかもその場で会話しているかのような体験を提供するものです。

証言者の一人である西岡洋氏は、13歳の時に長崎で被爆し、170以上の質問に答える形で証言を収録しました。4K映像と自然言語処理技術により、来場者の質問にも的確に応じることができます。AIを活用することにより、「ただ見るだけではない対話型の映像となり、戦争体験の継承をより効果的に行うことができる」ことが期待されています。同様の仕組みは、広島の原爆資料館にも「被爆証言応答装置」として導入されています。
体験型展示を通じて共感を育む展示
テクノロジーは強力なツールである一方、現時点のAIには限界もあります。感情を真に揺さぶることが難しいという指摘や、戦争体験者の思いから遊離する可能性があるとの懸念もあります。
こうした中、日本各地の博物館では、戦争の現実を若い世代の心に訴えかけ、彼らが共感し、その経験を共有できるよう、創造的なアプローチを模索。戦争関連の展示に加え、体験型プログラムを提供する動きも広がっています。たとえば、東京の「シベリア抑留者・戦没者追悼平和祈念館」では、子どもたちが展示から学んだことを基に新聞を制作するワークショップが開かれました。
さらに注目すべき取り組みとして、東京と広島で実施された「PEACE IN THE DARK」があります。障害者の多様性やインクルージョンへの理解を深める活動で知られる「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」が主催し、同団体が世界で初めて平和をテーマにした展示です。
このプログラムでは、参加者が完全な暗闇の中を案内役に導かれ、1945年当時の家庭を再現した空間を歩き回り、日用品に触れながら、原爆投下前の広島での暮らしを追体験します。展示の最中や終了後には対話の時間が設けられ、参加者は平和の意味について深く考え、語り合います。
同プログラムは、戦争を直接知らない若い世代に知的かつ感情的な働きかけを行い、平和の価値を自ら見つめ直す契機となります。このような創造的な試みは、AIを活用したツールを補完し、より没入感のある人間中心の体験を通じて、深い理解と共感を育むものです。テクノロジーに加え、空間デザインや創造的体験を通じて戦争を追体験する試みは、今後さらに広がっていくでしょう。
世代とセクターを超えた協働で、平和を守る
「国家間の武力衝突」は、「グローバル・リスク報告書2025」において最も深刻な現在のリスクとして位置付けられています。こうした時代において、戦争の悲惨さを記憶し、平和の大切さを再確認することは、単に過去を振り返るだけでなく、現在と未来を守る行動につながります。
日本における官民連携による取り組みは、戦争によってもたらされた断絶や苦難を記憶にとどめ、世界の平和構築への貢献するための試みです。こうした動きは、世代やセクターを超えた協働の重要性を示すものであり、国際社会における平和維持の一助となることが期待されています。
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。