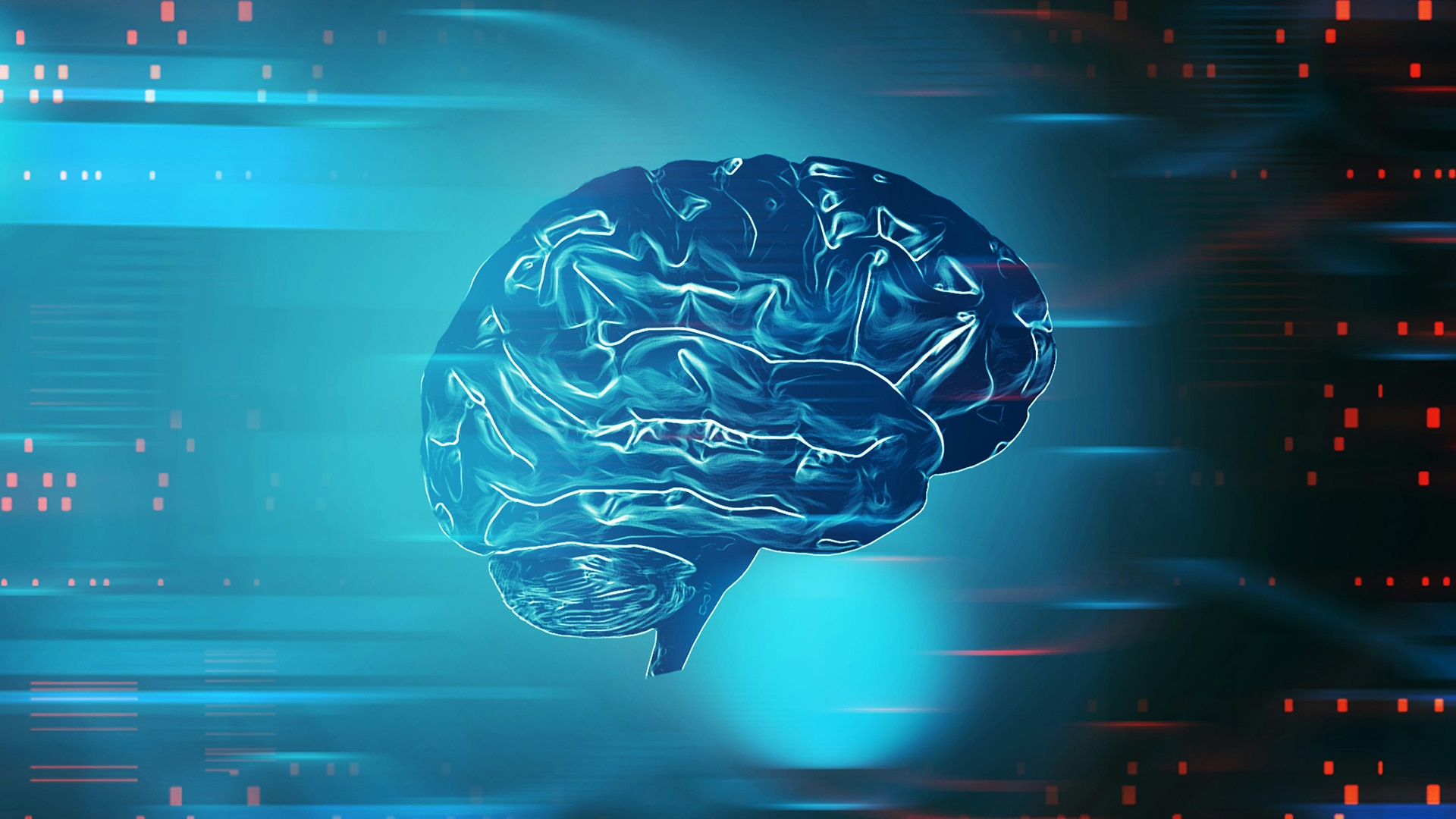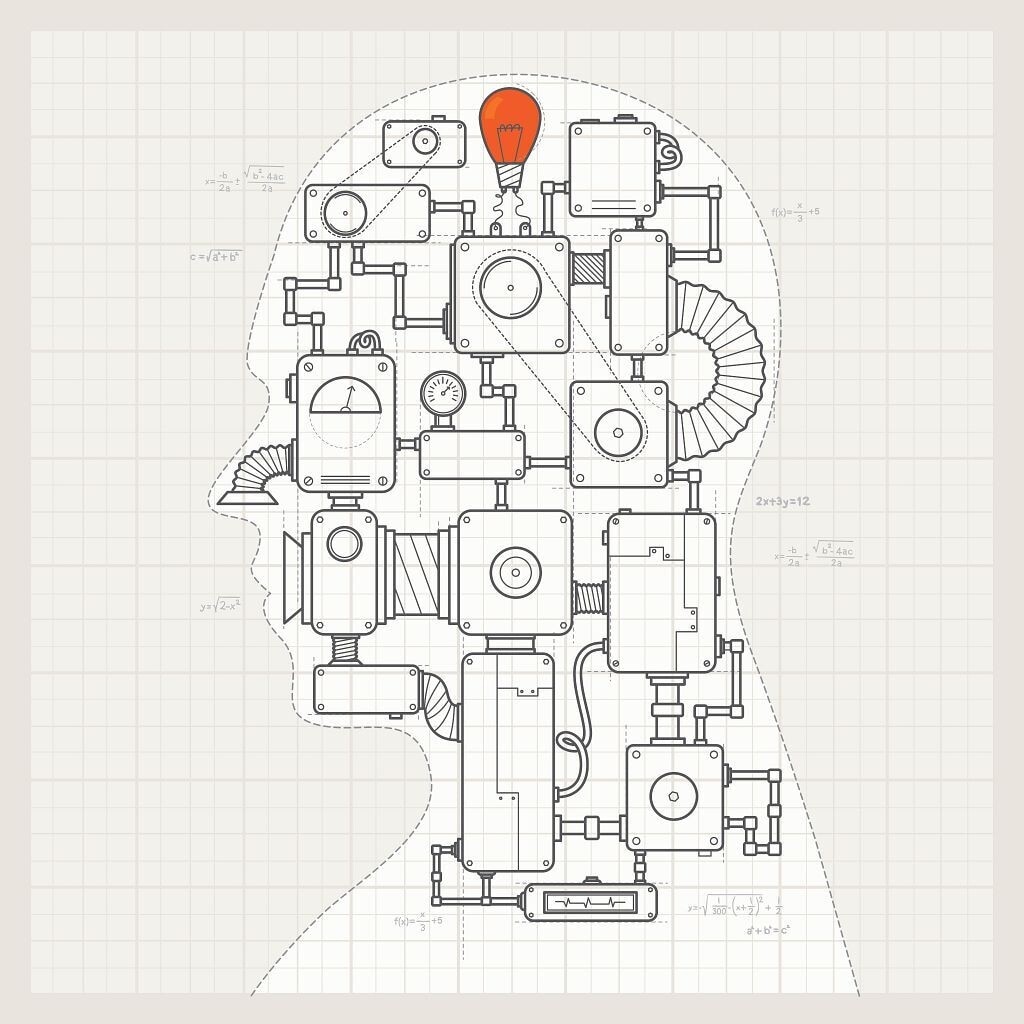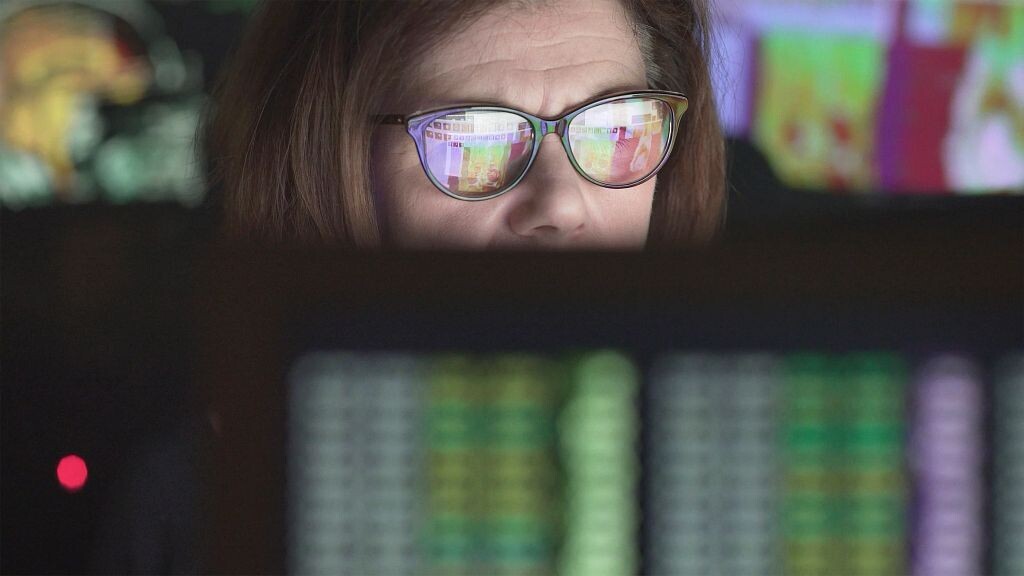「ウェルビーイング・エコノミー」でアジアが示す、新たな成長モデル

「ウェルビーイング・エコノミー」とは、進歩の概念を「生活の質」と「人間および地球の健康」を中心に再構築するものです。 Image: Unsplash/Ken Cheung
- 「ウェルビーイング・エコノミー」は、進歩の指標を「生活の質」「生態系の再生」「包摂的な繁栄」の観点から捉え直すものです。
- アジアは、その文化的価値観、家族経営企業のエコシステム、高いイノベーション力を背景に、このウェルビーイング・エコノミーを拡大する上で必然的にリーダーとなる地域です。
- 経済システムの変革には、リーダーシップの転換が必要です。これまでの統制、成長至上主義から「意識的なスチュワードシップ」と「内的な整合性」へと舵を切る必要があります。
気候変動、自然破壊、社会的課題、経済的課題が複合的に絡み合うポリクライシス(複合危機)の時代において、進捗を測る指針としての国内総生産(GDP)の限界が明らかになりつつあります。このため、新たな成長の指針、すなわち「ウェルビーイング・エコノミー」の必要性が高まっています。
ウェルビーイング・エコノミーとは、経済的意思決定において人と地球のウェルビーイング(幸福)を中核に据えるモデルです。これは決して新しい概念ではありませんが、今、これを実践に移す時機が到来しているのです。
ウェルビーイング・エコノミーは、生命のウェルビーイングと、人々と地球の繁栄を生み出すために設計されており、成功の定義を「際限のない生産性の追求」から、生活の質の向上、生態系の再生、包摂的な繁栄の促進へと転換するものです。その中での進歩は、健康や社会的コネクティビティから持続可能性、公平性、教育、経済的レジリエンスに至るまで、多様な観点で測定することができます。
ウェルビーイング・エコノミーの核心にある問いは、「経済は何のために存在し、誰のために機能すべきか」というものです。
個別事例を超えた規模でウェルビーイング・エコノミーを拡大する上で、システム思考のアプローチが有効となるでしょう。
”ニュージーランドからの教訓
ニュージーランドは、ウェルビーイング・エコノミーの世界的先駆者です。2019年から一連の「ウェルビーイング予算」を導入し、国家計画の焦点をGDPの成長から市民の生活体験へと転換しました。
同国の政府支出は、政策やプログラムが世代を超えたウェルビーイング(メンタルヘルス、子どもの貧困、家庭内暴力、生物多様性、気候変動への対応力など)にどのように貢献するかに基づいて配分されています。
2020年、同国は生活水準の枠組みである「LSF」を導入した世界最初期の国の一つとなり、政府のあらゆる施策を複数のウェルビーイング領域と整合させる取り組みを開始。どのシステムにも完璧なものはなく、実施上のギャップなどの課題は残っていますが、同国の事例はホリスティック(全体論的)な指標をガバナンスに組み込む際のモデルケースとなり得ます。
ウェルビーイング・エコノミーに向けた動きは世界的に勢いを増しています。カナダ、スコットランド、ウェールズ、フィンランド、アイスランド、ニュージーランドなどの国々は「ウェルビーイング・エコノミー・ガバメント」パートナーシップに加盟。共通の枠組みと政策革新について協力しています。
ウェルビーイング・エコノミーの実現に向けた課題
関心が高まる一方で、ウェルビーイング・エコノミーは依然として例外的な存在であり、以下のような大きな障壁が存在します。
- 経済的慣性:数十年にわたる成長重視の政策決定によって定着した考え方や制度を転換することは、容易ではありません。
- 測定の複雑さ:GDPとは異なり、ウェルビーイングは多次元的で主観的、かつ文脈依存的な概念であるため、標準化と比較が困難です。
- 短期的圧力:政治、金融システムでは、長期的なレジリエンスや公平性よりも、目先の成果が優先される傾向があります。
- 取り組みの分断化:現在のウェルビーイング関連イニシアチブは、多くの場合、国家政策や慈善活動といった枠内で個別に進められており、協調的な規模拡大が不足しています。
広範な変革を実現するための3つの道筋
これらの障壁は確かに大きいものですが、克服できない課題ではありません。システム思考のアプローチを取り、以下の3つの強力な推進力を活用することで、個別事例を超えた規模でウェルビーイング・エコノミーを拡大することが可能となります。
- 新たなリーダーシップモデルの導入。
- 文化的適合性。
- セクターを横断した強力な連携の構築。
1.「スチュワードシップ」としてのリーダーシップの再定義
ウェルビーイング・エコノミーにおいて、リーダーシップは従来のように支配力や蓄積、短期的な成果によって定義されるものではありません。むしろ、意識、思いやり、そして目的意識に根ざした「スチュワードシップ」として捉えることができます。
このウェルビーイングの時代において、リーダー個人と組織の内面的なウェルビーイングは相互に密接に関連しています。つまり、組織の各要素は全体と不可分の関係にあるのです。意識の醸成と方向性の一致がなければ、外部からの改革やその効果は脆弱で一時的なものにとどまります。
このパラダイムシフトは単なる戦略的変化を超えたものであり、瞑想やマインドフルネス、自己探求といったつながりの実践を通じて、意識の量子的な再調整が求められます。これにより、野心を責任へ、権力を奉仕へと転換していく必要があるのです。
これは単に余裕があるときにやるべきことではなく、必要不可欠な変革です。内省なしに成長を追求し続けるリーダーたちは、自らが依存するシステムそのものを不安定化させる危険を冒しています。しかし、意識を持ってリードする者は、成功を「人、地球、すべての生命の繁栄」と再定義し直すことができるのです。
2. リーダーとしてのアジア
人と自然、宇宙の調和を重んじる伝統的なアジアの文化基盤は、ウェルビーイング・エコノミーと極めて相性の良い、長期的かつ世代を超えた価値観を育んできました。
この価値観は、特に地域全体に広がるファミリービジネスにおいて生き生きと実践されています。長期的なスチュワードシップ、伝統を重んじる考え方、多世代にわたる投資戦略は、いずれもウェルビーイング・エコノミーの原則と自然に合致しています。
こうした深い文化的基盤に加え、アジアは、台頭する慈善活動リーダーシップ、イノベーション能力、そして人口動態の勢いが相まって、よりバランスの取れた再生型経済モデルを主導し、拡大していく独自の立場を築いています。
ウェルビーイング・エコノミーへの移行を示す事例は数多く存在します。
例えば、シンガポールを拠点とする企業であるTPC(ツァオ・パオ・チー)グループは、「生命のウェルビーイングに貢献し、同時に富を創造する」という使命を掲げています。
同社は企業フィランソロピーの概念を再定義し、関係性の修復(NO.17財団)、目的意識の回復(オクターブ・インスティテュート)、自然の再生(リストア・ネイチャー財団)の3つの非営利イニシアチブを事業運営に統合しています。
同社はまた、香港で社外イニシアチブ「AWE」(Association for a Well-being Economy)を開始。これは、革新的なビジネスモデルを推進し、システム的な変革を促し、企業とグローバルな機会をつなぐ共創、学習プラットフォームです。
グローバルには世界経済フォーラムと連携し、異業種間の協力とファミリービジネスの管理責任を通じて、ウェルビーイング・エコノミーの拡大を推進しています。
気候危機、自然破壊、格差の拡大といった課題が深刻化する中、レジリエンスは単に生産量だけで測定可能なものではなく、バランスの回復、公平性の促進、生命を支える生態系の再生にこそ見出されるものです。
”同フォーラムのイニシアチブであるGAEA(Giving to Amplify Earth Action)も、献身的なリーダーたちのコミュニティ形成を進めています。ビジネスはもはや単なる利益追求の手段ではなく、企業は社会において統合的かつ影響力のある主体として機能しなければなりません。その原動力となるのは目的意識であり、生命の繁栄に貢献するという使命によって導かれるべきなのです。
同様に、これらの原則の多くは中国でも静かに浸透しつつあり、ウェルビーイングを重視した発展と、調和、再生、共同繁栄を基盤としたリーダーシップが、新たな意義を見出しています。
3. エコシステムの拡大
これらの事例が示すように、GAFA、パブリックセクター、企業、慈善セクターの四者の連携が、協調的な公共政策を通じてシステム変革を実現する鍵となります。この公共政策で重視すべき点は、社会的、生態学的な成果の達成、利益と社会的使命の整合を図る民間資本の流れ、イノベーションのリスクを軽減すると同時に新たなモデルを創出する慈善資金の活用です。
例えば、東南アジアで展開されている「コール・トゥ・クリーン・イニシアチブ」では、官民の資金を組み合わせ、民間投資を引き出す仕組みであるブレンデッド・ファイナンスの手法を活用し、エネルギー安全保障と生活基盤を守ると同時に、比較的新しい石炭火力発電所の早期廃止を進めています。このような連携は、経済ニーズと長期的な生態学的・人的価値のバランスを取るウェルビーイング・エコノミーの本質を体現するものです。
欧州に拠点を置く非営利団体、ビルト・バイ・ネイチャーは、異業種間の協力を通じてウェルビーイングを推進し、排出量の多い建造環境の変革を主導しています。木造建築材などのバイオベース素材を活用した同団体の取り組みが高く評価され、GAEAアワードが授与されました。アジア太平洋地域での同団体の成長は、再生可能かつ地域社会に根ざしたデザインが、自然環境とウェルビーイングに関する目標達成をいかに促進できるかを示す好例です。
単なる数値指標を超えた、真の意味
GDPは経済成長の指標ではありますが、生活の質や地球の健全性といった、より本質的な問いには答えていません。真の進展を実現するためには、システム全体をウェルビーイングを基軸に再構築する必要があります。これは道徳的義務であると同時に、現実的な必要性でもあります。
気候危機、自然破壊、格差の拡大といった課題が深刻化する中、レジリエンスは単に生産量だけで測定可能なものではなく、バランスの回復、公平性の促進、生命を支える生態系の再生にこそ見出されるものです。
文化的な深み、家族経営企業のネットワーク、革新への意欲といった点において、アジアはこの転換を主導する独自の立場にあります。単にウェルビーイング社会を構想するだけでなく、それを共に実現していくことができるのです。
TPC会長のチャバリット・フレデリック・ツァオ氏は、現在GAEA Global Wealth Steward for Well-being(ウェルビーイング担当グローバル・ウェルス・スチュワード)を務めています。
このトピックに関する最新情報をお見逃しなく
無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
最新の情報をお届けします:
Well-being Economy
関連トピック:
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。