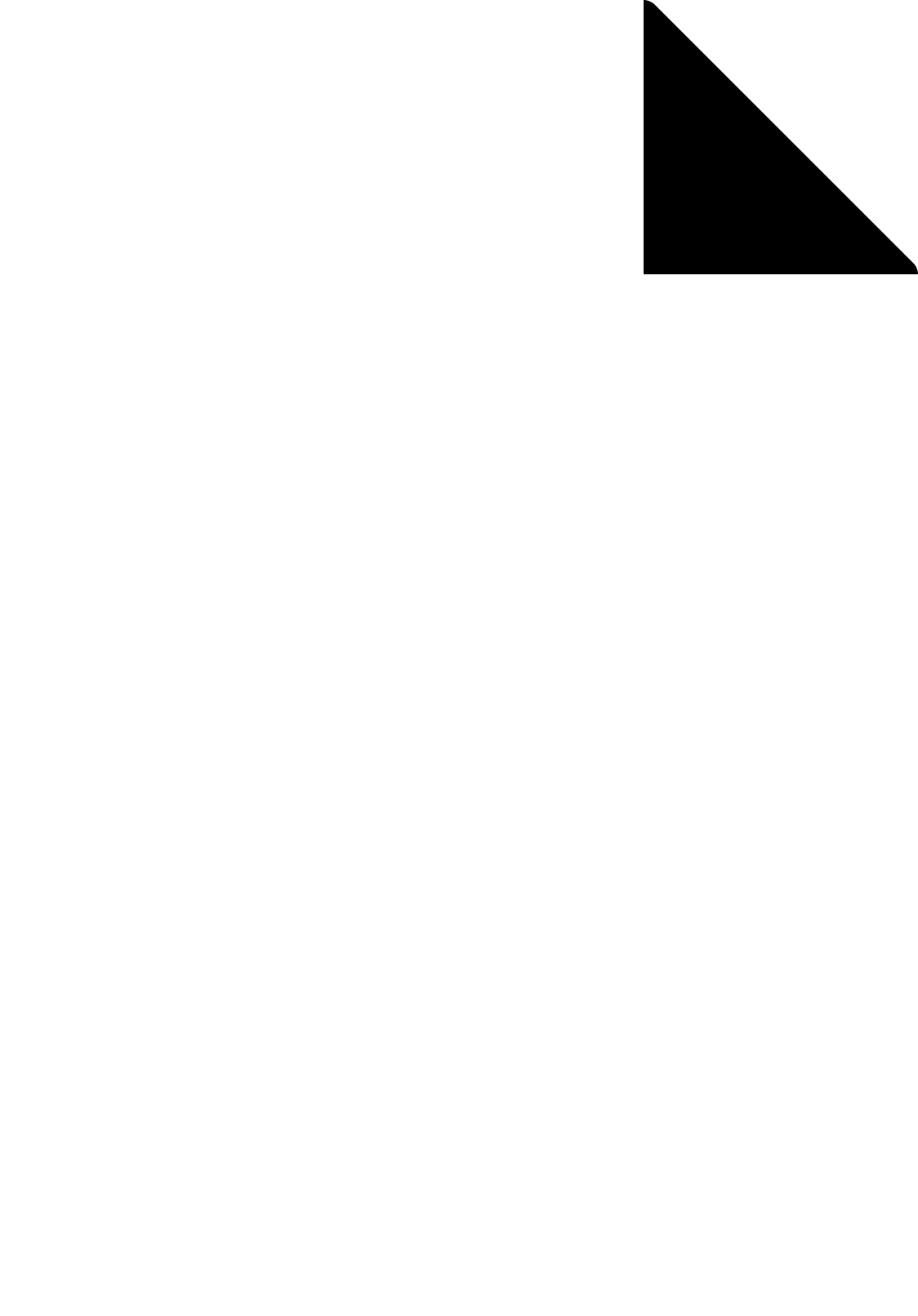今年正念場の日本経済、円安後に潜む「落とし穴」

2月10日、国際通貨基金(IMF)によれば、2019年の世界経済は2.9%成長(推定値)にとどまった。 Image: 2020年 ロイター/Kim Kyung-Hoon
国際通貨基金(IMF)によれば、2019年の世界経済は2.9%成長(推定値)にとどまった。3%を割り込むことは少なく、2000年以降では金融危機後の2009年(マイナス0.1%)と、米国のITバブルが崩壊した2001年(2.5%)だけだ。言うまでもなく、昨年の低成長の主因は、米中貿易摩擦による世界的な貿易数量と生産の落ち込みだ。
これに対し、IMFは今年1月20日、製造業や世界貿易の底打ちのほか、米中貿易交渉の進展、合意なきイギリスのEU(欧州連合)離脱懸念の軽減などを理由に、2020年の世界経済が3.3%成長まで持ち直すと予想した。
とは言え、米中通商協議第1段階の合意後も、中国の対米輸出(2019年実績、4522億ドル)のうち、半分以上の2500億ドルにはこれまでと同様、25%の関税が残る。合意の柱となっている農産品を除けば、米中間の貿易数量の復元はあまり期待できない。
しかも、新型肺炎の影響から、中国では当面、ヒトやモノの動きをはじめ経済活動が大きく制限される見込みだ。昨年の6.1%成長からの減速は不可避だろう。多くの国にとって、中国は最大もしくは主な輸出相手先であり、中国経済の減速によって、世界貿易の低迷も長引く公算が大きい。今年の世界経済も、昨年同様3%程度の低成長にとどまる可能性が高く、昨年より減速するリスクも低くない。
一方、世界の株式相場を見る限り、市場が悲観的になっているわけではない。むしろ、米国のほかドイツでも主要な株価指数が史上最高値を更新するなど、リスク選好的でさえある。春節に伴う休場明けに急落した中国の上海総合株価指数.SSECも、既に下げ幅の約7割を取り戻しており、矢継ぎ早に公表された中国当局の政策対応が市場で好感されたと言える。
際立つ日本の低迷
そうした中、日本の株式相場の低迷ぶりが目立つ。無論、この背景に日本経済の高い対中依存度や企業業績の悪化懸念が挙げられるものの、ほかにも日本の政策対応余地の乏しさを指摘できる。例えば、金融緩和に関して言えば、米国や中国には、まだ利下げ余地が残されている。米国では昨年10月以降、それまでの保有資産の縮小から拡大路線に転じた米連邦準備理事会(FRB)の柔軟性と機動性が市場センチメントの著しい好転を招いた。
これに対し、日本とユーロ圏では既に追加的な金融緩和余地が乏しく、日銀は国債の買い入れを減額しつつある。欧州中央銀行(ECB)も、戦略的検証作業を進めており、当分の間、様子見を決め込む可能性が高いだろう。
しかし、その欧州では2月18日のEU財務相理事会で、経済情勢が悪化した場合の財政出動の必要性が共有された。国ごとのばらつきはあるが、ユーロ圏全体としてみると公的債務残高(グロス)の対名目GDP(国内総生産)比は85.4%(2019年見込み)と日本(同、237.1%)や米国(同、106.9%)よりも低い。ドイツにいたっては61.7%とさらに低い。
つまり、ユーロ圏は日本と同じように金融緩和余地が乏しい半面、財政拡張政策の自由度は相対的に高く、これが日独の株式相場の明暗を分けている一因ではないか。ちなみに中国の公的債務残高は50.6%と低いため、金融緩和と合わせた政策対応余地は大きい。
結局、日本は長い間、金融緩和と財政拡張ともに異次元級の大盤振る舞いを続けた上、正常化に踏み出すこともないまま、再び世界の低成長局面に遭遇するおそれが強い。昨年の日本の第4・四半期実質GDP成長率は予想を大幅に下回り、2020年第1・四半期の訪日外国人の急減も避けられない。6月いっぱいで消費税増税対策としてのポイント還元が終わる予定であり、東京オリンピック後の建設需要の落ち込みを指摘する声も強い。
こうした局面でこそ、強い政治的リーダーシップも必要だが、最近の複数の世論調査にみられる安倍晋三政権の支持率低下は気になるところだ。こうしてみると、2020年、日本経済は正念場を迎えると言って過言ではない。
米株高とドル高は当面続く
さて、為替市場に目をやると、ドル/円JPY=EBSは年始こそ107円台まで下落したが、その後は堅調に推移している。特に2月19日には1日で1円70銭以上も上昇し、統計的には約2.5%でしか生じない「2シグマ」を上回る水準まで駆け上がった。
もっとも、G10通貨(豪ドル、ニュージーランドドル、日本円、スイスフラン、ノルウェークローネ、スウェーデンクローナ、ユーロ、英ポンド、加ドル、米ドル)の年初来のパフォーマンスを比べると、円はドル、スイスフラン、加ドルに次ぐ4番手に位置しており、残る6通貨に対しては年初に比べて円高だ。低成長や低インフレが意識され、世界的に長期金利は低迷しており、これが日本と海外との名目金利差の縮小と円高圧力を招いている。
加えて、1月下旬以降、インバウンド消費の大幅な落ち込みも懸念され、市場で観測されるブレークイーブンインフレ率(10年物)やインフレスワップ金利(5年先5年)が、いずれも第2次安倍政権発足後の最低水準に低下する場面もみられている。こうしたインフレ期待の低下は、実質金利と円の押し上げ要因だ。ドル高の陰で見えにくくはなっているが、いずれの材料もそろって円の続落を示唆しているわけではない。
これに対して、ドルは堅調な株価と歩調を合わせ、騰勢を保っている。その株価ではS&P500指数.SPXの予想株価収益率(予想PER)は19.5倍まで上昇しており、金融危機後で最高水準を記録した2017年終盤の20倍に接近中だ。ただ、日本とは異なり、企業業績の改善を伴っているだけに、必ずしも割高とは言えない。
加えて、米国の長期金利が低迷している(=債券価格が高止まりしている)ことも、債券と相対的に比較した株価の割高感を打ち消している。したがって、しばらくの間は、米国の株高とドル高が並走する可能性が高いだろう。
とは言え、2月の米議会証言で、パウエルFRB議長は、短期財務省証券(Tビル)の買い入れを今年の7月以降、縮小していく方針を示している。昨年10月以降、FRBによるこのTビル買い入れの開始とともに、米国の株式相場も騰勢を強めていた。それだけに、今後の政策調整を契機に株式相場上昇の勢いが和らいだり、軟化すればドル高にも歯止めがかかりそうだ。
それまでは新年度入り前後の本邦勢による対外証券投資活発化への思惑も手伝い、最大で昨年の高値112円40銭も視界に入ってくる。もっとも、経験則上、2シグマを超えて到達したドル高・円安水準は、よほどの材料が続かない限り、持続性に乏しいのも事実。高値水準やその到達時期の予想は難しいが、112円近辺をピークに、年後半にかけてドル/円が小緩んでいく展開を予想している。
*この記事は、Reutersのコラムを転載したものです。
このトピックに関する最新情報をお見逃しなく
無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
最新の情報をお届けします:
日本
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。