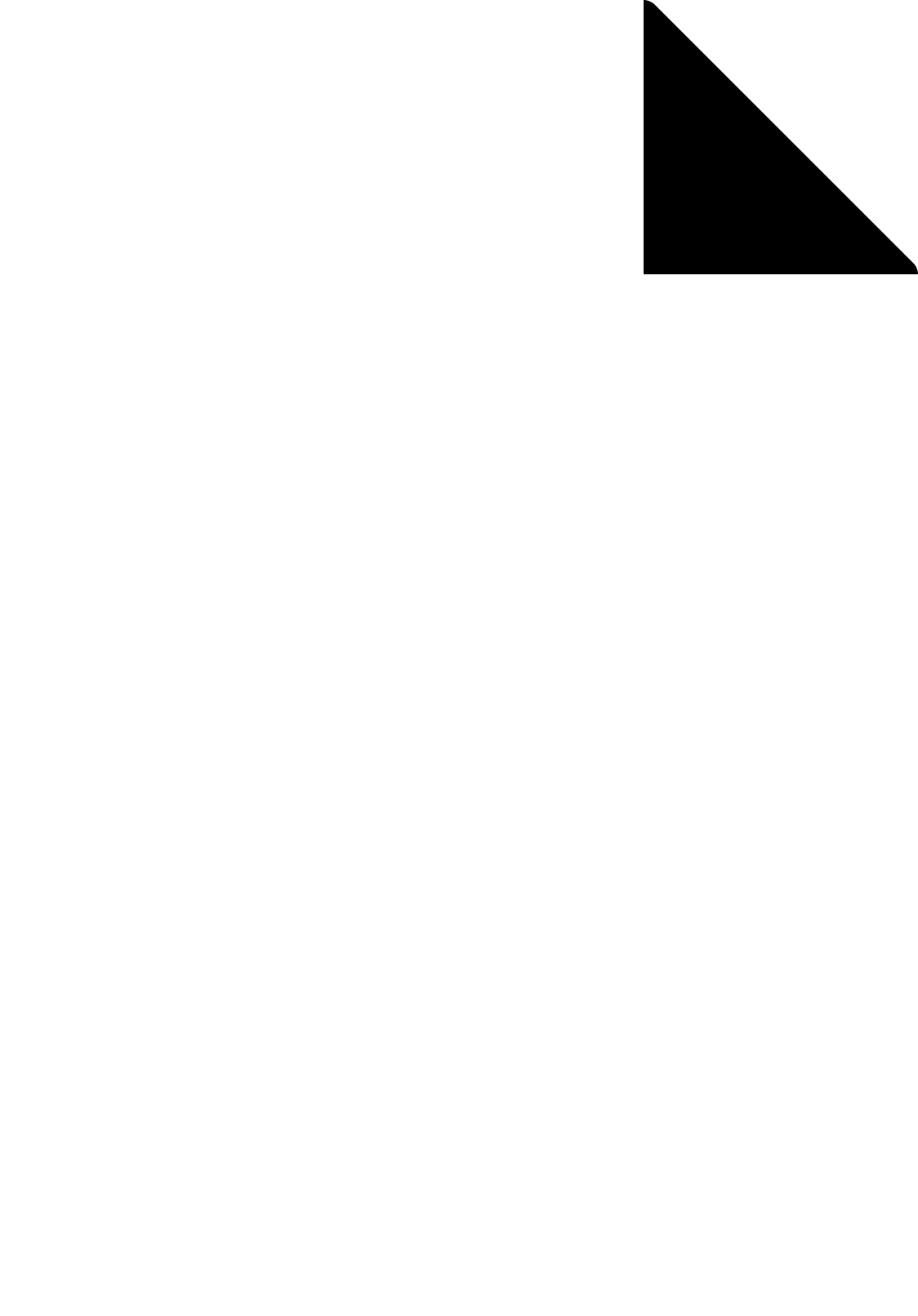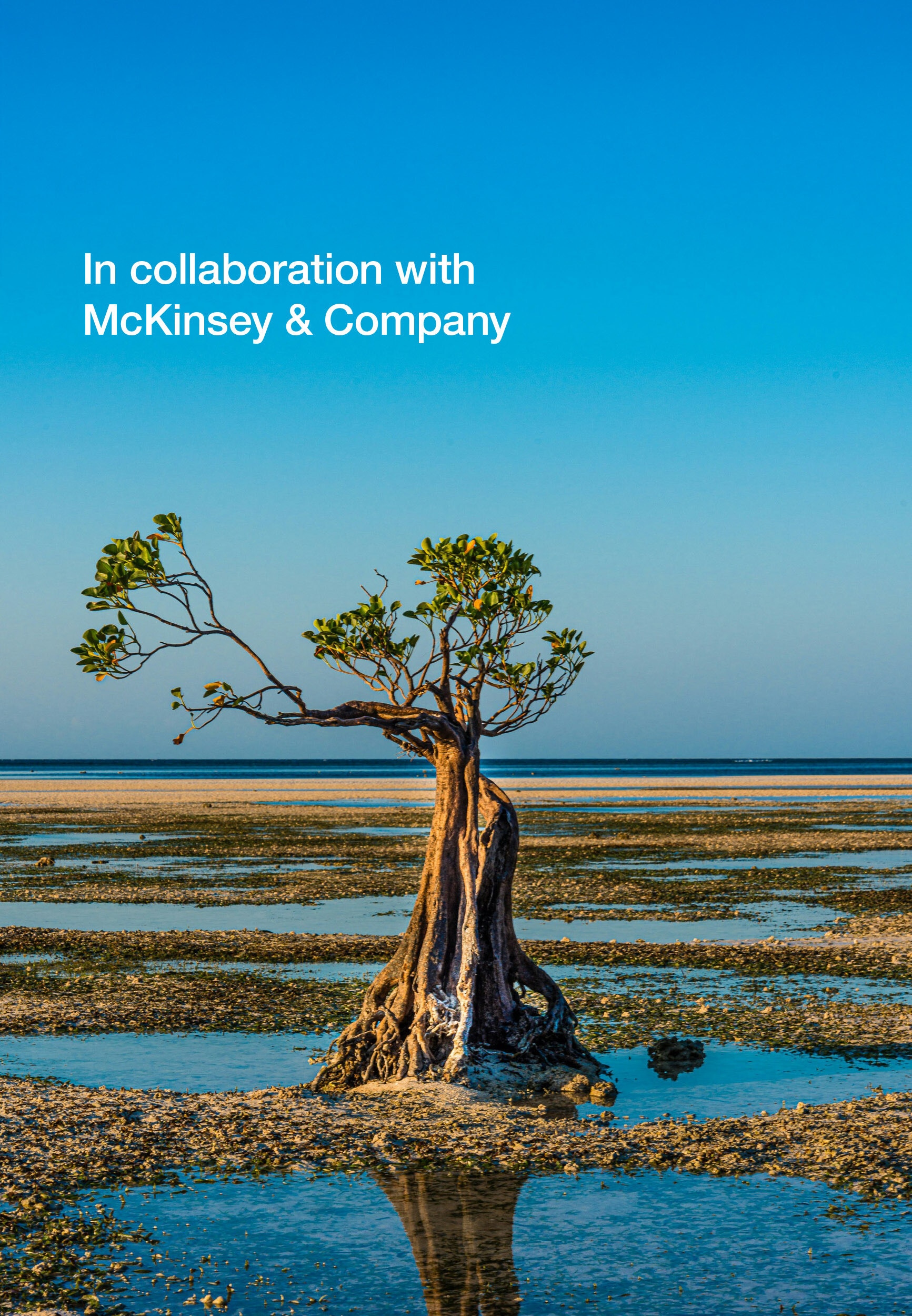サステナブルな漁業を目指し、中国と日本が進める変革

WTOの漁業補助金協定は、2022年6月にコンセンサスで採択されました。 Image: WEF/iStockphoto
- 全世界で、漁業に支払われる補助金は年間350億米ドルにのぼり、そのうち60%以上が乱獲の原因となっています。
- しかし、WTOの漁業補助金協定を批准しているのは、中国や日本を含む40カ国に過ぎず、発効にはさらに69カ国の批准が必要です。
- 日本と中国は、有害な漁業補助金を廃止し、ポジティブな公共投資に切り替えようとする流れに変える役割を果たすことができます。
いわゆる「有害な漁業」補助金は、長い間、世界中で乱獲や破壊的な漁業慣行の原因となってきました。近年、全世界の漁業補助金は年間350億米ドル以上にのぼり、その60%が有害なものとみなされています。
この有害な漁業補助金は、世界的な影響を及ぼしているとの研究結果があります。ある調査では、その37%が、国際水域や公海での漁業を支援していることが明らかになっています。これは、海洋生物の多様性、小規模漁業者への公正な機会、沿岸漁業コミュニティの食料安全保障に悪影響を及ぼすと同時に、国連締約国が2015年に全会一致で合意した持続可能な開発目標(SDGs)のうち、海洋に関する持続可能な開発目標(SDGs)、SDGs目標14の達成にも深刻な影響を及ぼすことになります。
2022年6月に採択された、世界貿易機関(WTO)の漁業補助金協定(Agreementon Fisheries Subsidies)では、SDGs目標14のターゲット6に基づき、有害な漁業補助金の廃止を通じて水産資源の保護を促進するための多国間ルールが定められています。この協定により、違法・無報告・無規制(IUU)漁業や、枯渇しているあるいは管理されていない水産資源の漁業に対する補助金が禁止されます。さらに、漁船の国旗の掛けかえのような有害な慣行に対処し、新たな透明性ある規則を導入することも目指しています。
しかし、この長期にわたる交渉を発効へつなげるためには、WTO加盟国の少なくとも3分の2が、各国政府を通じて正式に受け入れを承認する必要があります。109カ国以上の承認が必要ですが、現時点で正式に受け入れを済ませているのは、中国(2023年6月27日)と日本(2023年7月4日)を含む40カ国です。
漁業補助金依存からの脱却
日本は、世界で上位5か国に入る漁業補助金支給国です。日本の漁獲量は、一時期のピーク量の3分の1程度にまで減少していますが、漁業関係者などの多くは、依然として国からの漁業補助金に大きく依存しています。
こうした中、日本の水産業界と政府は、過去10年間にわたり、効果の望めない延命措置を段階的に見直すと同時に、本質的な環境の持続可能性と社会的責任の確保に向けた連携のために様々なレベルで内部調整を進めてきました。
その結果、2020年には、70年ぶりの大改正となった改正漁業法が施行され、2022年には、IUU漁業による水産物が国内市場に流入するのを防ぐため、日本初の行政措置である「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」が施行されました。
今回、漁業補助金に関するWTO協定を正式に承認したことは、日本が国策を転換し、漁業と海洋利用の持続可能性にコミットしていることをグローバル社会へ示す、より一層強いメッセージとなっています。
一方、中国は、30年にわたり世界最大の漁業国の一つであり、現在、全世界の海洋天然漁業水揚げ量の15~19%を占めています。こうした大規模な天然漁業は、環境に大きな負荷をかけています。中国近海の4つの海(渤海、黄海、東シナ海、南シナ海)は、世界で最も乱獲が行われている海域であり、見境のない過度な漁獲が栄養カスケードに深刻な影響を引き起こしています。このような海洋食物連鎖におけるドミノ効果によって、海洋生物の多様性は著しく失われています。
中国の有害な漁業補助金は、こうした状況を作り上げた主な要因であり、経済的な利益を求めた結果、中国の漁獲能力が生態学的な持続可能性をはるかに超えるところまで追い込んできました。
しかし、中国がこの10年間、より持続可能な漁業に向けた取り組みを継続的に強化していることは、変化に向かう良い兆しです。例えば、2014年から2019年にかけて、国内漁船団への燃料補助金を60%削減させるとしたほか、2020年末までに遠洋漁船団の上限を3,000隻に制限する方針も示しました。中国は、WTO漁業補助金交渉への参加と並行して、入港する漁獲物の厳格な管理を通じて、IUU漁業を防止、抑止、排除するための違法漁業防止寄港国措置協定(PSMA)を批准する意向を示しています。
こうした取り組み以外にも、中国全土で海洋巨大生物の個体数回復への関心が高まっています。2020年にはクジラ、イルカ、すべてのウミガメが長いリストに挙げられ、国家第一級または第二級保護種に指定されましたが、いずれも乱獲とIUU漁業の犠牲になっている生物です。一方、2021年には、質の高いよりサステナブルな漁業の発展を目指す、新たな漁業開発助成金管理措置(Management Measures of funds for Fisheries Development Subsidies)が発表されました。
これらの新たな措置は、今後、国内漁業への燃料補助金が、人工礁の大規模開発や資源増強を基盤とする海洋牧場などの活動への補助金に転用される可能性を示しています。また、漁業と養殖設備の近代化、インフラ建設、漁業資源の調査と監視、そして、国際条約の遵守を約束しています。
世界最大の漁業国であり、水産物の貿易と消費においても重要な存在である日本と中国が、WTO漁業補助金協定を承認したことは、世界中の漁業コミュニティと海洋のバランスを取り戻し、調和を再構築する上で大きな進歩となります。WTO加盟国164カ国の3分の2が正式に署名すれば、この協定は運用可能となります。しかし、有害な漁業補助金を撤廃し、海洋、食料安全保障、生活を保護するためには、すべてのWTO加盟国が効果的で透明性の高い実施メカニズムを採用することが不可欠です。
補助金をポジティブな公共投資に転換する
日本や中国のような主要な漁業国・水産物の貿易消費国が重要な変革を起こすためには、ネガティブな補助金を廃止し、より決定的な行動を促すことが不可欠です。重要なのは、現在の補助金をポジティブな公共投資に置き換えるよう促すことです。
例えば、WTO協定に関わる漁業が、乱獲されている資源、持続的に漁獲されている資源、あるいは十分に漁獲されていない資源を対象としているかどうかを評価するために、より科学的根拠に基づいた行動を取らなければなりません。漁業関係者は、船団の収容力や、魚種または魚種グループごとの水揚げデータを公表することが求められます。同様に、補助金を受けている漁船の詳細情報も開示する必要があります。資源と重要生息地の保全および管理措置を強化し、有効性を評価すると同時に、期限をさらに厳しく定めて公表する必要があります。
有害な補助金が、表向きは持続可能性を実現するための対策として説明されていながら、実際には、重要な漁業管理改革を阻害しかねない活動を支援する目的で再利用されないようにすることが、極めて重要です。例えば、資源増強や人工礁を基盤とする大規模な海洋牧場への投資は、その有効性を正当化するため、より強力な科学的モニタリングと調査に基づく根拠が必要です。
燃料補助金を、設備の近代化や漁業インフラへの投資に置き換えることは、近代化されたモニタリングや管理、監視策とセットでなければ、漁獲能力の増大と搾取の拡大につながる可能性があります。さらに、過去の漁業補助金のポートフォリオも、環境にさらに優しい代替案の多くも、大企業を優遇するために策定されているため、小規模漁業者は見過ごされ、疎外された立場に置かれています。有害な補助金の一部は、本来、より持続可能な未来に向け、グリーンで公正な移行を求める小規模漁業コミュニティに再投資されるべきなのです。
日本と中国は、東シナ海と多くの水産資源を共有しています。そのため、国内の水産学や管理・保全対策についてより活発な交流が行われることは、両国にとって有益です。日本は、沿岸生態系の健全性と社会的公平性を共に強化するために、伝統的な小規模漁業コミュニティを組織化し関与させる方法に関して、模範となるかもしれません。日本と中国は、地域漁業管理機関(Regional Fisheries Management Organizations: RFMO)内外で、水産学や遠洋漁業のサステナブルな管理・保全措置に関する情報やアイデアを積極的に交換することが可能でしょう。
グローバルな施行とガイダンス
水産物の主要な貿易消費国である日本と中国は、WTO漁業補助金協定のグローバルな施行を後押しする重要な役割を果たすことができます。また、WTO協定で禁止されている有害な補助金による水産物が市場に出回ることを防ぐことで、グローバル社会をよりサステナブルな消費パターンへと導くこともできる立場にあります。
協力することで、私たちの海の健康、日本や中国、そして世界が共有する青い地球の魚、漁業者、漁業に関わる人々のウェルビーイング(幸福)を失わせる有害な漁業補助金を撤廃できるのです。
世界経済フォーラムの海洋行動計画(Ocean Action Agenda)の、フレンズ・オブ・オーシャン・アクション(Friends of Ocean Action)は、海洋の健康を取り戻すため、迅速にソリューションを推進する多様なグローバルリーダーたちのコミュニティです。
このトピックに関する最新情報をお見逃しなく
無料アカウントを作成し、パーソナライズされたコンテンツコレクション(最新の出版物や分析が掲載)にアクセスしてください。
ライセンスと転載
世界経済フォーラムの記事は、Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licenseに基づき、利用規約に従って転載することができます。
この記事は著者の意見を反映したものであり、世界経済フォーラムの主張によるものではありません。
最新の情報をお届けします:
海洋生物の再生
「フォーラム・ストーリー」ニュースレター ウィークリー
世界の課題を読み解くインサイトと分析を、毎週配信。
もっと知る 自然と生物多様性すべて見る
Laura Fisher, David Mueller and Anika Duggal
2025年11月14日